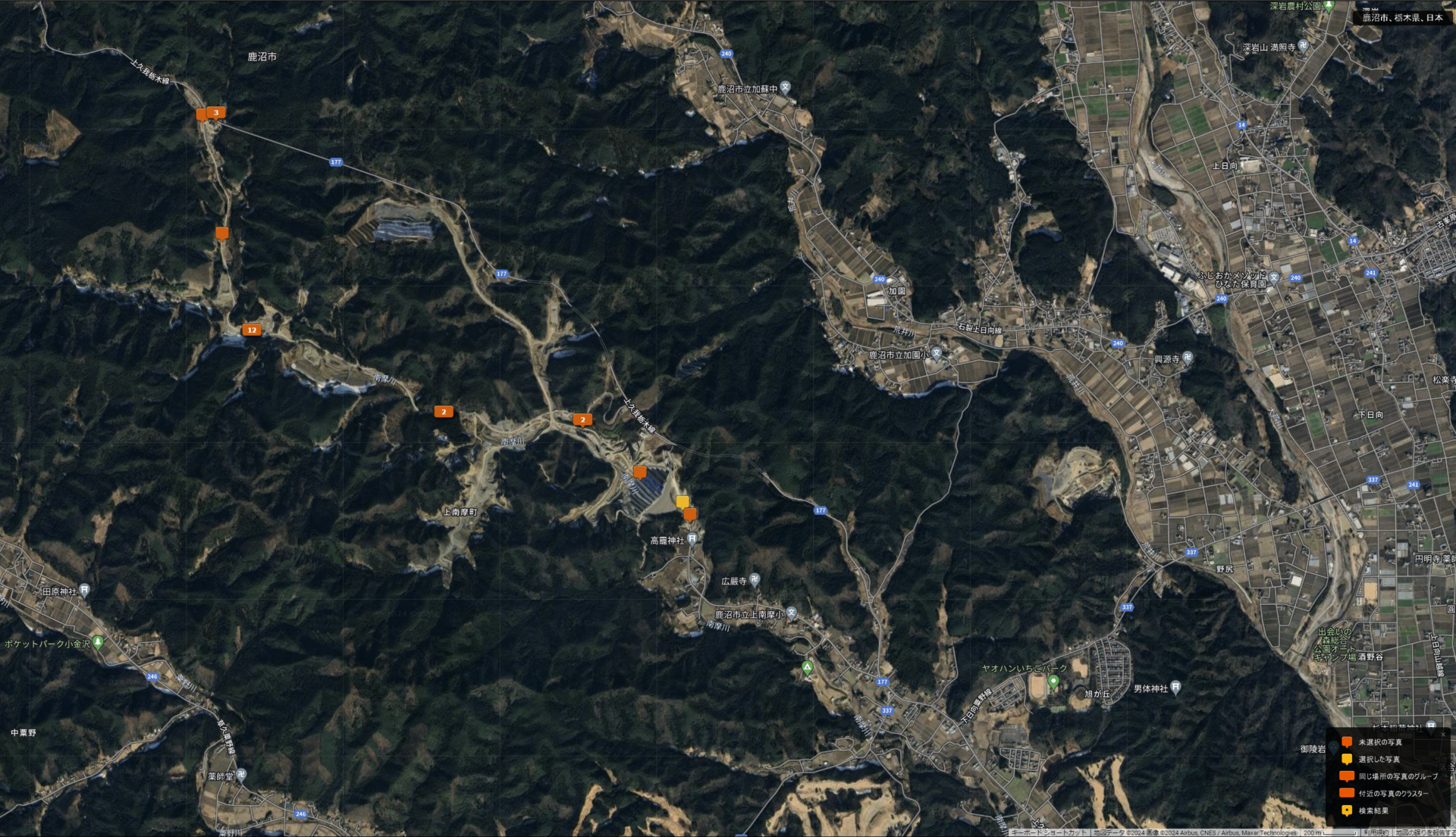35mmレンズは標準レンズたる50mmより少し画角が広く、35mmが標準レンズという人も世の中に少なからず存在しますし、私もその一人です。
屋内でも屋外でも、汎用的に使える画角で、昔の単焦点コンパクトカメラでも35mmや38mmというレンズはよく使われていました。
ずっと50mmの画角が苦手だったワタシ(今は苦手意識はなくなり好きな画角になりました)には、35mmレンズは必ず持ち出したい1本となり、いつの間にかレンズも増えました(笑
レンズ交換式のNIKKORレンズだけで4本あります。ま、世の中にはもっとたくさん持っている人もいますが、この4本はそれぞれ思い入れのある4本です。

左からNIKKOR-S Auto 35mm F2.8(後期型), AI AF Nikkor 35mm f/2D, AF-S NIKKOR 35mm f/1.8G ED, NIKKOR Z 35mm f/1.8 Sです。NIKKOR-Sは1959年発売の前期型ではなく、後期型になりますが、NikonのFマウントレンズでも古いものになります。これは親父が1970年に新品で買ったものです。
AIレンズは持っていなくて、いきなりAFレンズのAI AFとなりますが、これが自分にとっての最初の35mm交換レンズです。これを長年使い、待望のAF-Sは初めて予約して買ったレンズでした。そしてNIKKOR Zは、Zマウントで初の単焦点レンズとして2018年位発売されたレンズになります。Zマウントレンズはハズレがないので、試したくて購入しました。
新しくなるほどレンズが大きくなっていますね。古いほど光学系も機構もシンプルとも言えます。Zマウントではマウント径が一眼レフのFマウントより大きいため、大きい径と短いフランジバックを活かした製品づくりをしているせいか、大きめのレンズが多いですね。
ここからは三脚を据えて、レンズ交換しつつ各f値で撮り比べをしています。
今回は中距離風景編、ということで、練馬の光が丘公園にやってきました。
ここはかつて陸軍飛行場があった場所であり、戦後はアメリカ軍が駐留していた場所でもあります。なので、とても広いのですよね。息子もサッカーの練習試合でたまに使っていたりします。自転車で走るもよし、ランニングもよし、スケボーで遊べルるエリアもあり、BBQエリアもあり、なんでもあるんです。こういう撮影テストにピッタリの場所です。
カメラはNikon Z8を使用し、ISO感度は64に固定、AWBは自然光オート、絞り優先のマルチパターン測光で撮影しています。
1本のみMFレンズのNIKKOR-S Auto 35mm F2.8は非CPUレンズなので、カメラ側にあらかじめレンズ情報を入力しています。
現像はLightroom Classicで未調整撮って出しで出力しています。
描写だけでなく、絞りによる露出のばらつきも確認してみてください。
NIKKOR-S Auto 35mm F2.8
半世紀以上前のレンズだけあり、開放では画面中心でわずかに球面収差による影響が見られなくはないものの、なかなか解像力は悪くないです。正直なところ、こんなによく写るとは思っていませんでしたね。
このレンズはAI改造をしていないため、AF一眼レフではフィルム機でもデジタルでも使用していなかったレンズです。Zマウント機へはFTZ IIを使用して撮影していますが、初期のAuto NIKKORレンズはAIレンズ行こうと違ってわずかに寸法の公差設定などが違うそうで、レンズによっては装着が硬かったり外しにくいものがあるため、公式には装着できないことにはなっていますが、自己責任で装着の上撮影しています。確かに手持ちのこの個体は少し装着は硬めでした。






絞るほど解像感は増していき、f11では周辺までかっちり解像します。非CPUレンズの場合は絞り込み測光になるため、実絞りと計算値と乖離はそうそうないはずですが、何故かf11とf16では露出オーバー気味になってしまいました。
もしFやF2をお持ちなら、このレンズは標準レンズとしてコンパクトで確かな描写を得られそうです。F2.8と他のレンズより若干暗いのも(光学設計的に無理がない)古い割に描写の良さを感じさせる要因でしょう。
カラーバランスはやや寒色寄りに感じますね。
AI AF Nikkor 35mm f/2D
80年代の光学設計のレンズ、Auto NIKKORより30年新しいだけに、開放から安心して使えますね。グルグルボケの原因になる非点収差もあまり感じませんね。ただワタシが持っているレンズの個体差なのか、右下隅がほかより像が流れてしまっている気がします。ただf11まで絞ると全体としてかっちり解像します。中心部は開放から何ら問題なく使えそう。
このレンズに限りませんが、初期のAF Nikkorレンズ、ごく一部を除一眼レフではAF時にフォーカスリングが回転するタイプ故に、MFの操作性がスカスカです。MFレンズのようなネットリ感を出せないのは、フォーカスリングごと回る機構によるものです。
そのためか、フォーカスの繰り出しによるガタツキもあり、こうした四隅の一部のみがボケるといった症状、この時代の85mm以下のAF単焦点レンズでよく見かけるような気がします。
中古で買う場合はこうした個体差が出やすいことに注意が必要です。







絞るほど解像感が増していくのは最近の新しい設計のレンズでは味わえない感じです。かといって開放も緩くはないです。
AF一眼レフならフィルムでもデジタルでもオススメの1本です。とてもコンパクトです。ただ外装は昔のプラ外装故に、現代のプラ外装ほど高級感は出せないですね。チープ感も結構あります。使い込むほどテカってしまいます。
色味は少し黄色味が強い気がします。
AF-S NIKKOR 35mm f/1.8G ED
2014年発売の本レンズ、流石にまだ新しいだけあります。開放でも中心部はキリッと描写します。周辺はわずかに非点収差による影響はなくはないですが、デフォーカスしていくボケのグラデーションが良いですね。なので、絞り開放でも自然にボケていく感じです。個人的に大好きな描写で、どんな撮影もそつなくこなせるのと、AF-SによりAFもスパッと快速とまで言わないものの、ストレスなく使えます。もちろんFTZ II経由でZマウントボディでもAFが使えます。フル機能で使えるので、AF一眼レフでもミラーレスでも、ちゃんと使えるのがありがたいです。







開放からしっかり解像するので、絞り込むほど解像感が増していく感じはありませんが、f11まで絞ると、この撮影条件では周辺までちゃんと解像しますね。f16だと回折の影響が出てくるので、f11までが実用でしょう。
色もニュートラルに感じますね。
NIKKOR Z 35mm f/1.8 S
実はAF-Sより4年新しいだけです。2018年発売。が、描写がぐっと上がったのはミラーレス専用設計で、口径が大きくフランジバックが短いZマウントの性能を如何なく発揮出来るからでしょう。
開放ではことさらカリカリ感を出していなことに好感が持てます。描写の繊細さが出ています。解像力だけ見ると、ほとんどAF-Sと変わらないですが、デフォーカスしていく部分のつながりがAF-Sより更に上をいっているのではないでしょうか?
少し手前のボケに二線ボケが出ていますが、そこまで目立つ感じではないですね、








絞りによる解像力の変化はもっとも少ない気がします。とにかくグラデーションが豊かですし、f16まで絞っても回折の影響は少なめです。個人的には風景ならf11が良いと思います。
暗部の階調もよく出ていますし、風景でカリカリしないのは本当に好感が持てます。
色味もよりニュートラルで、Nikonで言われがちな黄色味もこのレンズは感じませんね。
光学設計はNikonではない(KONICA MINOLTA?)とも言われていますが、そんなことはどうでもよく、さすが最新ミラーレス専用レンズだけあります。デビューから7年近く経ちますが、まだまだII型は不要でしょう。
Zマウントユーザーは1ポンあって損はないレンズです。
作例が多いので今回はここまで。他にもいくつかのパターンで撮影しましたので、ぼちぼちアップしたいと思います。
Zマウントユーザーならスナップにこの1本。f/1.4よりも描写は良いです。
AF-Sレンズの場合、安価なDX(APS-C)フォーマット用レンズとフルサイズFX対応の以下のレンズとは描写は別物です。APS-Cのデジタル一眼レフでもこちらのレンズがおすすめです。