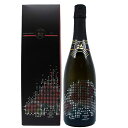天気予報が大雨で行くかどうか迷った静浜基地。2日前に予報が変わって大雨は朝まで、ということでこの予報に賭けて行ってきました。
午前8時まで大雨が降っていてこれは無理かなと思っていたら、雨が止み、それどころか晴れ間も見えて、状況開始!ってことで撮影ポイントへ。
実は静浜基地撮影は初めて。事前にGoogleマップで確認していましたが、やっぱり現地に来てみると色々想像と違いますね。
T-4の事故があったためか、内容は色々変更が入ったようですが、それでも中止にならずに開催してくれたことに感謝です。
オープニングフライトは9時からの予定でしたが、まず2機のT-7が上がりました。どうやら無線を聞くに、上空の天候確認なども行っていたようです。
この時には嘘のように青空も出てきて日差しが照っていました。雨が降らないだけで終始曇り予報だったのですが、見事に晴れましたね。
そして展示飛行開始。T-7はスバルが開発したT-3練習機をさらに改良した機体で、航空自衛隊のパイロット訓練生が最初に乗る初級練習機です。
スピードは当然遅いけど、戦闘機より旋回半径が小さく、プロペラを止めたくないのでシャッタースピードを下げなければならないので、望遠レンズ撮影にとっては難易度の高い機体です。ある意味戦闘機より難しい面もあります。
オープニングフライトは見事に晴れてなかなか良かったです。そして難しい撮影。プロペラ機は斜め後ろ姿も生えますね。
元々この後予定されていたT-4は事故の影響もありT-4時代が飛べないため中止でしたが、浜松救難隊のU-125A、百里基地から来る予定だった3SQのF-2も結局キャンセルになったようです。また、C-2輸送機、C-130H輸送機やKC-767給油機のフライトもキャンセルとなったようです。
ただ、飛行開発実験団(通称飛実)のF-15J (32-8941)とF-2B (03-8105)はフライトを実施。予定では2機での機動飛行だったのが、編隊航過1回と、各機が別々に機動飛行を実施しました。
この頃からまた雲が来てしまったのが残念でした。F-2Bはこの撮影ポイントでは遠すぎ近すぎといった具合でしたね。今回は初めてなのでよくわからなかったけど、次回以降は少しポイントを変えて撮りたいですね。
この後移動しつつUH-60Jの救難展示を見たりしながら基地内へ。
静岡県警のA109Eを見つつ、最後のT-7編隊飛行へ。
曇りなのが残念だったけど、雨が降らず良かった! 基地内も売店辺りはかなりぬかるんでいて、あの大雨の早朝によくテントを設置したなぁと思いました。
そして午後、密かに楽しみにしていたT-7Jrを見れて満足でした。
ええやん! 編隊飛行ならぬ編隊走行。昔ブイブイ言わせていたw隊員さんもいたのかな?
ってことで、強行軍で撮影に行ってきましたが、のんびりした雰囲気で良かったです。ブルーインパルスが来ていたら、もっと混んでいたでしょうけど(同日ブルーインパルスが行く予定だった別の航空祭は中止)、また行きたいなと思いました。静岡グルメもあるしね。