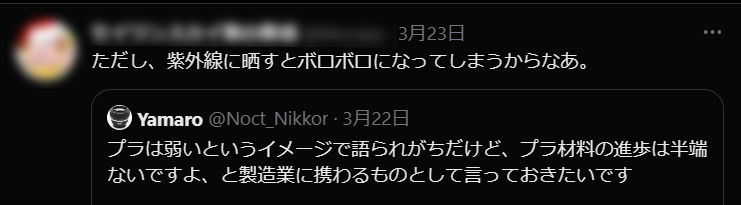金曜日、CP+2025の2日目。実はこの日、マイナンバーカードの更新があり、午後引き取りに区役所に行かなければならなく、せっかく午後仕事の休みを取ったので、マイナカード更新後にCP+ に行くことに。
マイナカード更新が予定よりも早めに終わったのは良いけど、遠いんですよね、会場のパシフィコ横浜。結局15時半頃に着いたので、18時閉場までの約2時間半程度しか時間がないため、見たいところのみを重点的に周ることにしました。よって写真少なめです。
基本アクセサリや説明を聞きたいところを中心です。
TEAC/TASCAM
真っ先に行ったブースがTEAC・TASCAM。動画系の音質向上を考えていまして。


XLRマイクアダプターCA-XLR2dですが、3種類(Canon, Fujifilm, その他アナログ入力用)ありまして、Nikonは外部音声のアクセサリポートによるデジタル入力非対応のため、最終的にはカメラ本体のステレオミニマイク入力端子に入れなければならず、音質的に向上するのか(特にS/N比)興味がありました。
が、肝心の展示機のNikon Z 9のバッテリ切れ、おまけにマイクアダプター自体も電池切れと、2日目なのに準備の悪さが目立ちました。しかも説明員さんはあまりカメラに詳しくないのが残念。音質そのものは、隣りにあったOM-1IIの内蔵マイクとの比較で、確かにかなり音質が良いのはわかりました。が、やはりどうせなら外部レコーダー入れたほうが確実かなという気も。なので、導入するとしたら、隣りにあったタイムコードジェネレーター搭載のレコーダー、FR-AV2かなぁと。こちらなら32bit Floatで録音できるので、録音レベルを気にしなくても良いですから。
焦点工房
言わずとしれた、海外のマウントアダプターやレンズなどアクセサリ類の輸入代理店からは、MonsterAdapter LA-FZ1をまず試しました。
Nikon純正よりも前に、なんとAFモータ非内蔵レンズをZマウント機でAF動作可能なアダプタで、マウントアダプターにAFモータを内蔵しています。
純正は恐らく様々な事情でこういったものが難しいのでしょうね。


試したところ、まだまだ試作品、色々と問題が。
まずはカメラの電源を入れるとずっとなり続けるカチカチと言う異音。後から知ったのですが、レンズの絞り連動レバーを連打している音だそうです。
カメラ側で設定した絞りにするためには、CPUレンズの場合、絞りは最小絞りに設定しているので、それは設定通りになっていますが、実際のところこれがうまく機能していないようですね。
実際の動作は動画で撮ってみました。
ずーっとカチカチ鳴り続けているのは絞り連動レバーの音らしいのですが、AFもまだ近場では合わないとか、ウォブリング動作を繰り返すとか、絞りをボディ側で操作しようとしても反応がないとか(ずっとf1.8のまま)不安定で、ベータ版にすら達していない感じです。
元々が一眼レフの位相差センサに合わせた特性なので、位相差の検出範囲が構造上どうしても狭くなる像面位相差センサとコントラスト方式のミラーレスでは、レンズデータを持たせておかないとかなり動作不安定なんでしょうね。
Nikon純正のFTZ/FTZ IIはモータ内蔵レンズ(AF-S/AF-P/AF-I)のみの対応で、その本数約90本ですが、恐らく各レンズのデータを持たせていて、距離エンコーダを内蔵している、比較的新しいor古いものは上級レンズが多い(つまり各種収差が少ない)からこそ、Zマウントレンズと遜色なく動作させられているとは思います。
MonsterAdapterがどこまでそういったことを出来るのか、まあこういうのは遊び要素も多いですから、完璧を求めちゃいけませんね。ロマンです、ロマンを買うのです。
そしてもう1つ注目なのは、TTArtisan 203Tで、何とこのカメラ、蛇腹のクラシックなスタイルの完全機械式カメラで、何とチェキでおなじみのインスタントフィルムinstaxで撮影可能なカメラで、フィルム排出も電動ではなく回転式レバーで行うようです。


質感はさほど高くはなく、ジャバラ部分は皮ではなく布製っぽいですが、チープすぎず高級すぎず、こうしたカメラが現役だった頃の質感に近いのが好感持てます。
昨今フィルムが高くなりすぎ、現像受付できる店が極端に減り、気軽にフィルム撮影できる環境ではなくなりつつある今、instaxを使うカメラというのはなかなか目の付け所が良いですね。instaxならすぐに無くなることはないでしょう。むしろ今人気で、Fujifilmの写真部門でもかなり売上が良いそうですから。
こちらは秋に発売予定、値段は不明ですが、わりと欲しいカメラですね。
ちょうどHASEO氏の公演も行われていました。
Videndum(Manfrotto/Gitzo/Lowepro/JOBY)
動画用の一脚、色々試してみました。
このフルードカーボンビデオ一脚MVMXPROC5、一見華奢に見えて、剛性感はアルミのもう少し太いタイプと変わらず、なかなか使いやすそう。
去年運動会用にこれの1世代前のアルミ版を使いましたが、なかなか良かったけどもう少し軽いといいなと思っていたので、これは候補にしたい1つです。
アウトレット品なら買えそうだけど、この値段出すならもうちょっと頑張ってGitzoかなとも思ったり
Nikon/RED Z CINEMA
結局ここが時間的にも最後に。動画編集(特にDavinci Resolve)関係で色々聞こうと思って訪ねたら、肝心のDavinci Resolveを動かしているマシン(某PCショップの高級動画編集マシン)のグラボの調子が悪いとかで、全然サクサク動かない。これだったらうちの環境のほうが数段階的だわ~となりつつ、同時に展示されていたASUSのモニタも結構良かったな。
で、なんとREDのシネカメラV-RAPTOR [X] Z Mountを触らせてもらえるとな!



おねーさんが解説してくれて持たせてもらいました。全くどう使うかわからない、文字通りプロ用カメラですが、モニターに出てくる絵がもう映画っぽくてスゲー(笑
ブース柄、映画関係者と思われる外国人のお客もちらほら見かけました。
なにせNikonのRED買収は、業界を賑わせましたからね。


一体実際にどれくらいNikon Z 9で動画撮影が行われているかわかりませんが、少なくともNikonは気合が入っているようです。そろそろII型の足音も聞こえてきそうな感じですが、Z 9自体はまだまだフラッグシップ機として君臨、動画もN-RAW 8.1K 60pで撮影可能で、Panasonic S1RIIという強力な動画ライバル機も出現しましたが、それはさておき新しい動画向け電動ズーム搭載のレンズNIKKOR Z 28-135mm f/4 PZを初めて試せました。
なかなかズムーズに動くズームですが、もう少し感度が低いと良いかなぁ。またAFはかなり素早く、スチルでの動体撮影も余裕そうと感じましたが、逆にカメラ側でAFを一番遅い設定にしてもまだ動画用としては速く感じました。もう少しゆっくりフォーカスできるとよいですね。
レンズの操作性自体はかなりよく、MFもとてもやりやすい。映画のような撮影なら、MFのほうが何かと都合は良いかもしれませんね。
あとこのレンズ、アウトフォーカスした背景の玉ボケがきれいで、それに感動しました。これでスチル撮る人は少ないでしょうけど(スチルなら絶対Z 24-120mm買った方が良いです)、かなりボケ味にも留意していると感じました。
ここで時間切れ。18時です。せめて19時までやってくれたらなぁ…。
話題のSIGMA BFや300-600mmを見たかったけど、残念終了です。
今回は一部Z 24-200mm、それ以外は軽量なZ 40mm f/2でお気軽撮影でした。結構良いんですよZ 40mm。
ということで、次に向かいました。
ほんまアホやな…横浜から銀座へ。ちょっとした戦利品もゲットしましたが、その話題はそのうち。大したものではないですよ。

































































































![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/34a30351.2364a6fe.34a30352.22d7144b/?me_id=1238086&item_id=10001033&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fsake-makino%2Fcabinet%2F00906082%2Fimg56345753.jpg%3F_ex%3D300x300&s=300x300&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/34a305cb.8bf44929.34a305cc.9ebf5b55/?me_id=1300186&item_id=10000019&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fmangando%2Fcabinet%2F03922193%2F22usukawa_image3.jpg%3F_ex%3D300x300&s=300x300&t=picttext)