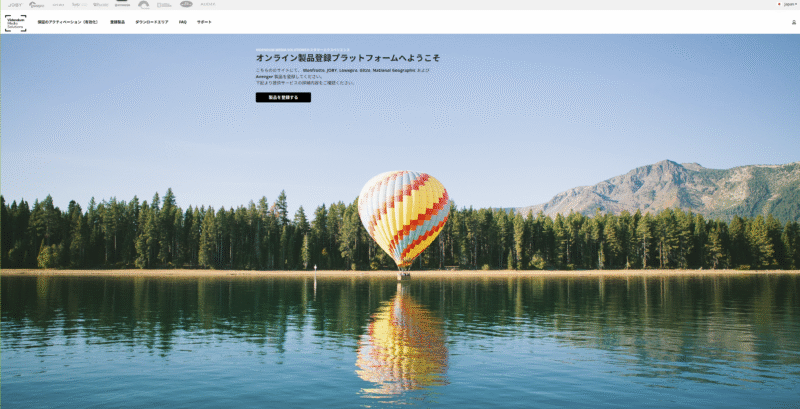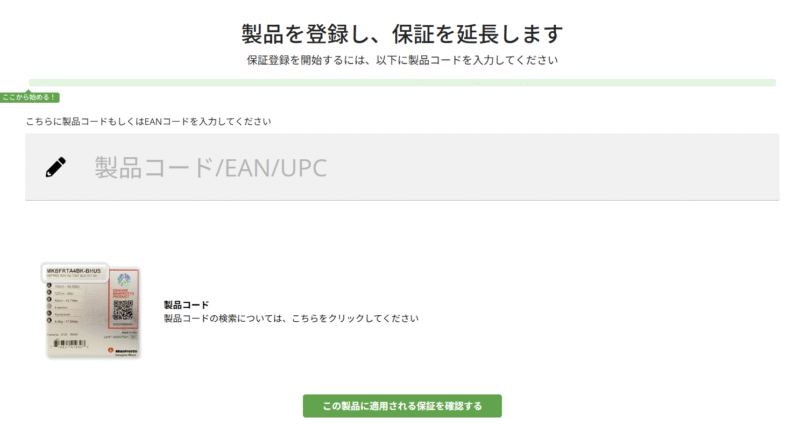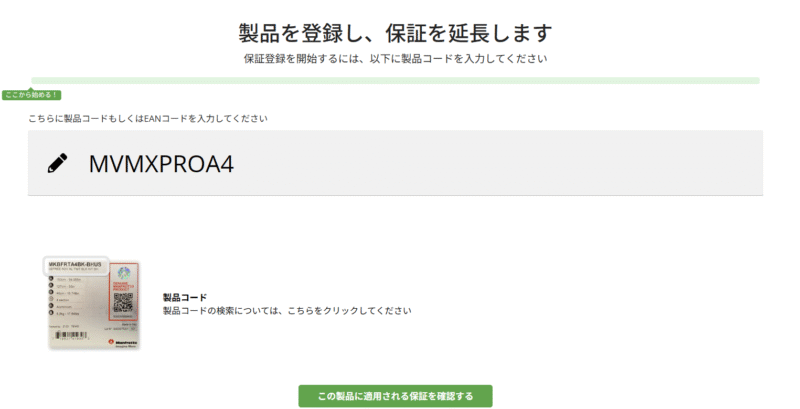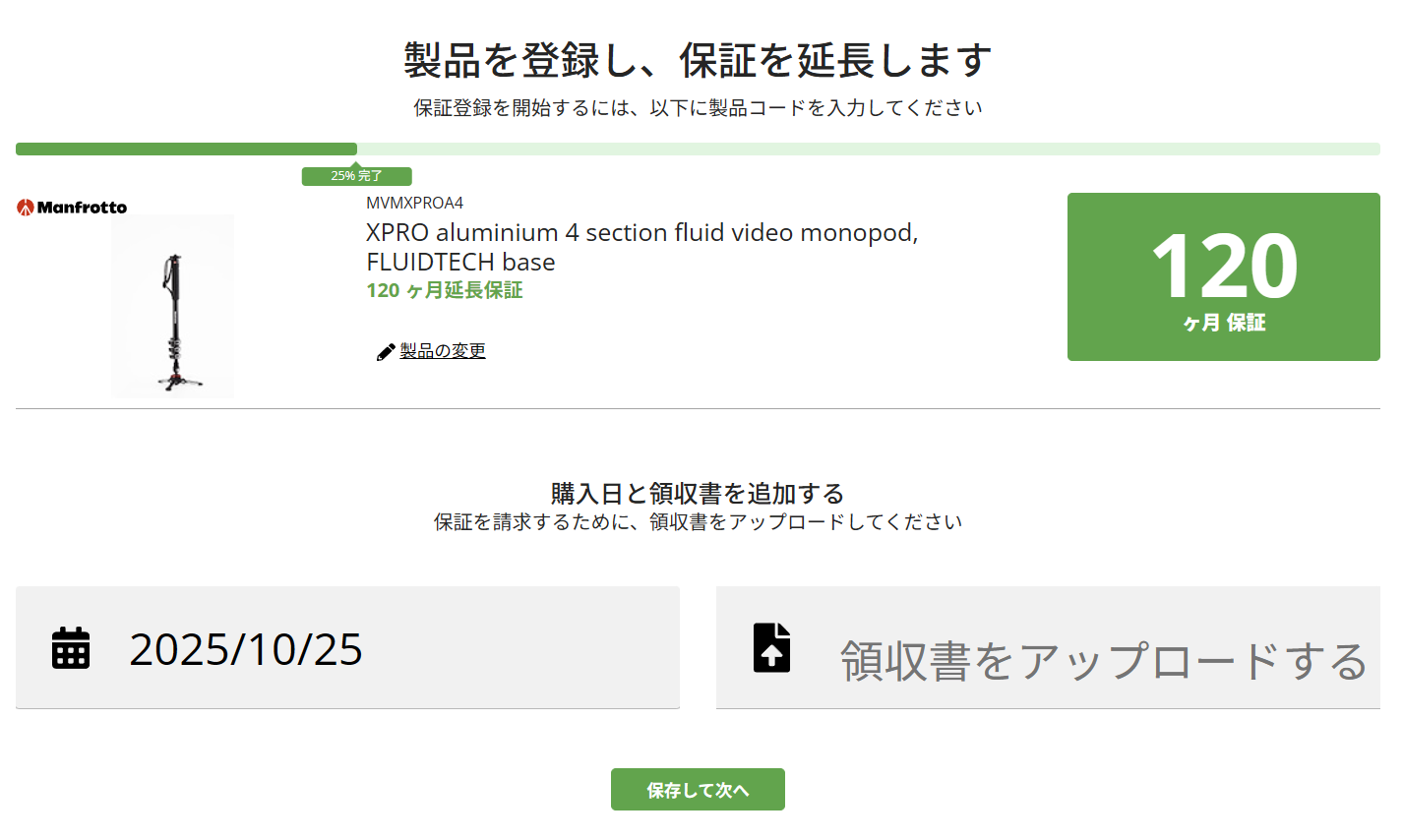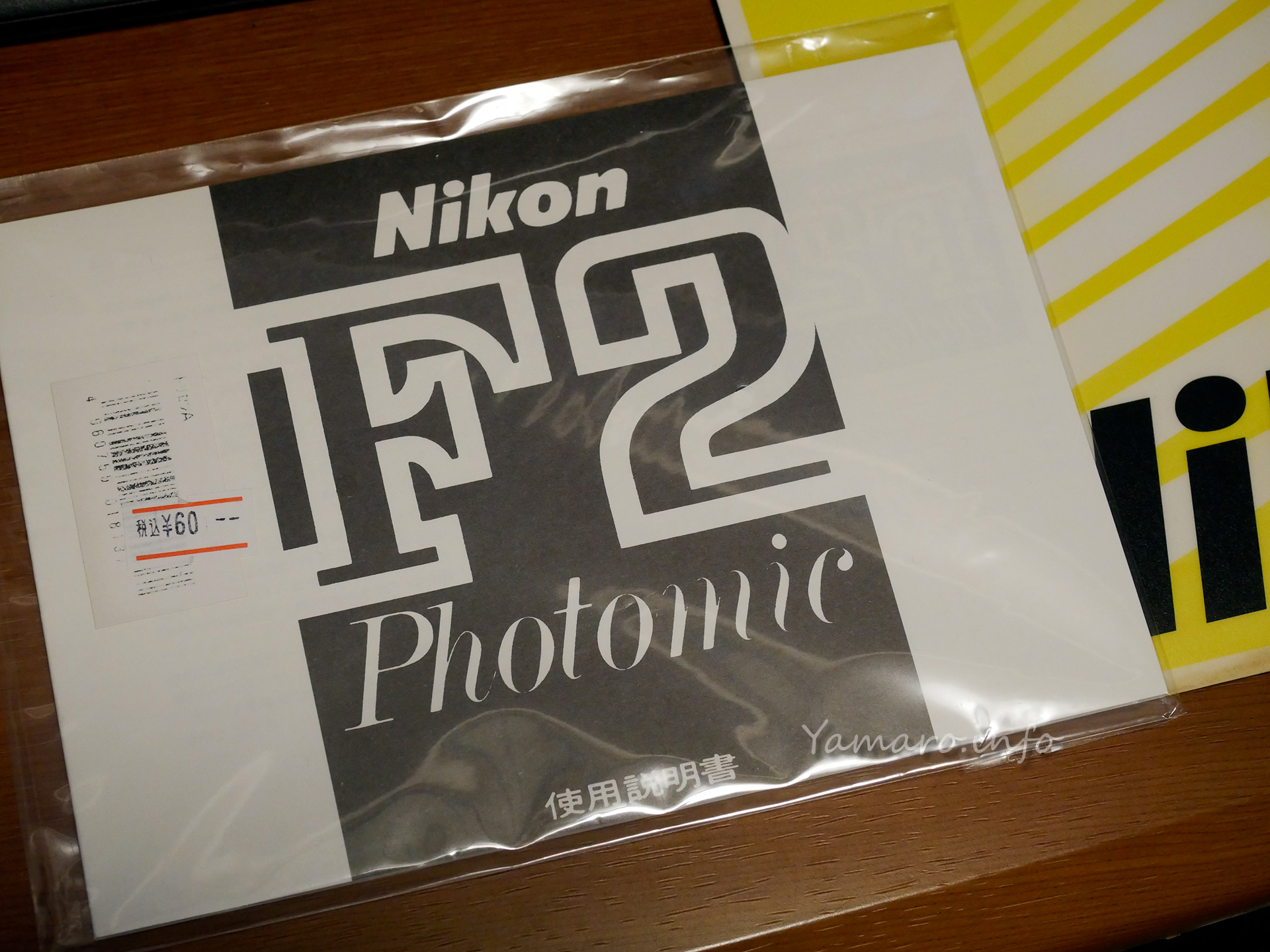東京都なんですよ奥多摩は。鳩ノ巣周辺の廃墟散策、廃墟がなくても中々の絶景スポットでもあります。
先日行った際はまだ紅葉には早かったです。2025年は11月中旬から下旬にかけてが見頃と思われます。
絶景ですが、一歩先が崖な場所もあります。柵はありません。十分注意しましょう。
撮影に際しては、カメラと三脚をセットして、自分はなるべく崖に近づかないようにしました。
最近はデジタルカメラも手ブレ補正、高感度耐性の良さから三脚を使わない人も増えました。が、カメラの基本感度で、三脚に据えてじっくり撮るのも良いです。
Nikon Z8は高画素機、積層型CMOSセンサで電子シャッターのみなので、センサの熱ノイズはどうしても出やすいカメラです。でもこうしてISO64という低い基本感度で撮影すれば、そうしたノイズは気になりません。
少なくとも実写ではノイズの影響は感じないですよ基本感度だと。ベンチマークテストでグレーカードで比較するとノイズはあるかもですが、それは実写とかけ離れた世界です。
カセットテープだってラジオだって、音源があればノイズはマスキングされ目立たないのと同じ理屈です。
あと、Nikon Z8はベイヤーセンサの高画素機なので、木の葉のように高周波成分の多い被写体は、明瞭度を落としたほうが逆に絵に精細さが出ます。明瞭度は輪郭をくっきりさせる効果はあるけど、木の葉のように細かい描写だとその輪郭が目立ちすぎてうるさい絵になるんですよね。
さて紅葉、イチョウ以外はまだまだ色づきが始まっていなかった11月上旬の奥多摩の鳩ノ巣、ごく僅かに色づいているものもあったので、135mmで抜いてみました。
かなり演出入っています(笑

実は実際はもみじの赤はそのままですが、周りの葉っぱは緑だったので、ガッツリ色温度をいじってみました。お遊びです。実際にはこんなに黄色っぽい葉っぱではないです。
AI AF DC-Nikkor 135mm f/2Dで、DCリングは過剰に回してみました。こういう幻想的な柔らかい写真になります。
来年は…11月後半に行きたいな。今年はもう予定が立て込んでて難しいです。
場所はここです。
高速連写も風景も、何でもOKなカメラです。