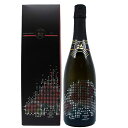視察ですw。GW、せっかくなので気になっていた栃木県は鹿沼市の南摩ダムを見に行ってきました。
栃木に住んでいた当時は、建造前の同地を何度も訪れて撮影しています。ダム建設に伴い廃校となった旧梶又小学校を撮るのが目的でしたが、今はダム自体に興味があります。
上の記事も合わせてご覧いただけると、その経過がわかります。
この地を訪れるのは13年ぶりです。栃木から東京に引っ越して、もうそんなに経つんですね。
ダムを正面から。すっかりダム本体は出来上がっています。今はこの場所より先は通行止めですが、いずれこの先も行けるといいですね。

それではダム湖(まだそんなに貯水されていませんが)を見下ろせる新道に行ってみます。
残念ながら展望台自体の場所は現状立入禁止でした。が、この場所はいずれアクティビティゾーンとして最近流行りのジップラインを作る計画のようですね。なるほど、出来たら一度やってみたいです。
元々展望台だったのが、どうやら熊出没のために閉鎖され、そのままアクティビティゾーンとして新たに整備する事になったようですね。





そしてダム湖はまだ底が見えるくらいにしか貯水されていませんね。元々南摩川の水量はかなり少ないので、他の川からも導水路により水を取り入れているようです。
上の写真右下のは取水口かな? 将来的には鹿沼市の水道水としても使われるようですね。


ダムの管理棟ではダムカードは配布していません。麓に出来たスノーピークのキャンプ場(この後行きました)で配布しているのですが、もらい忘れてきました…。
コンクリート表面遮水壁型ロックフィルダム(CFRD)という、断面にすると平たい三角形のダムです。ロックフィルダムは地盤が強固ではない地形で使われることが多いのですが、砂利を固めているものは多く見ますが、表面をコンクリートで覆う近代的工法タイプでは日本初の方式だそうです。
満水近くになるのは何年後でしょうか…
ダム脇の杓子沢トンネル、ダム建設に伴う新道開発では初期の頃に出来たものですね。
この後は新道を登り、旧道を見たり、ダム湖の端となりそうな場所?を何枚か撮影。





ダムの本格運用は2027年度とのことで、また2年後に行ってみたいですね。
この日のカメラはNikon Z 8でしたが、GPSアダプタを紛失してしまって、スマホのSnapBridgeアプリ経由でGPSデータを付与しているのですが、元々SnapBridge経由だと精度がいまいちな上に、Bluetoothが途切れると再接続がなかなかスムーズに行かなかったりして、やはりちゃんと撮影場所のログを取るにはGPSを内蔵したZ 9か、あるいはGPSアダプタが必要ですね。
今まで古いNikon GP-1というGPSアダプタと、di-GPSという社外アダプタを使っていましたが、di-GPSはGPSの取得スピードが早くて消費電力も少なく良かったのですが、物理的に折れてしまいました…。GP-1は取得が遅いし消費電力も多いのですが、今回これも紛失したっぽいです。トホホ…。
ということで、そのうちまたdi-GPSを買い直したいと思います。ただ今このアダプタの会社が香港からイギリスに移って、価格もちょっと高くなってしまったんですよね。直輸入なので輸送費込みで高いのですが、他に良いものもないんですよね。Amazonが代理店として扱ってくれればいいのですが、あまり需要ないんでしょうね。