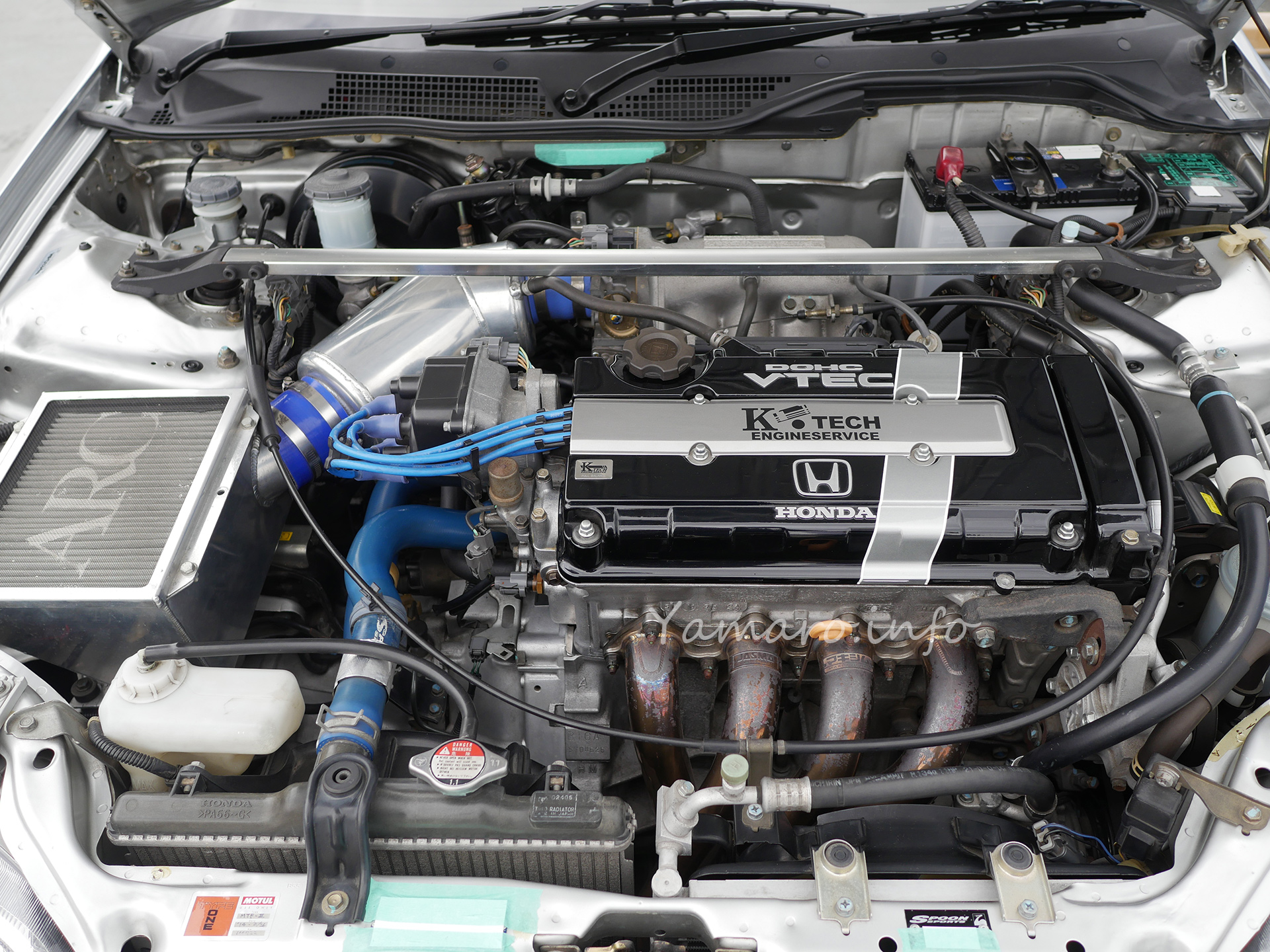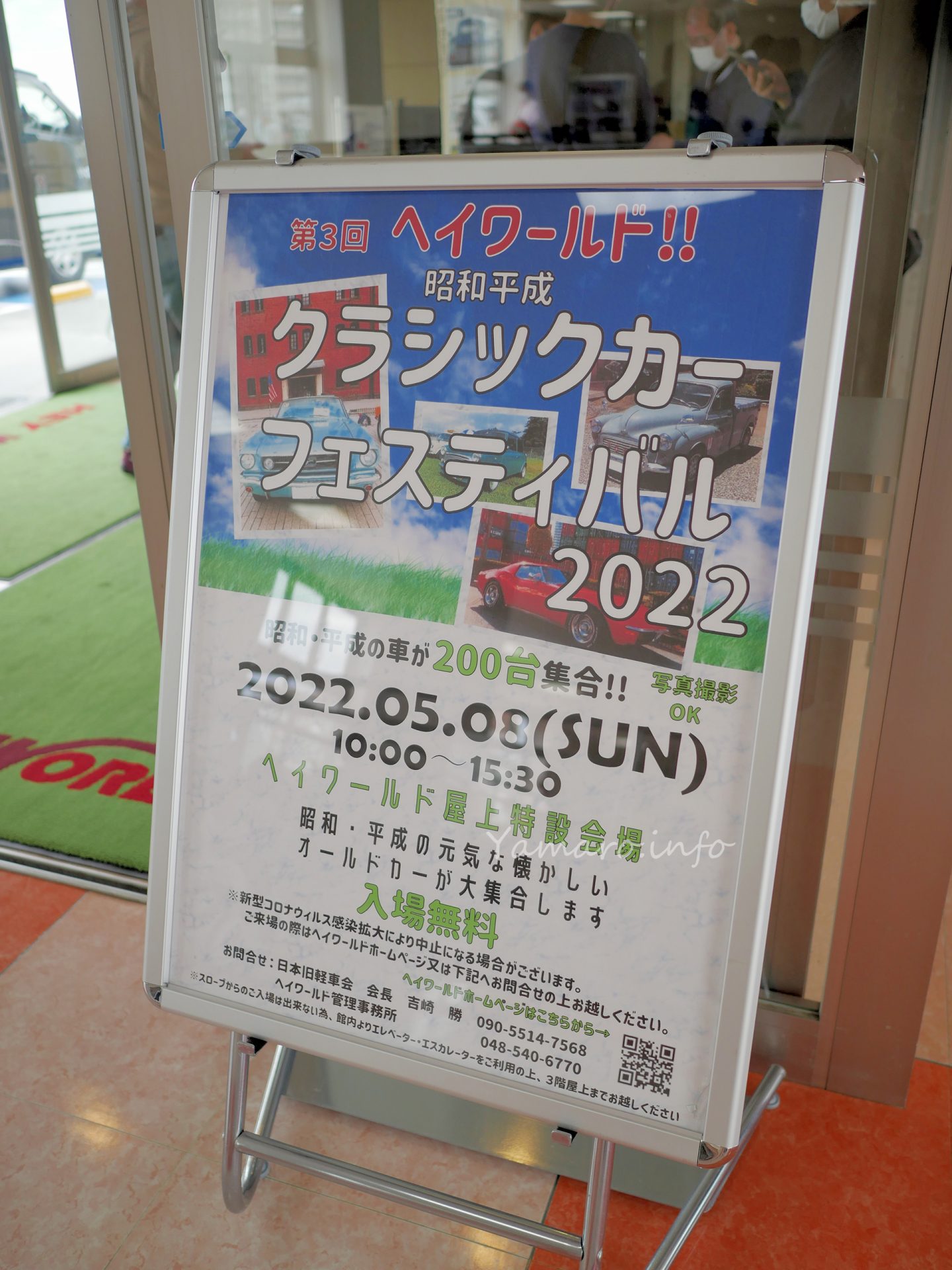嫁車エスティマ、13年を経過し、走行距離も10万キロを超えました。
そろそろメンテナンスしなければなと思っていたCVTフルード(CVTF)の交換。前回は2017年に、6万4千キロでトルコン太郎による圧送交換を実施しています。
あれから5年、4万キロ近く走ったため、そろそろ2回目の交換が必要かなと。
前回は、CVTFのみの圧送交換でしたが、今回は13年10万キロを超えたため、CVTのオイルパン洗浄とストレーナ交換も含めた本格メンテナンスを依頼しました。
そのあたりの話は次回に書きたいと思います。
さて今回依頼した車屋さん、街の整備工場といった趣で規模は小さいですが、交換実績数も多く、そして代車を依頼したら、なんとまだ新しいスズキ・ワゴンR スマイルでした。10年落ちのコンパクトカーでも出てくると思ったら意外でした。
しかも、グレードも一番上のHYBRID Xのようです。


 スズキ・ワゴンR スマイル
スズキ・ワゴンR スマイル
おっさんが乗るには可愛すぎだろ!
見た目は…おっさんが乗るにはラブリーすぎですね(笑) 主なターゲットは小さな子供のいるママなのでしょうね。
ワゴンRの名前がついていますが、デザインは全く異なり、リアドアもスライドドアになっています(ワゴンR はリアもヒンジドア)。デザインは、どちらかというとスペーシアの屋根を低くした感じでしょうか。
最新の軽自動車に乗るのは久しぶりです。最近は乗ったとしても、職場にある初代初期型の10年近く前のN-BOXなので、軽自動車10年の進化は感じられるかな?
軽自動車が安っぽいエンジン音を出すのは昔の話に
まず走り出してびっくり、一昔前のNAの軽自動車と言えば、パワーが無いので回転で稼ぐしかなく、ギュイーンと安っぽい音を立てるのですが、全然そういう安っぽい音はしないですね。エンジン音そのものは、回せばそれなりにありますが、音の質感が甲高くなく、どちらかというと1.3Lクラスのコンパクトカーに近い印象。
個の音だけでも質感がよく感じます。静粛性も、軽自動車としてはなかなか良いです。
HYBRID Xというグレードだけに、ハイブリッドエンジンです。ただ、エンジン出力が36kW〈49PS〉/ 6,500rpm, 58N・m〈5.9kg・m〉/ 5,000rpmなのに対し、モーターの出力は1.9kW〈2.6PS〉/ 1,500rpm, 40N・m〈4.1kg・m〉/ 100rpmと、ほとんど発進時のトルクを補う程度で、ターボ車のようなパワーがぐんと立ち上がる感じはありません。
ぶっちゃけ、アシストしてる? という感じですが、加速状況に応じて30~60km/hまでアシストは入っているようです。
ただ、アクセルを抜くと、わりと回生が入って減速しやすいですね。すぐに回生でバッテリの充電量も上がるので、バッテリ自体の容量も低いようです(3Ahしかない)。
そんな感じなので、一般道の法定速度60km/hまでの走行は、まあ不満なく走れます。ただ、いざという時の瞬発力は、そこはNAエンジンの軽自動車らしく、一人乗車でもACオンだと苦しめです。あくまで、街乗りの範囲で快適に走れる、というチューニングのようです。
内装の質感も必要十分
 内装の質感も悪くない
内装の質感も悪くない
内装、今どきの車だなと思うのが、純正ナビの画面が大きく、そして全方向のカメラが付いていて、車の状況を俯瞰した状態でモニタに表示できることです。
軽自動車なので、サイズ的にも見切りはそんなに悪くはないけど、運転苦手なママにはぴったりなんでしょうね。
内装は、今どきのクルマらしく、ステッチは偽物ですが、柔らかい表皮となっていて、一昔前のプラスチックむき出し感がないのもよいですね。
ステアリングが、最上級グレードなのにウレタンなのだけが残念だけど、このクルマのコンセプトは街乗り主体だから、長時間ステアリングを握るような走りはあまり想定していない感じですね。
純正ナビは、メーカー名は入っていませんが、恐らくパイオニア製ですね。表示や挙動など、サイバーナビとそっくりです。
足は案外固め?
ここは軽自動車だな~と感じさせる部分。道路の継ぎ目を通過するときに、案外ドタドタとします。ダンパーが細かく速い動きについてきてないです。その割にロールがあるので、峠道を走るクルマではないですね。
ガチャガチャ安っぽいノイズを発しないので、うまくごまかせている感じですが、このあたりはコストダウンをそれなりに感じる部分です。
実燃費は渋滞走行で19km/Lくらい
国道17号線、部分的に渋滞走行、トータルで60km走って、車載燃費計で19.3km/Lでした。返却前にガソリンはきっかり3L入ったので、だいたい燃費計に近い数値ですね。渋滞走行しつつ、ACオンでこの数値なら悪くないですね。
街乗りならこれで十分
今まで軽自動車の一番キライな部分だった、ギュイーンという安っぽいエンジン音がない、これだけでだいぶ印象が違います。あの安っぽい音が嫌いで、絶対に乗りたくないのが軽自動車でしたが、このクルマなら、「街乗り限定」であれば、特に不満なく乗れそうです。今や軽自動車は新車の半分の割合とも言われていますが、そりゃ売れるような~という印象です。
初代N-BOXよりもよく出来ています。ということは、乗ったことはないけれど、現行N-BOXもそうとう良いのだろうなと思います。
自分は長距離走行が多いので、まだ軽自動車を選択するということはないけれど、栃木に戻った際には、セカンドカーは軽自動車で十分かな~。

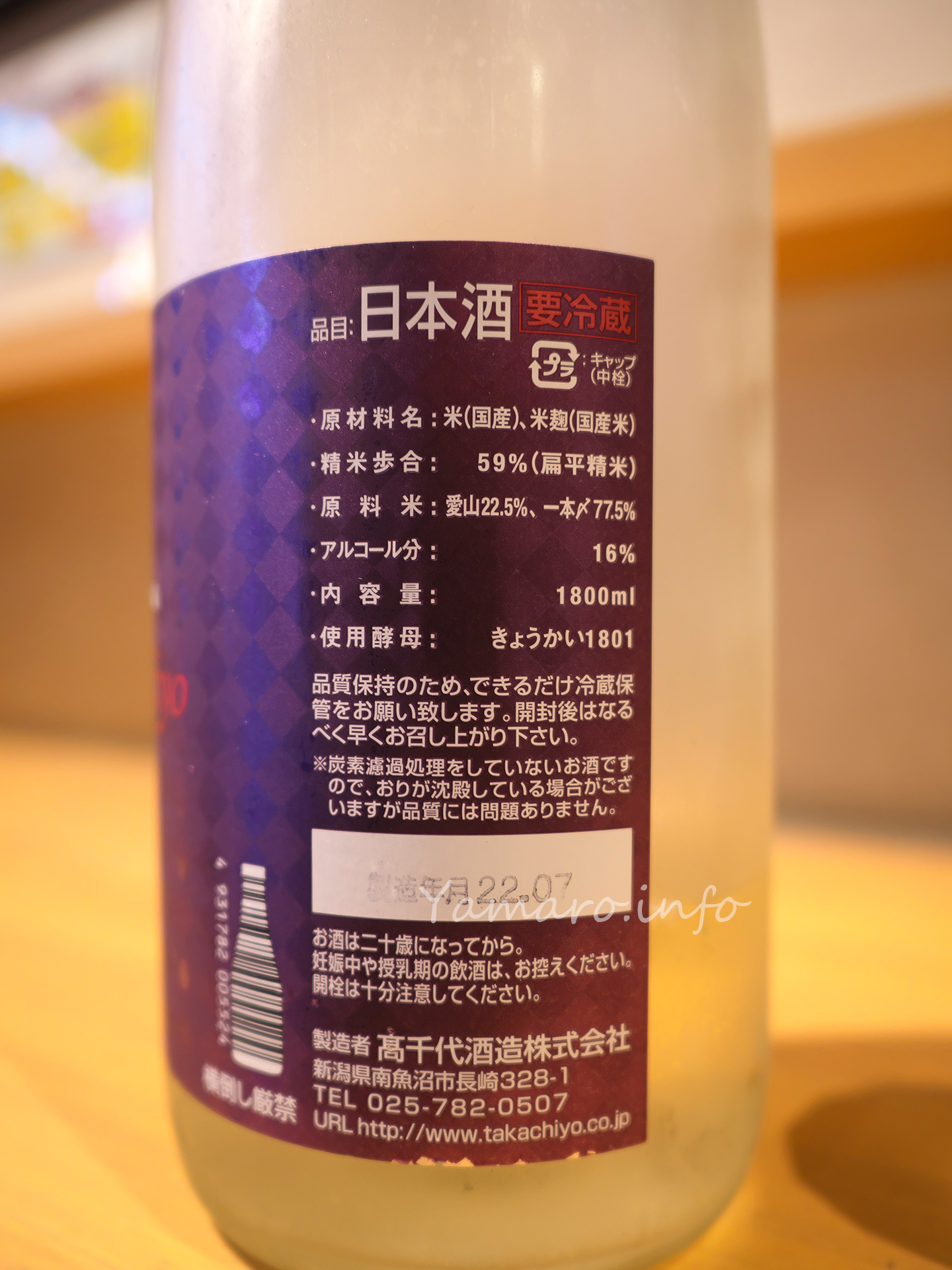












































![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/1934bd1b.2e569fee.1934bd1c.0115c6c3/?me_id=1217830&item_id=10754049&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Femedama%2Fcabinet%2F54%2F2142592886254_1.jpg%3F_ex%3D300x300&s=300x300&t=picttext)