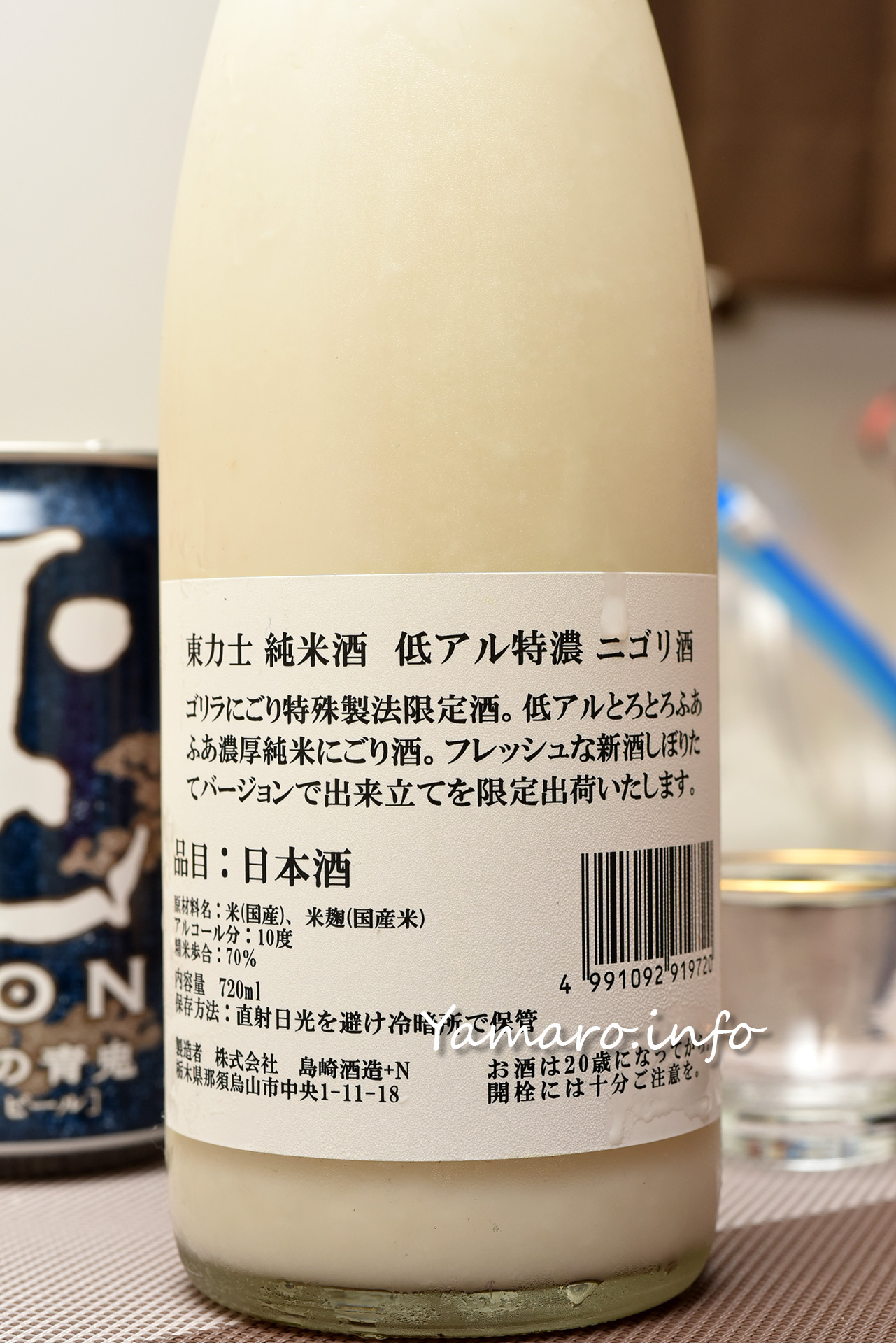7月6日(土)の関東の豪雨、すごかったですね。1時間あたりの降水量が60mm! ちょうど車に乗っていましたが、ワイパーが効かない(むしろワイパー動かない方が撥水で見える!?)くらいの大雨。そして雷も凄まじかったですね。
自宅に帰ってきて、その雷をベランダからNikon Z 8のC120モード(秒120コマ, プリキャプチャーON)で撮影してみました。
どこに閃光が走るかわからずなので、やや広角のNIKKOR Z 35mm f/1.8 Sで撮影したので、撮れた閃光はちょっと小さいのですが、なかなか面白い結果になりました。
※手前に住宅が写っているのでぼかしを入れています
落雷した瞬間は空が明るくなりますが、その明るくなった部分とそうでない部分の境界線が出来てしまっています。
当然これは実際こう見えるのではなく、電子シャッターの幕速の関係でこう写ってしまったのです。この3枚はシャッタースピードは1/500秒です。
Nikon Z 8はメカシャッターレスとなっていて、電子シャッターのみですが、その幕速は上級機のメカシャッターとほぼ同等の速度となっているために、メカシャッターを廃しています。
積層型CMOSセンサとしては幕速が現時点で最高速の部類に入るわけですが、最高速とは言え、画面の上から下を順番に走査しスキャンしているため、幕速1/200秒(画面の上から下までスキャンする時間)よりも速い閃光時間では、このような状態になってしまいます。シャッタースピードがもっと遅ければ問題ないはずです。
上の写真の左側は、稲妻が左下に見え、空がその影響で光っていますが、明るくなっている部分は画面の1/3程度。幕速1/200秒とすると、閃光の発光時間はおおよそ1/600秒です。閃光時間は概ね1~1/1000秒と割と差があるようです。
ちなみにこの撮影中にEVFで稲妻が見えることはなく、空全体が明るくなったのが分かる程度でしたが、こうしてしっかり写っていますし、1秒間のプリキャプチャの恩恵でもありますね。
速いシャッタースピードで全体が明るくなっている状態をしっかり撮るにはグローバルシャッターのカメラが必要
メカシャッターであれ、積層型CMOSセンサーの電子シャッターであれ、このシチュエーション、1/500秒のシャッタースピードでは上の写真のような結果になってしまいますが、これが全画素読み出し可能なグローバルシャッターのカメラであれば、シャッタースピードをより速くしたとしても、幕速の概念なく一気に撮影できます。
グローバルシャッターのカメラは、従来業務用・産業用の高速度CCDカメラで採用されていて、初期の民生用デジカメでも採用されていましたが、近年CMOSセンサが主流となったため、民生用カメラでCCDセンサはほぼなくなってしまいました。これはCCDカメラでは発熱が大きく消費電力も大きいためです。
ところが、SONYからα9IIIが発売され、このカメラは積層型CMOS「Exmor RS」を搭載しお、全画素を同時に露光できるグローバルシャッター方式となっています。このカメラであれば、プリキャプチャー+全画素同時読み出しで雷の閃光と空の光の反射がきれいに撮れると思われます。
そうしたシチュエーションはなかなかないですが、いずれ高速読み出しが売りのカメラはグローバルシャッターのセンサが主流になるかもしれませんね。
※シャッタースピードの観点が抜けていたため補足追記しました。
執筆時点では民生用唯一無二のグローバルシャッターCMOSセンサ搭載のカメラです。この流れはNikonやCanonに波及するのか、興味深いですね。
¥846,426
(2025/12/20 09:58:35時点 楽天市場調べ-詳細)