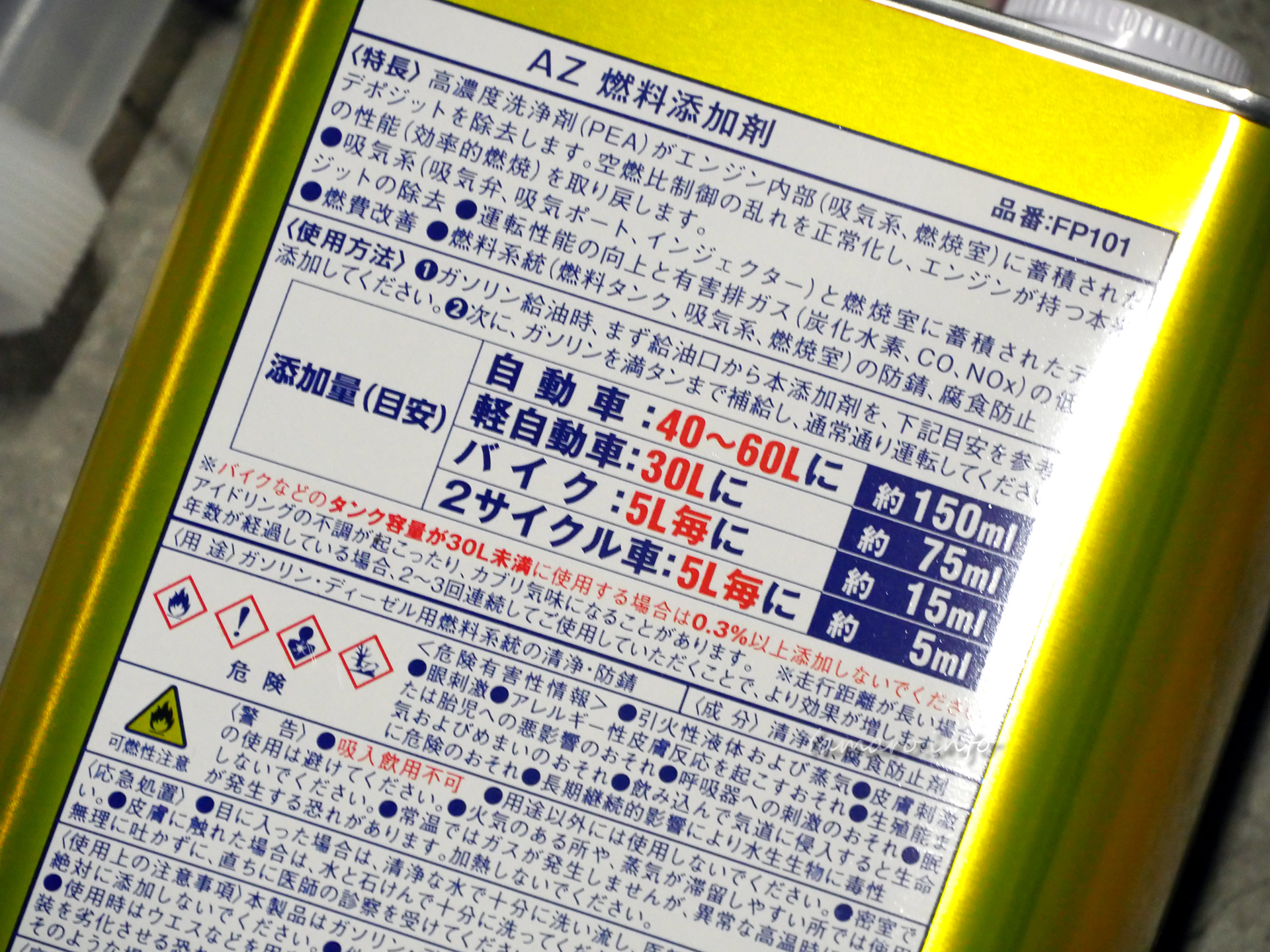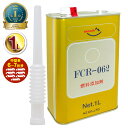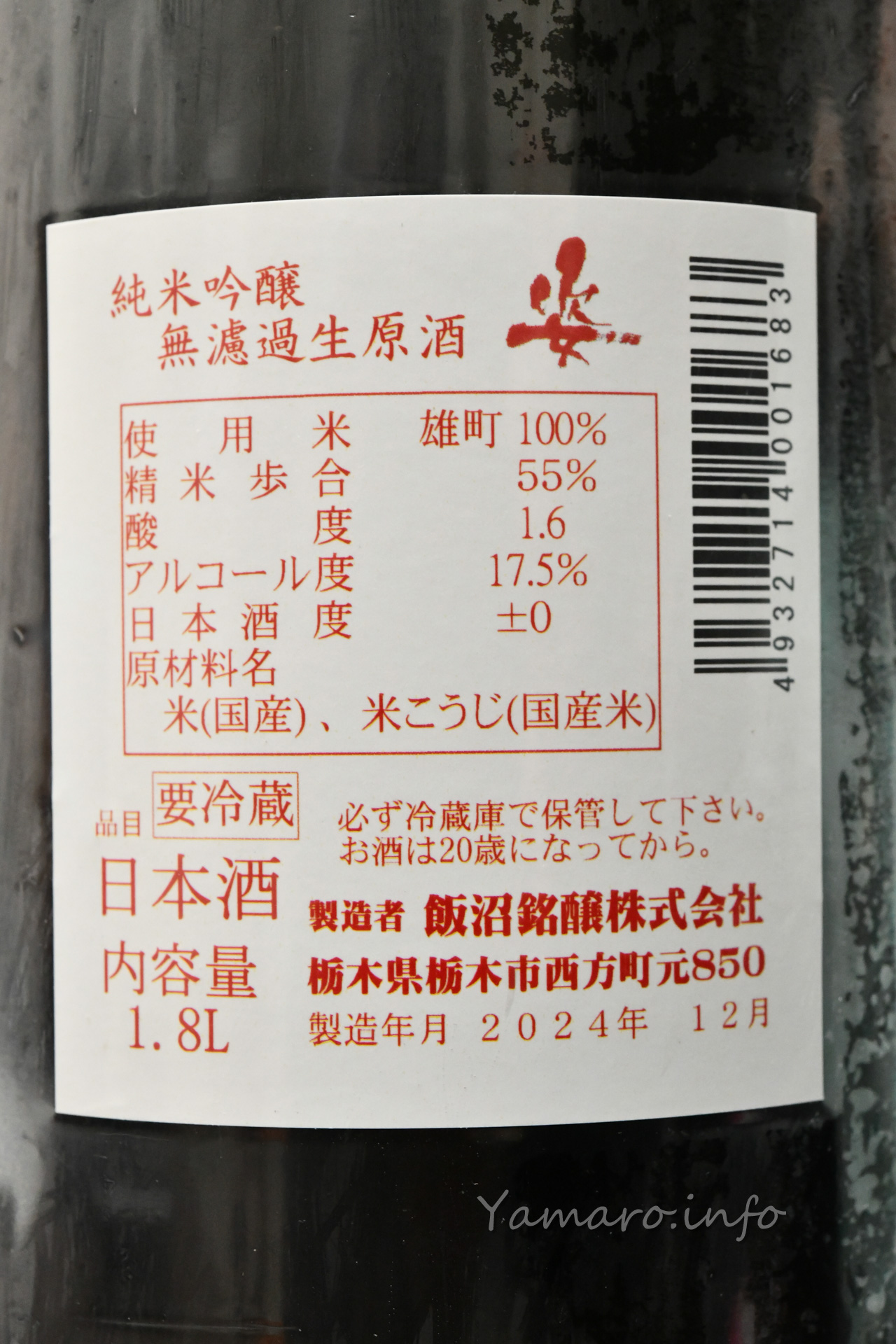クロスバイクの購入受取から1ヶ月半、購入後点検をしにコーダーブルームショップ稲城店へ行ってきました。

アクセサリ、ウェアにシューズと色々揃っているので、コーダーブルーム乗りでなくても見ていて楽しいかと思います。
点検は緩み確認などやってもらって問題なく終わり、ちょうど他にお客さんがいなかったので、店員さんに色々質問できました。クロスバイク買ったばかりですが、次買い替えるとしたらグラベルロードかな?という感じになっています(笑)
やはりグラベルを走れる分フレームを頑丈にしてあるので、フレームにもよるけど、このショップで扱っている車体だとロードバイクやクロスバイクよりやや重いとのこと。
今乗っているのが完成車で9.9kg、展示してあったNESTOブランドのKING GAVELで11.1kgかぁ。かといってMTBだともっと重いので、このあたりが良さげだよなぁ、なんて考えつつ、もちろんしばらくは現状で。通勤だとクロスバイクの方が適しているでしょうし。
ショップの周辺は多摩川があってサイクリングロードも整備されているので、帰る前に少し走ってきました。


天気が悪くなってきてポツポツ雨も降り始めたので、あまり長い時間ではないけど、多摩川のサイクルロードも走ってみました。
目の前にサイクルコンピューターを着けたSPECIALIZEDのロードに乗ったガチな感じのライダーがいたので、ついて行ったら、まあまあついていけました。まあ短時間ですが。
コーダーブルームショップの近くには、SPECIALIZEDのショップもあるんですよね。
高級車ばかりで自分に縁はなさそうですが(笑
うちの周辺はアップダウンばかりなので、ここは平坦な道が多く走りやすいですね。
色んなところに遠征して走る気持ち、ちょっとわかったような。まあ、まだ自分はそういう境地には達していないはずなので(笑)、あくまで撮影のための移動手段ではありますが、車を初めて買ってあてもなくドライブする気持ちで、チャリンコ乗るのも楽しいですね、知らない土地を走るとかだと。
ということで、ガチに走りこむというよりは、のんびりチャリンコライフを楽しみたいと思います。