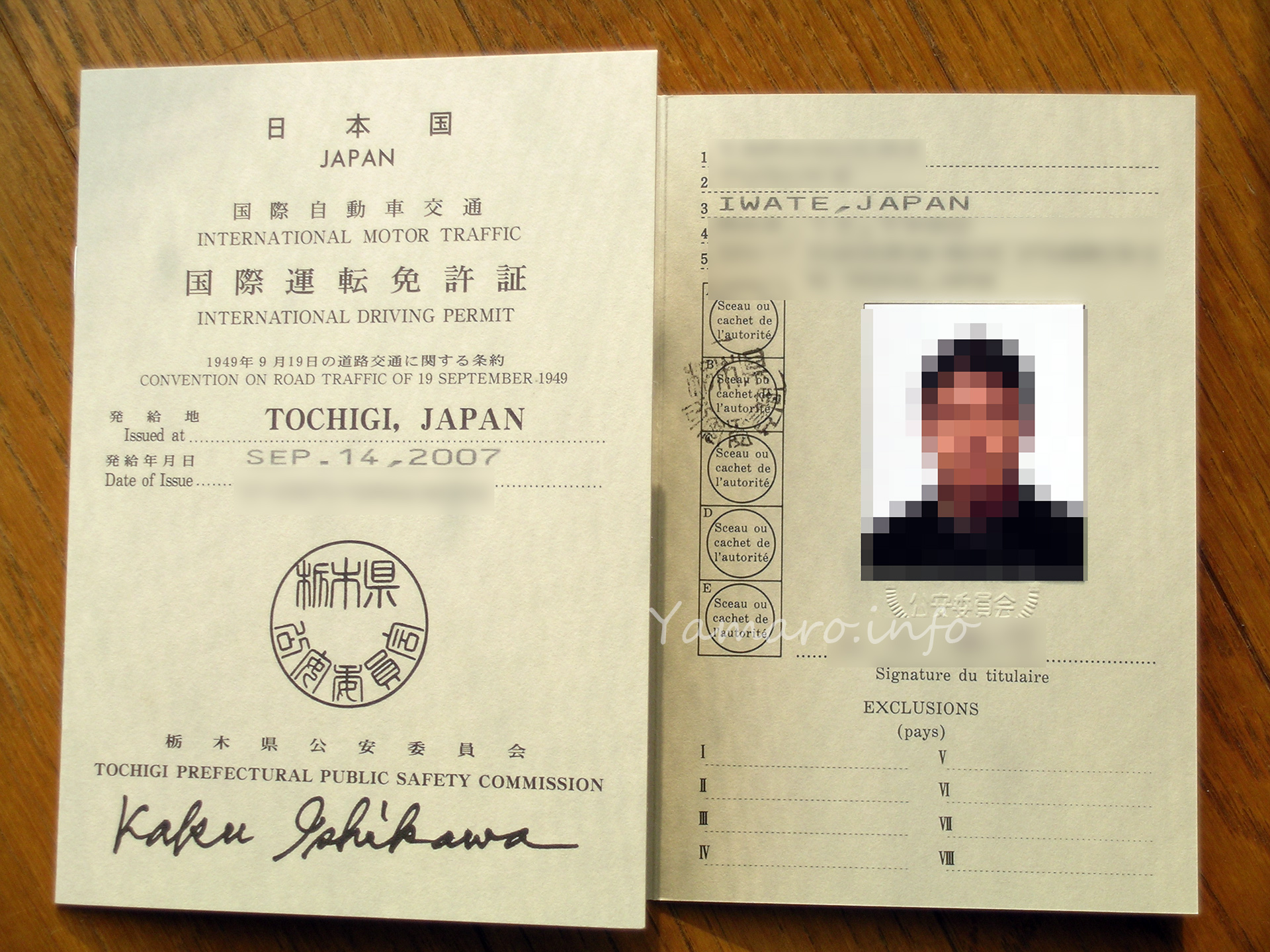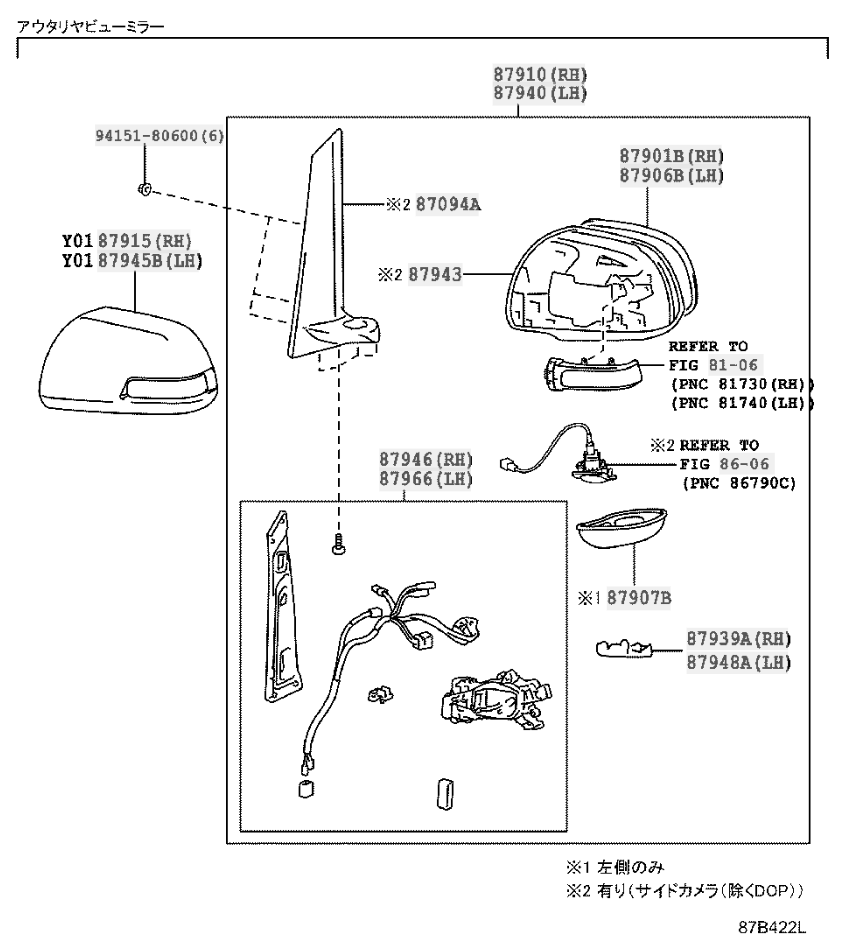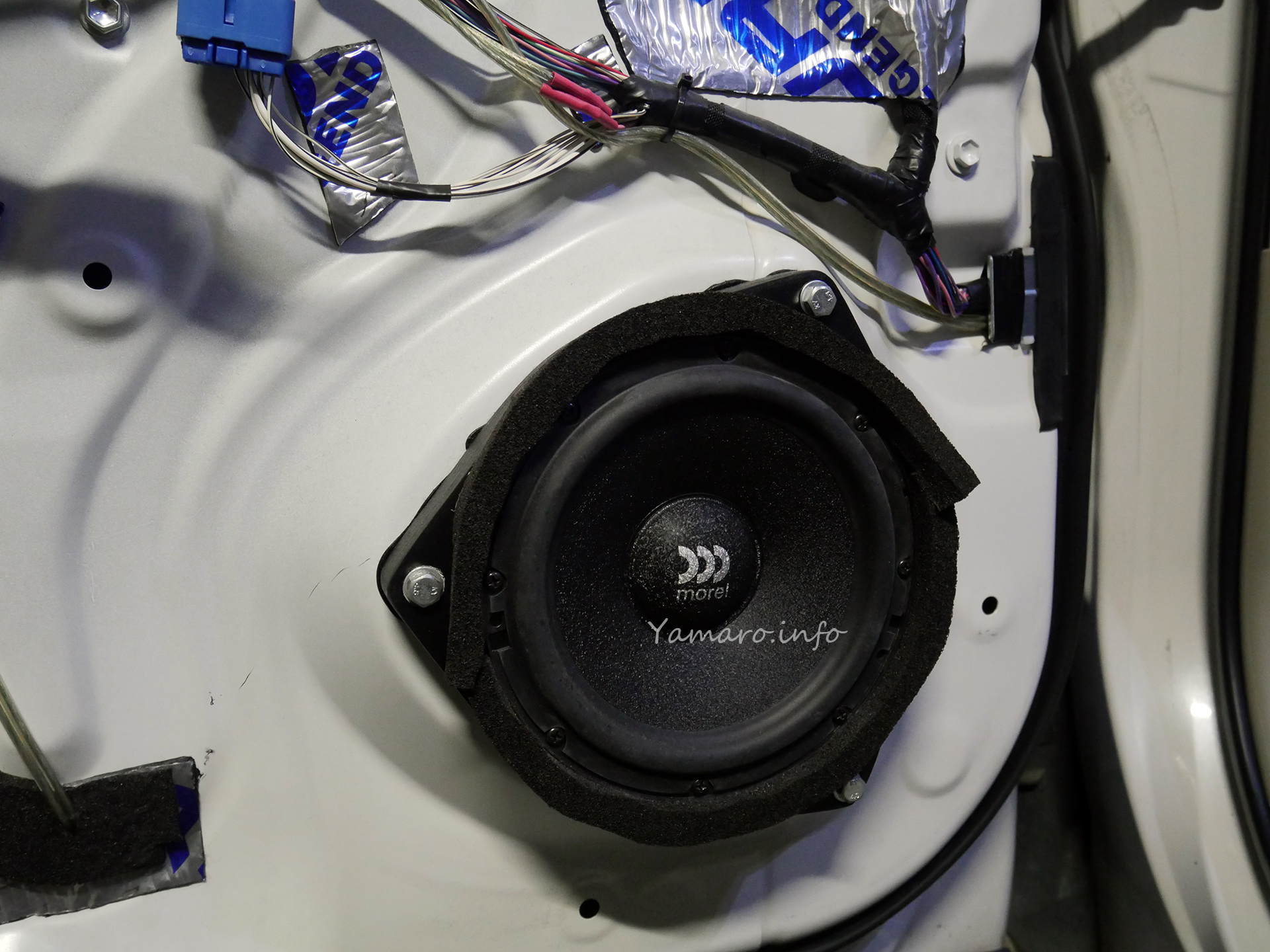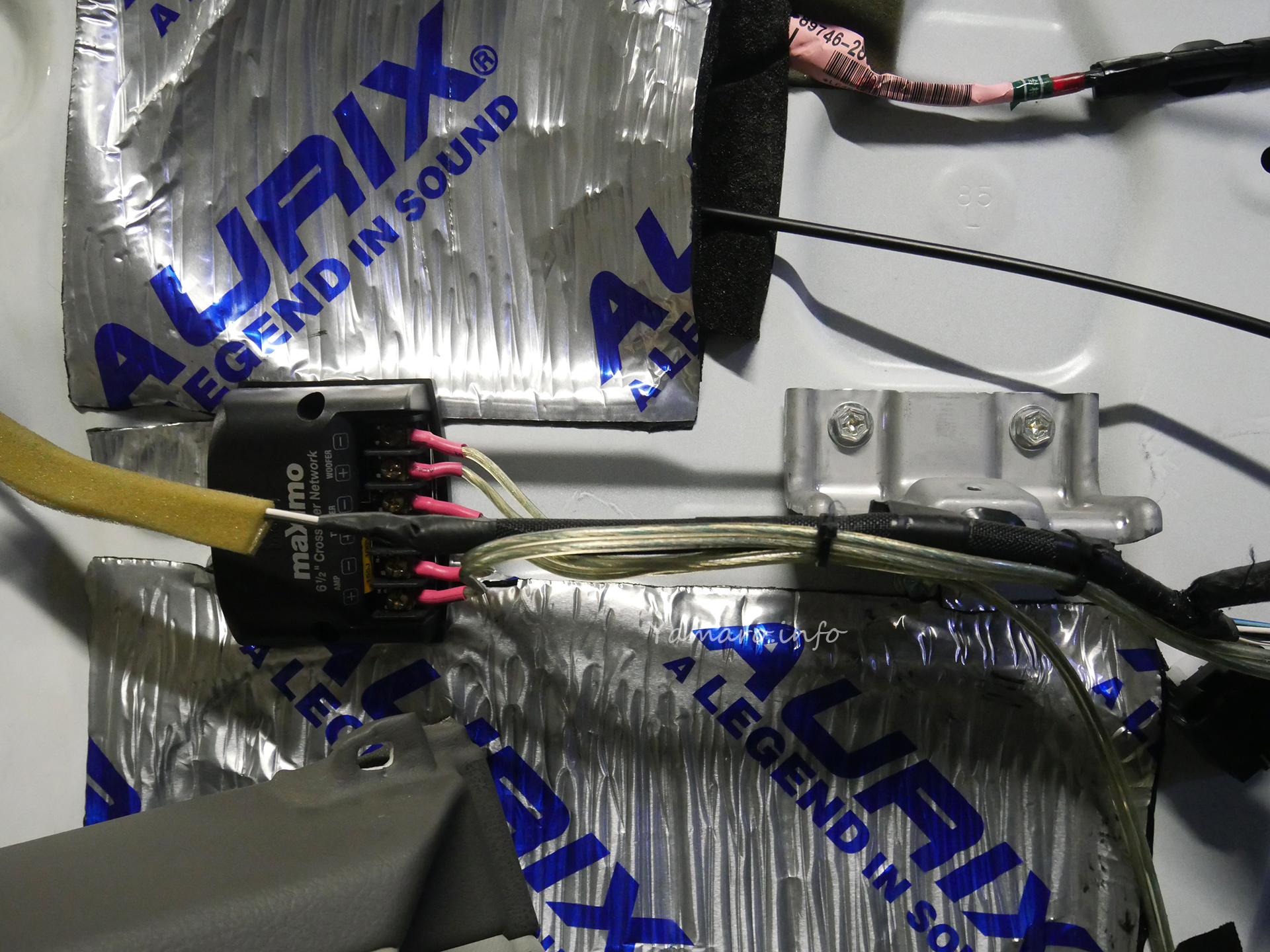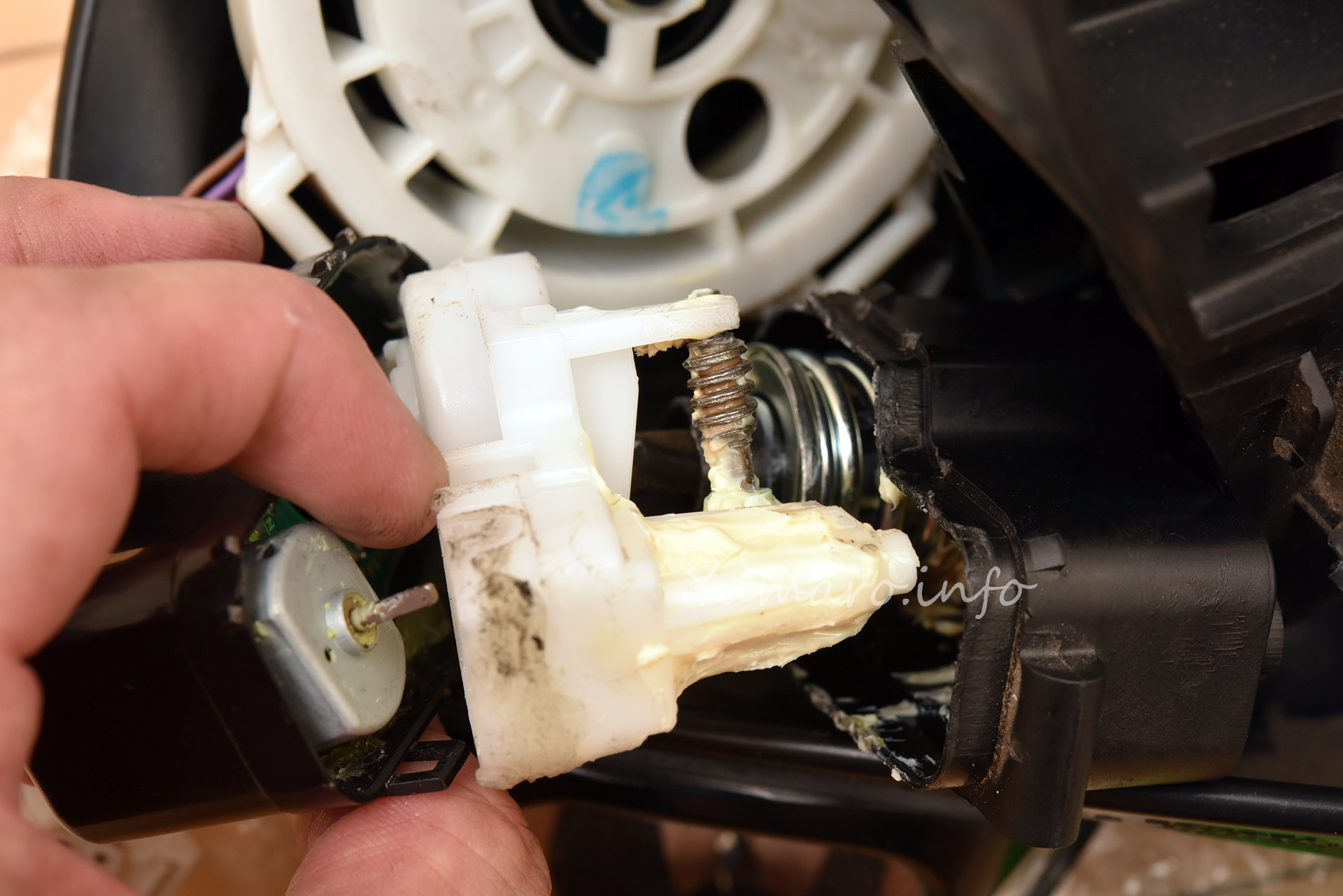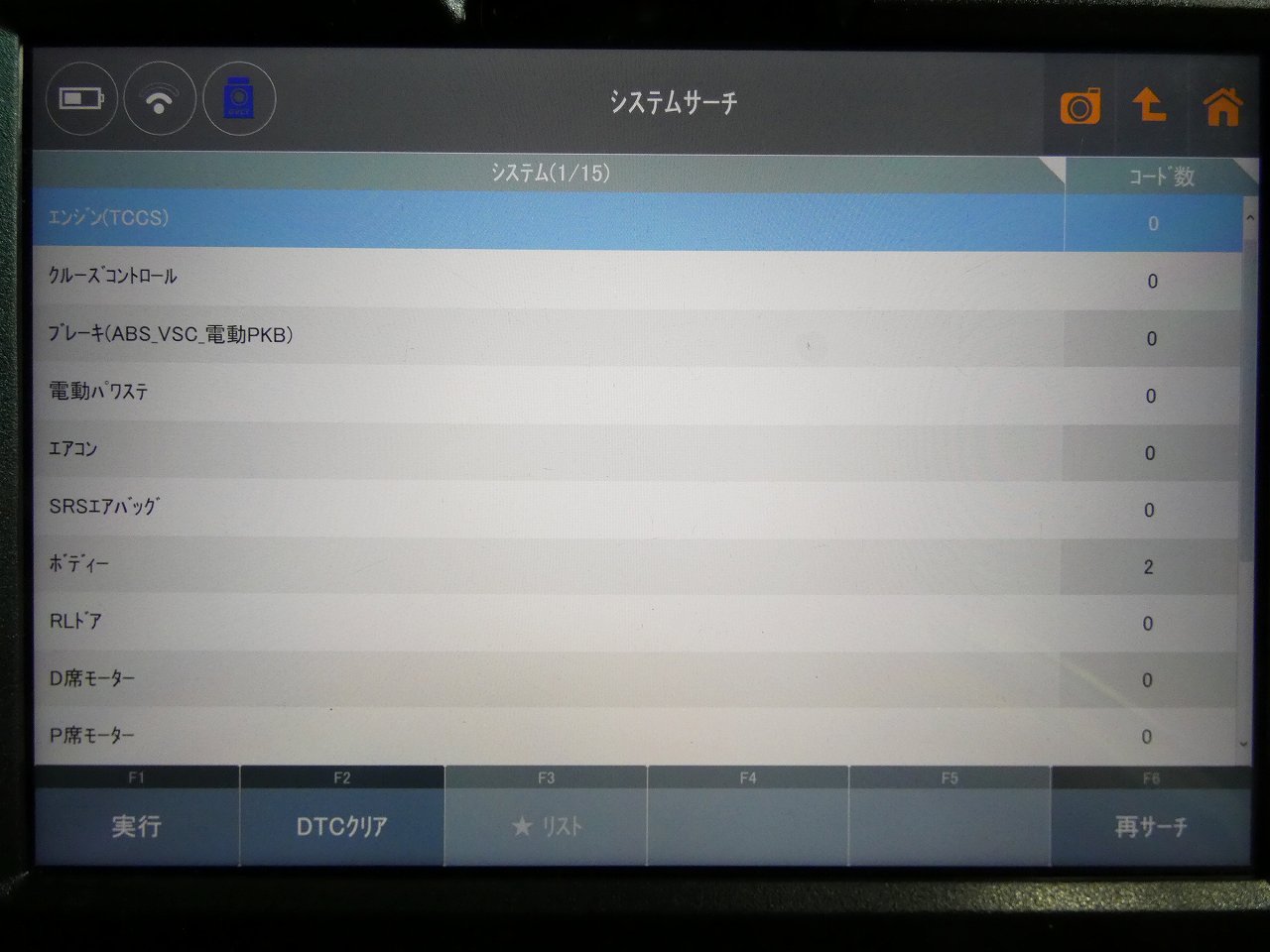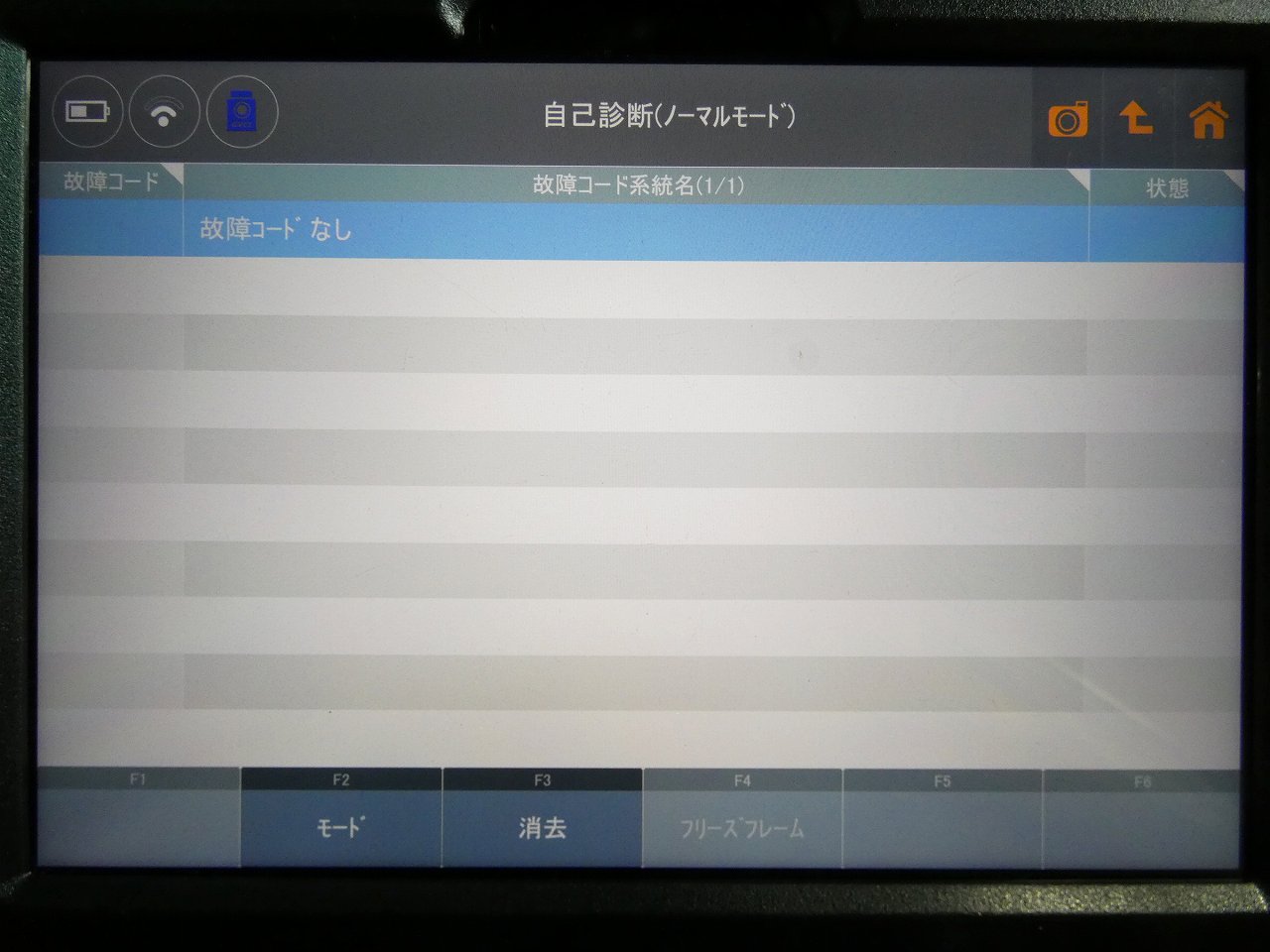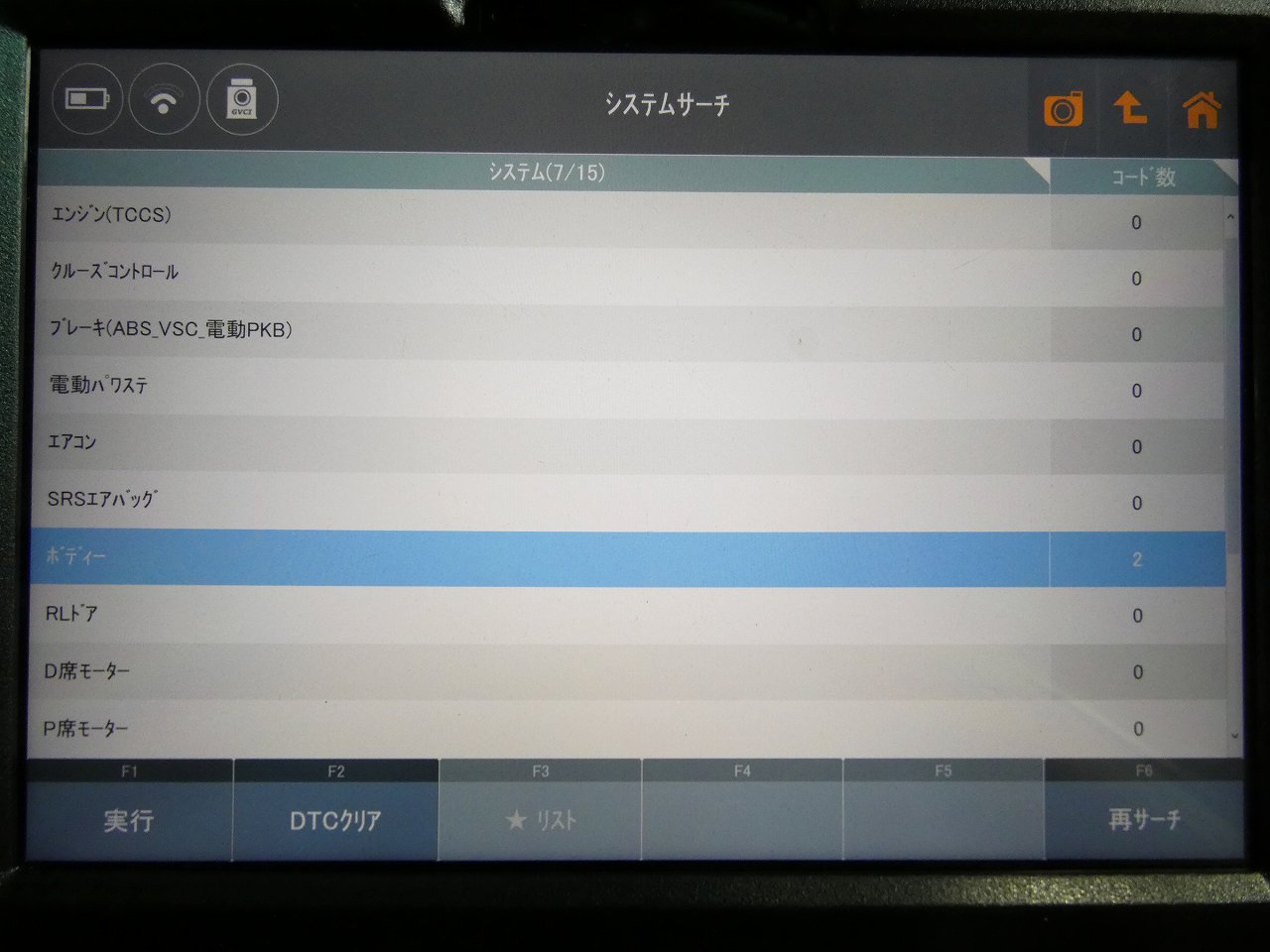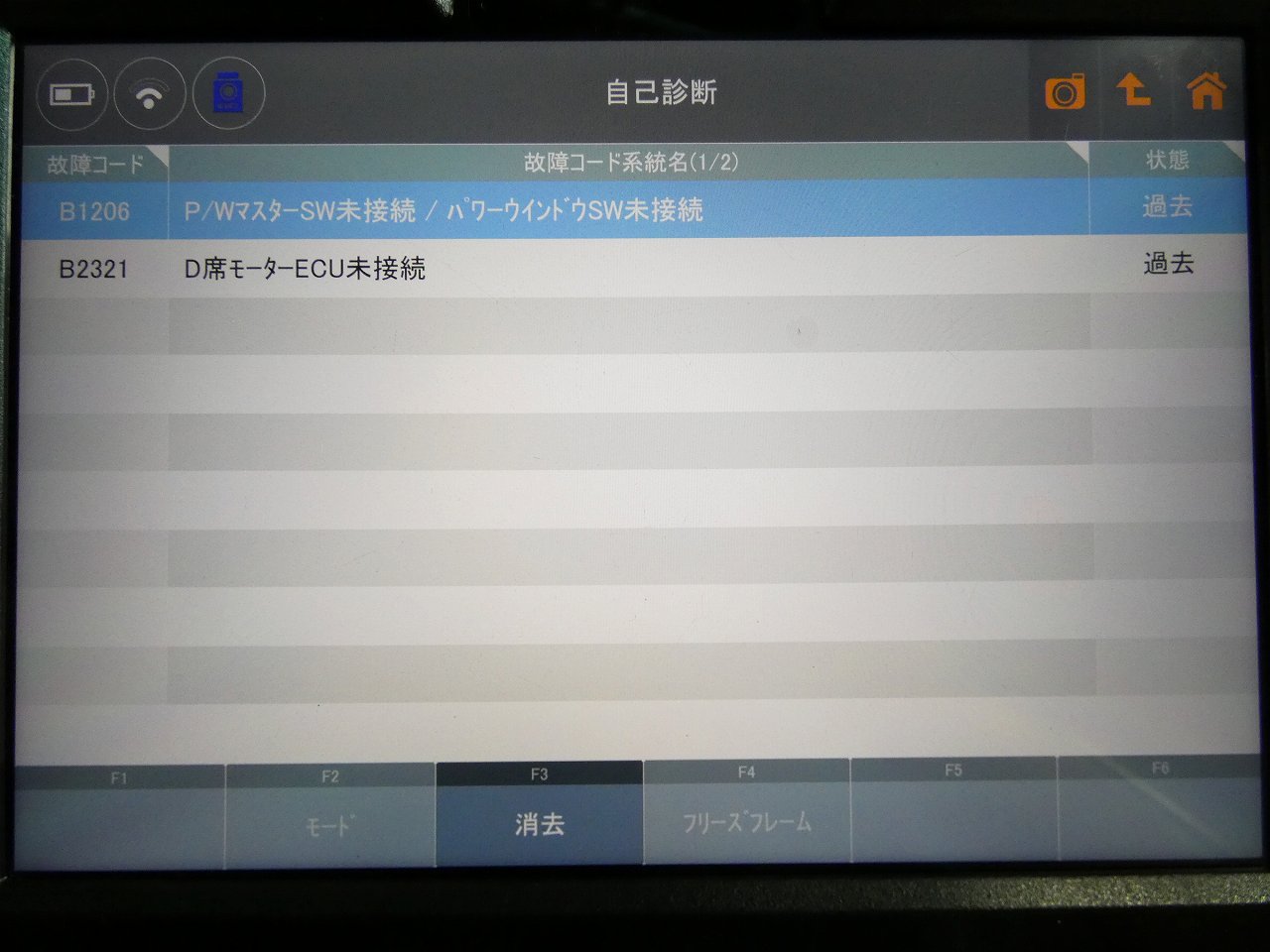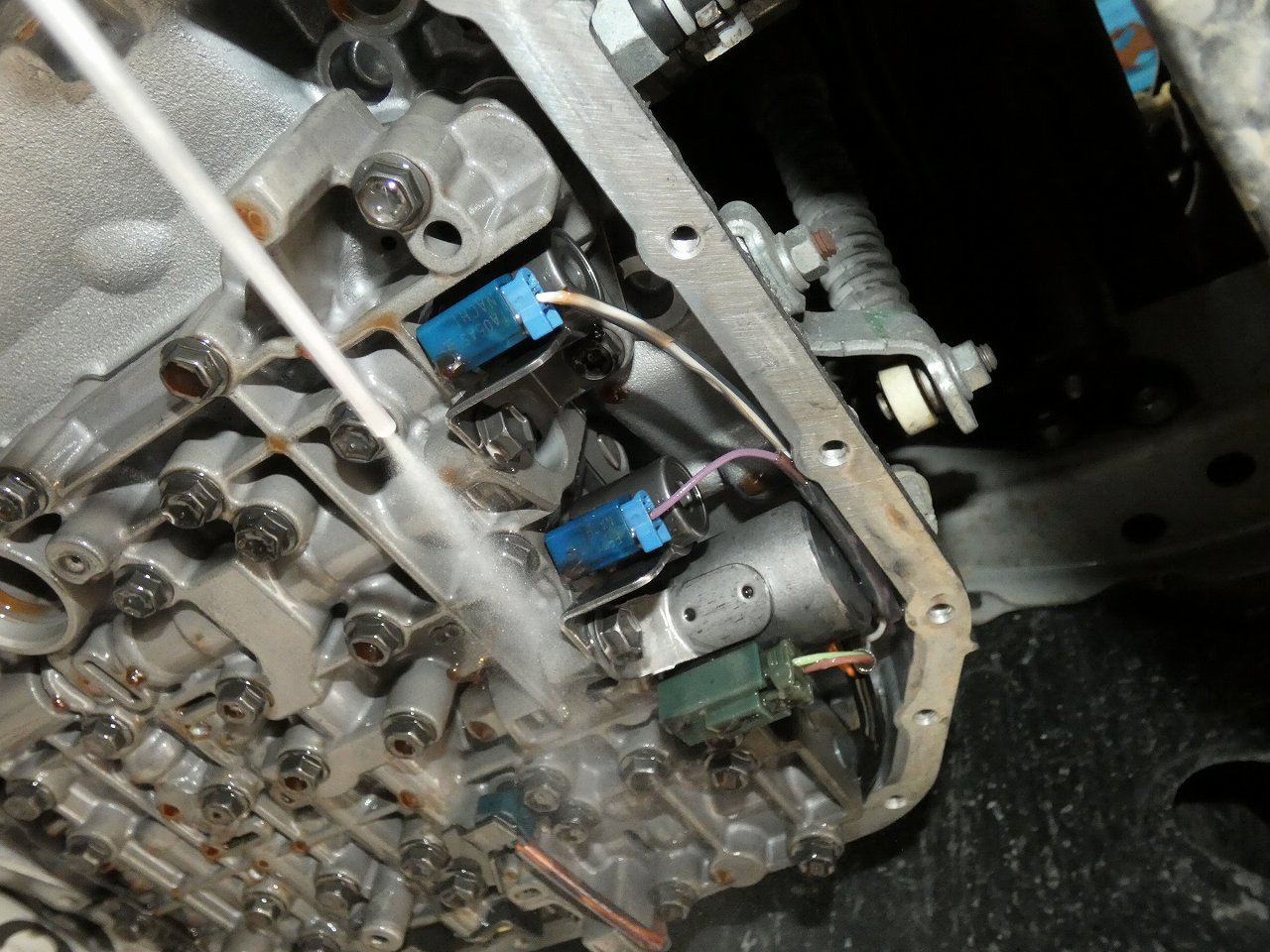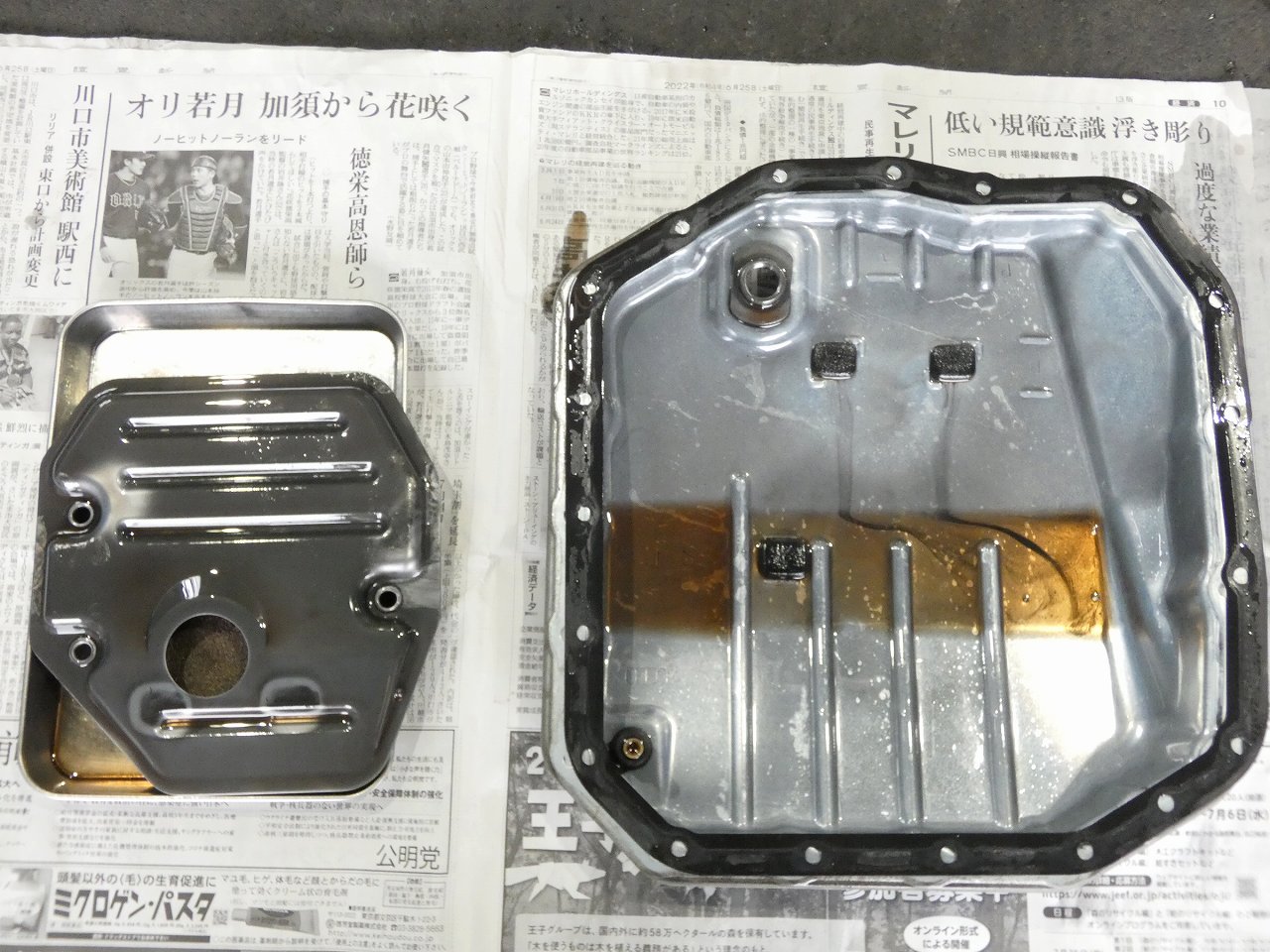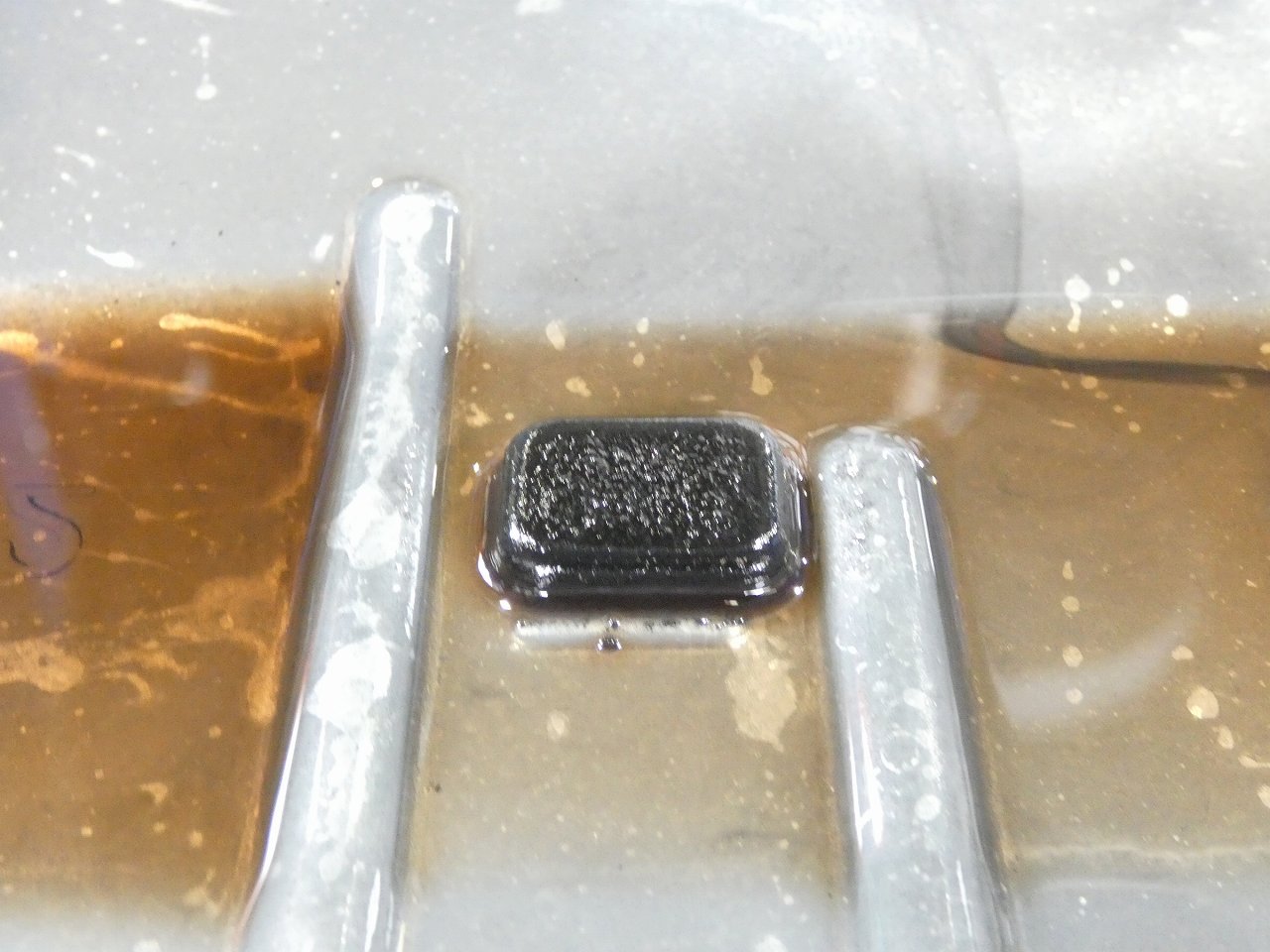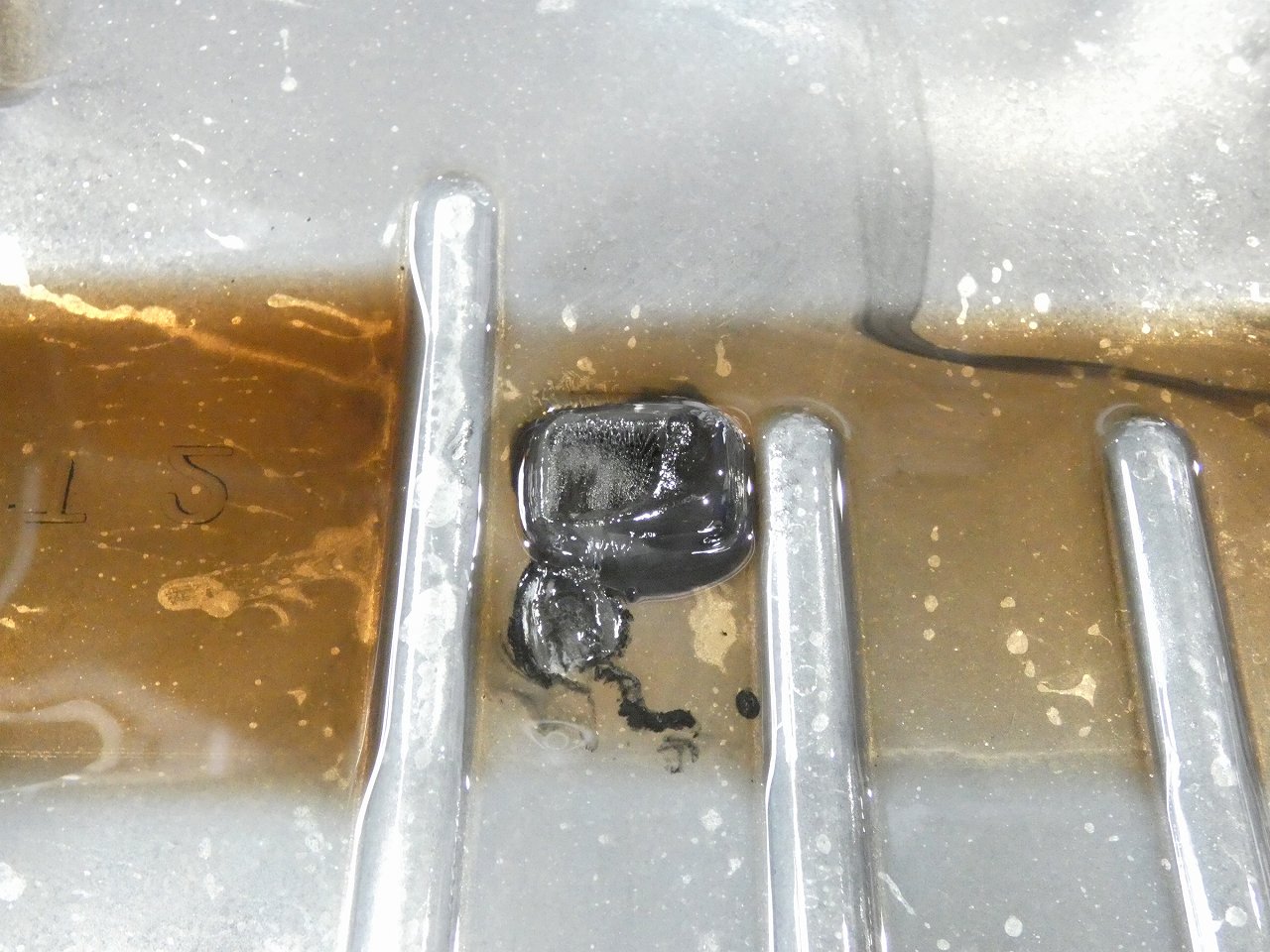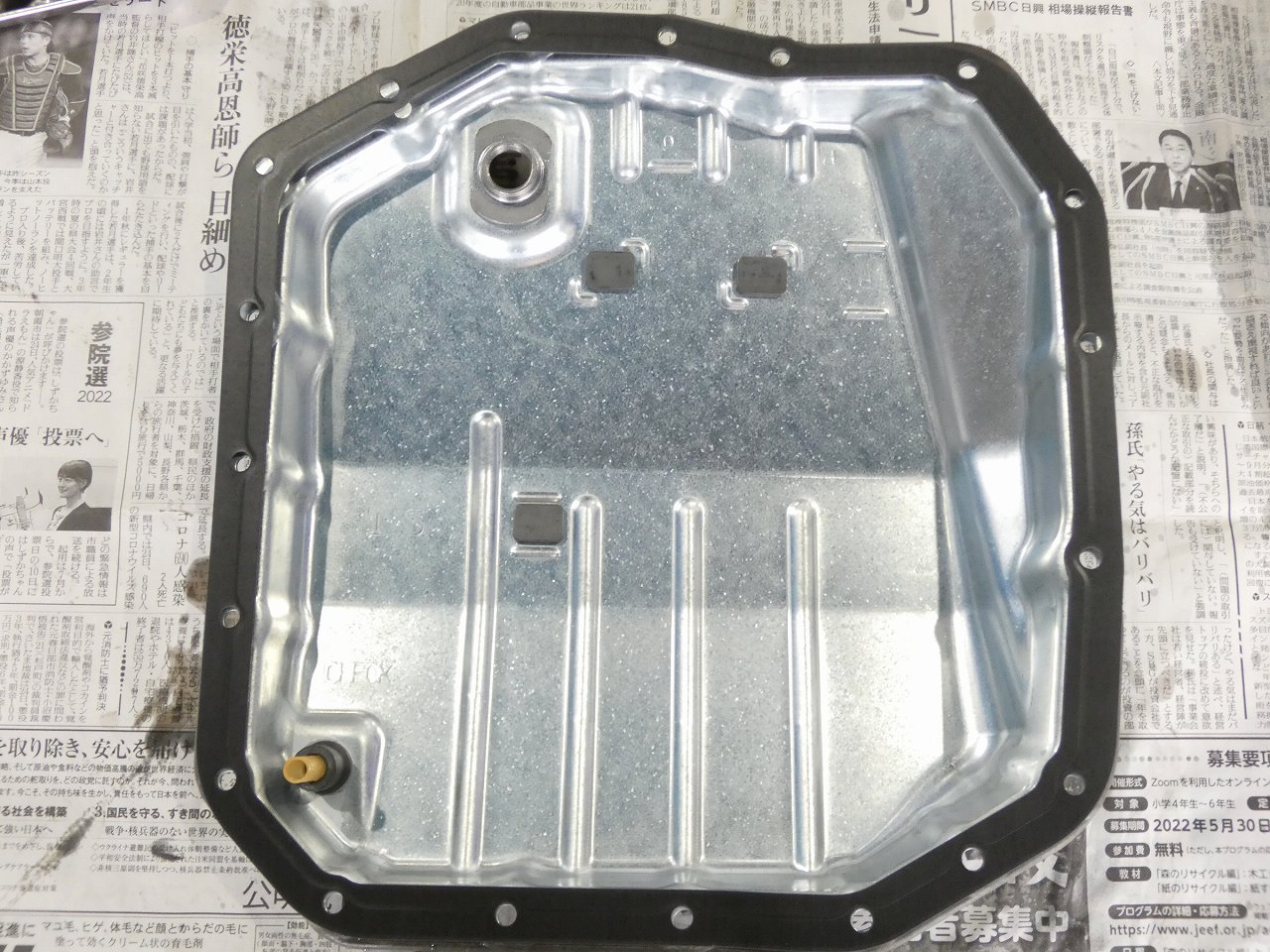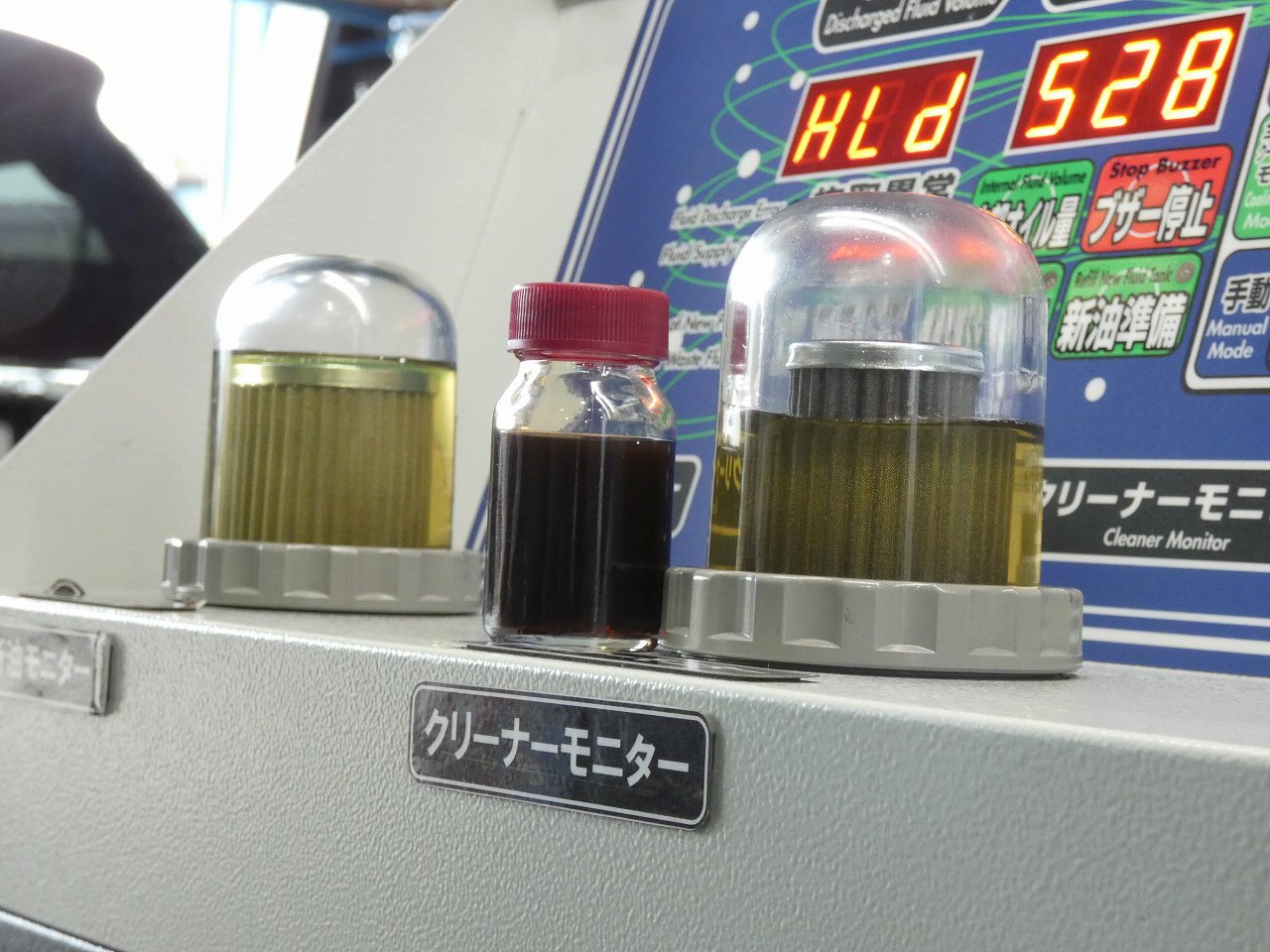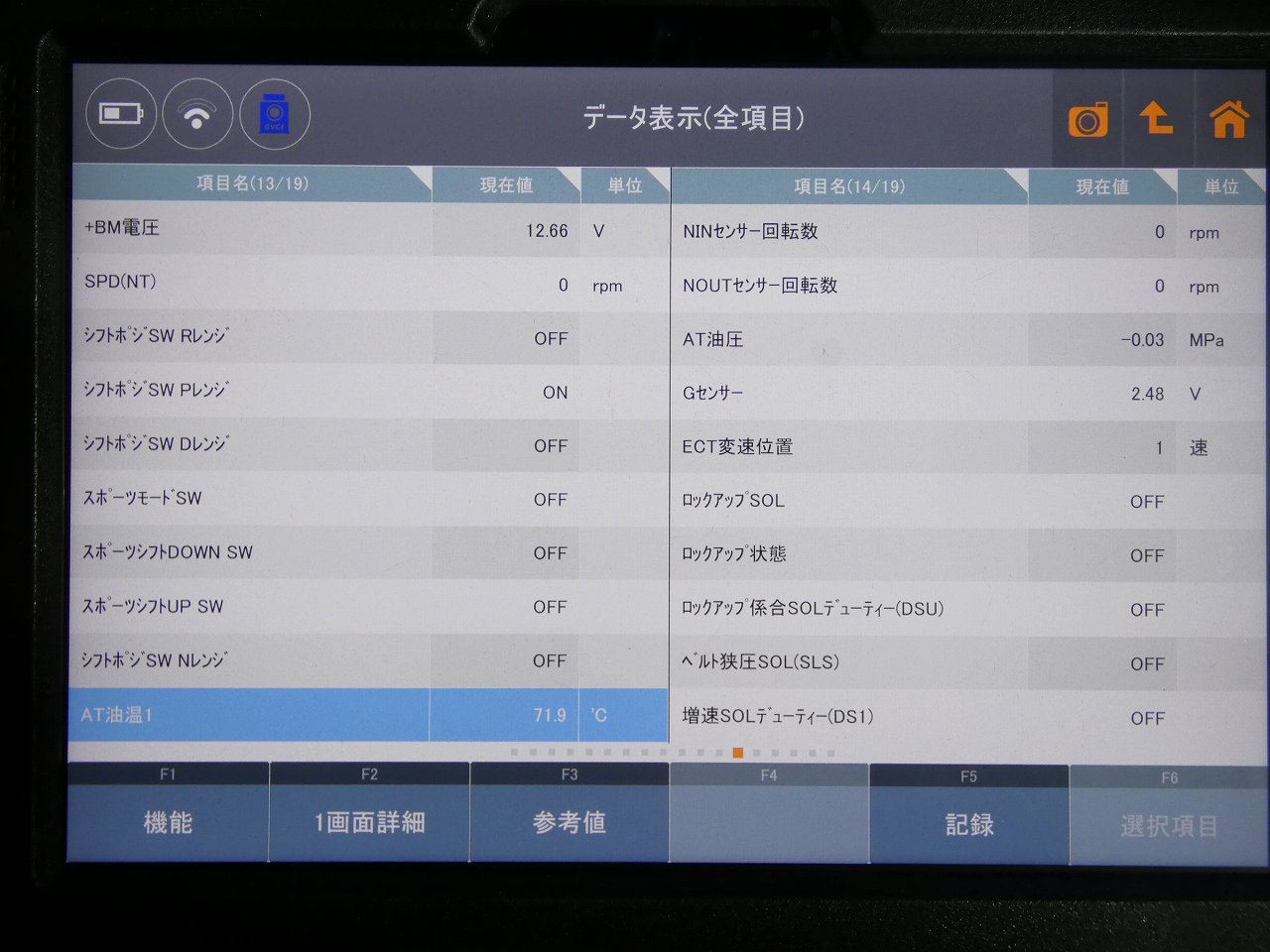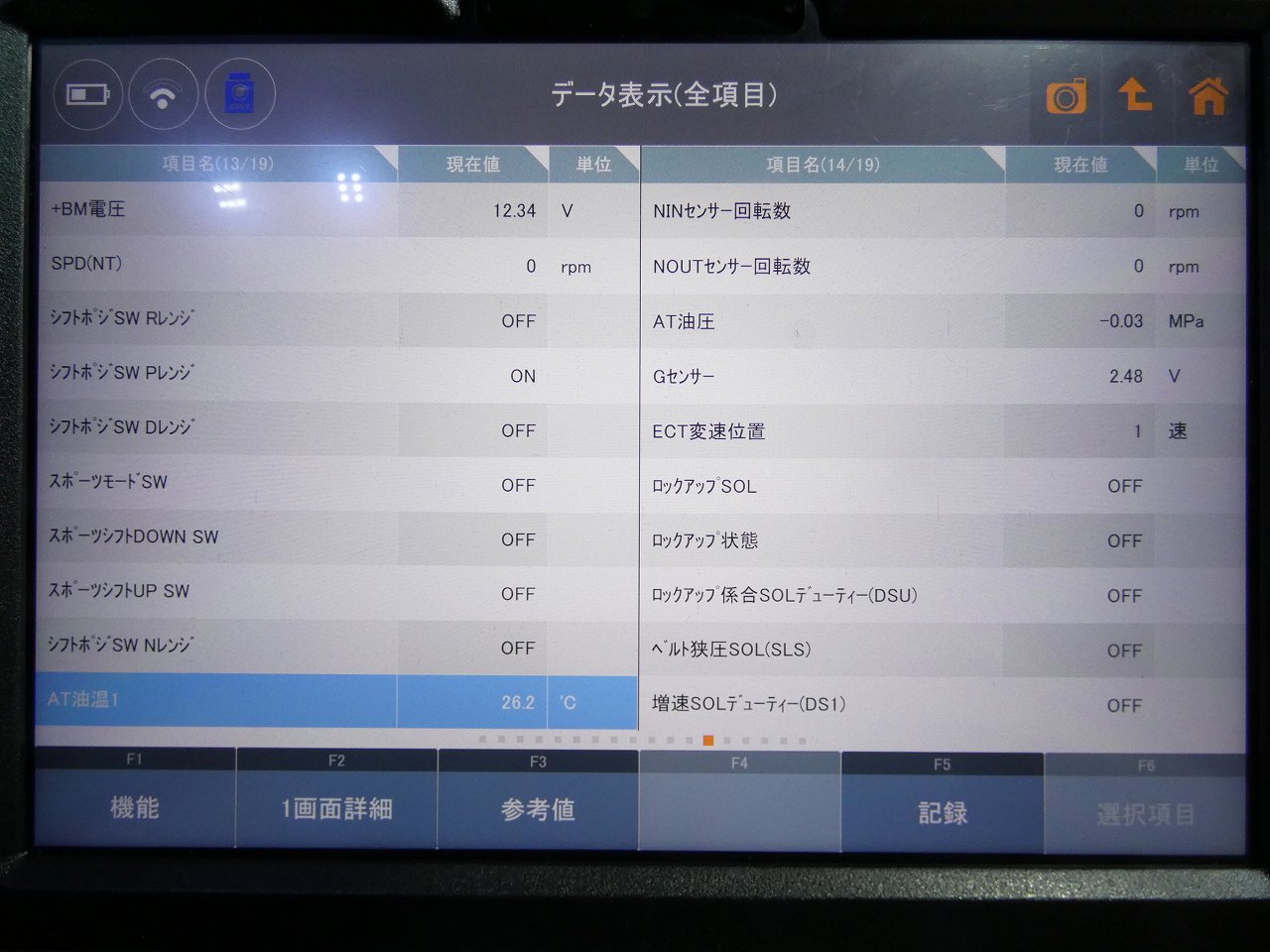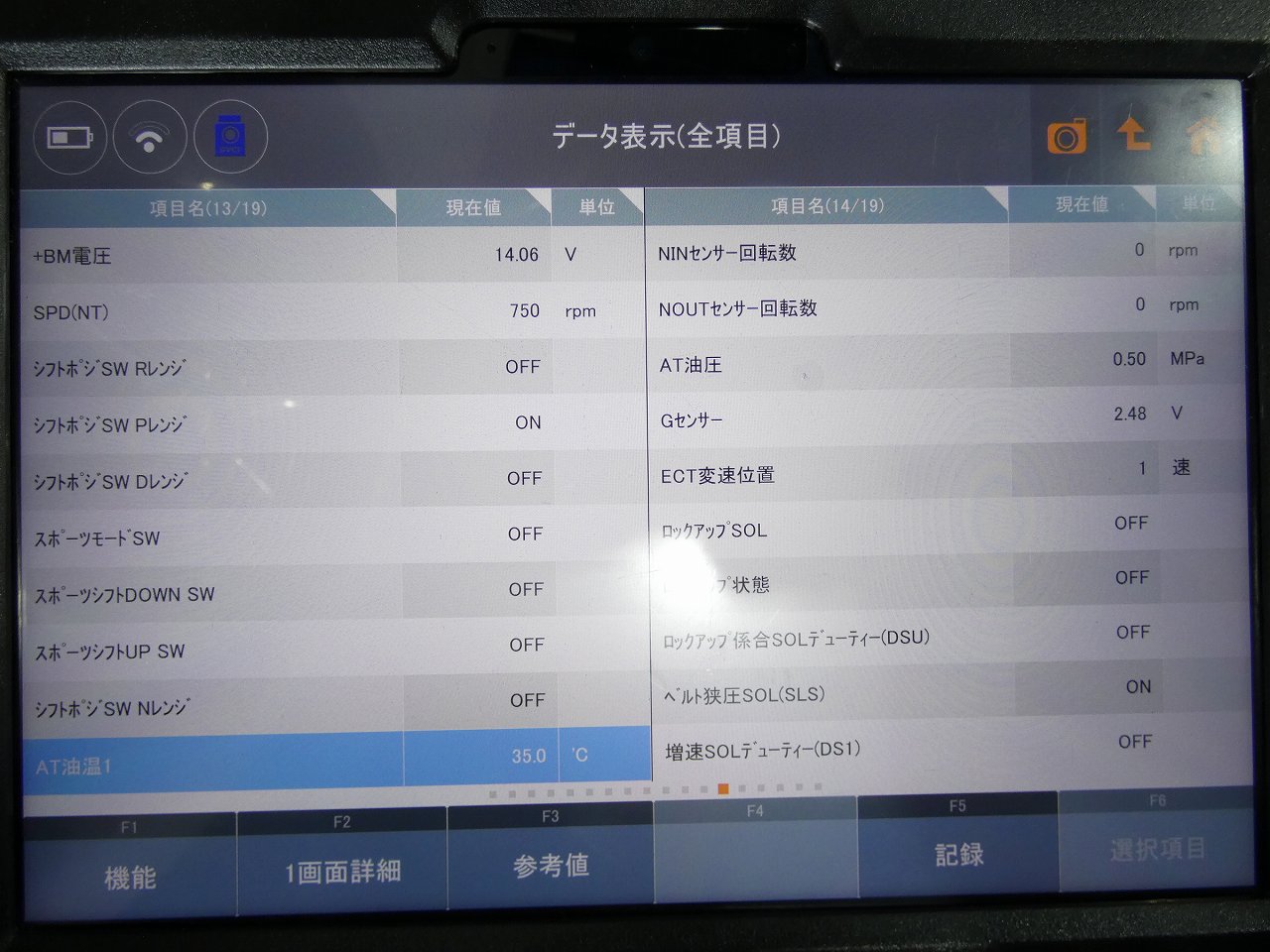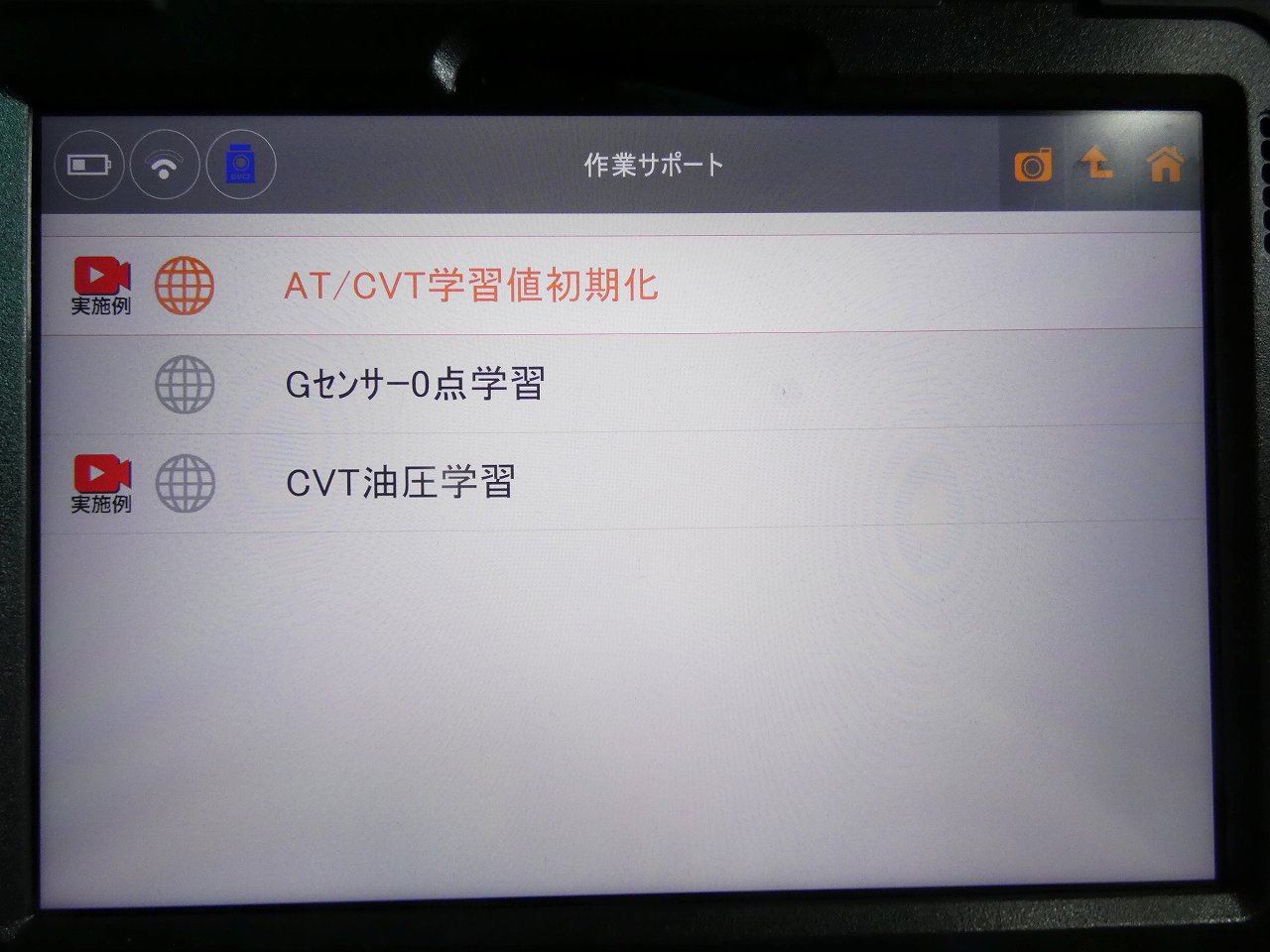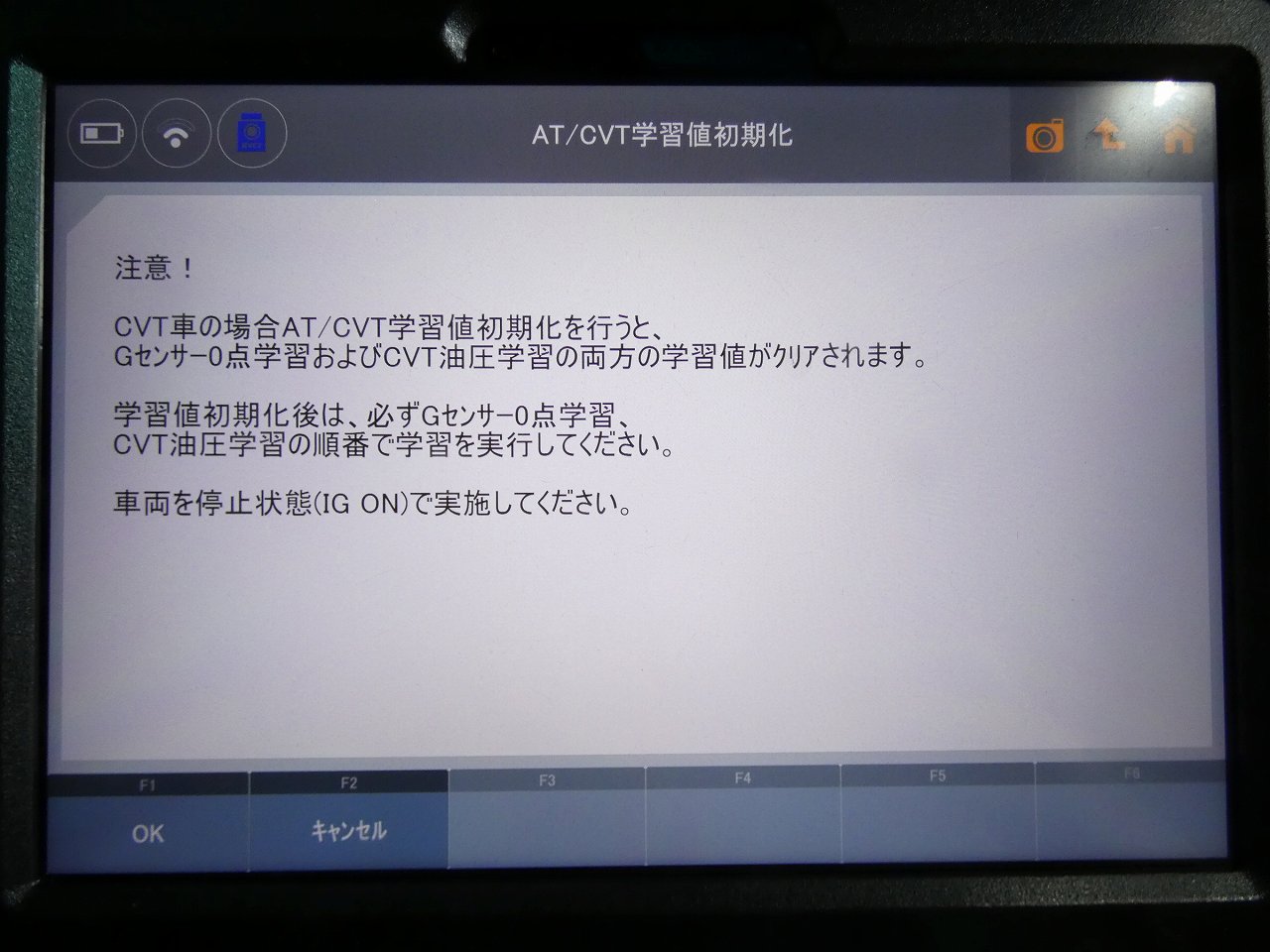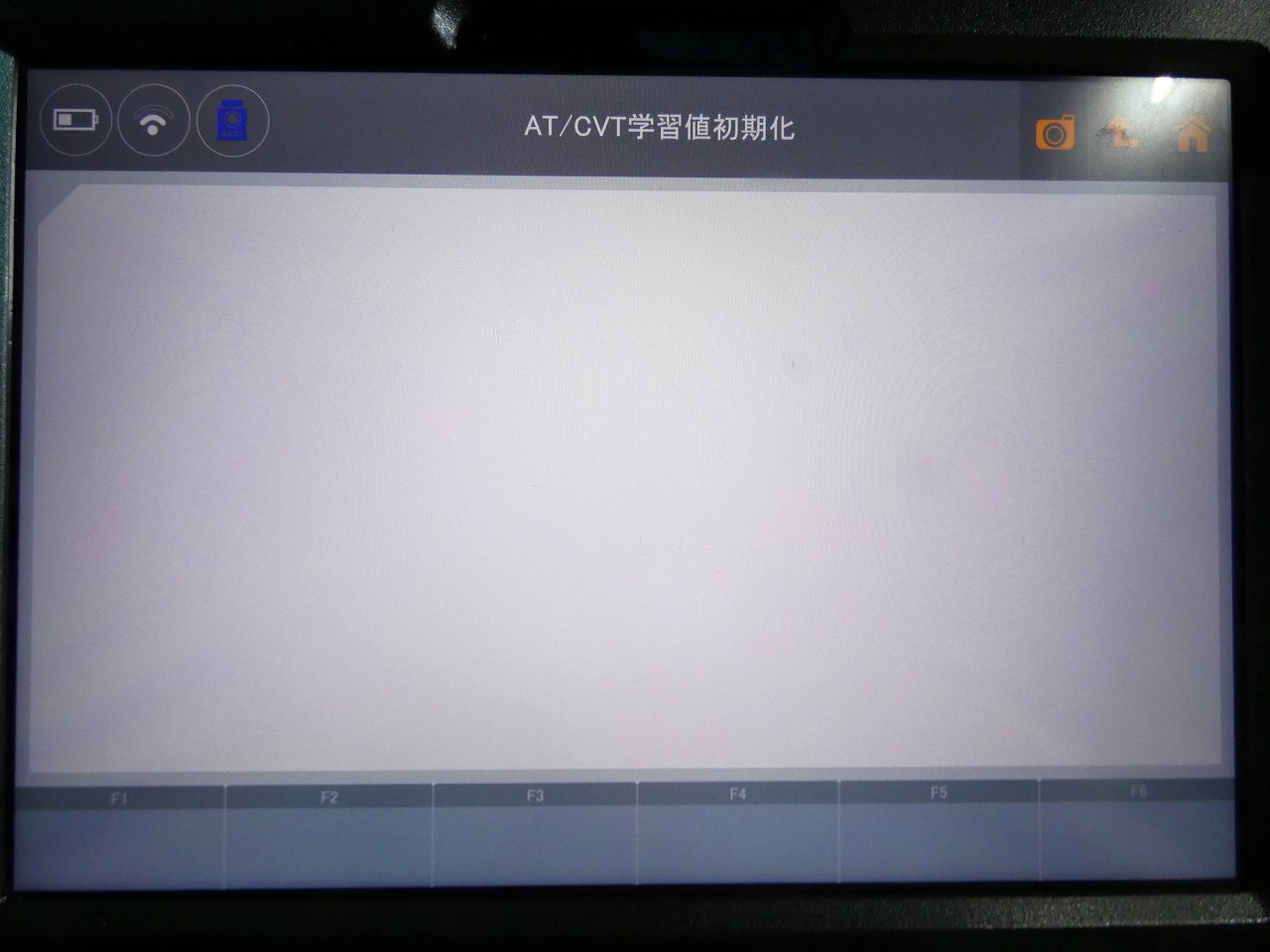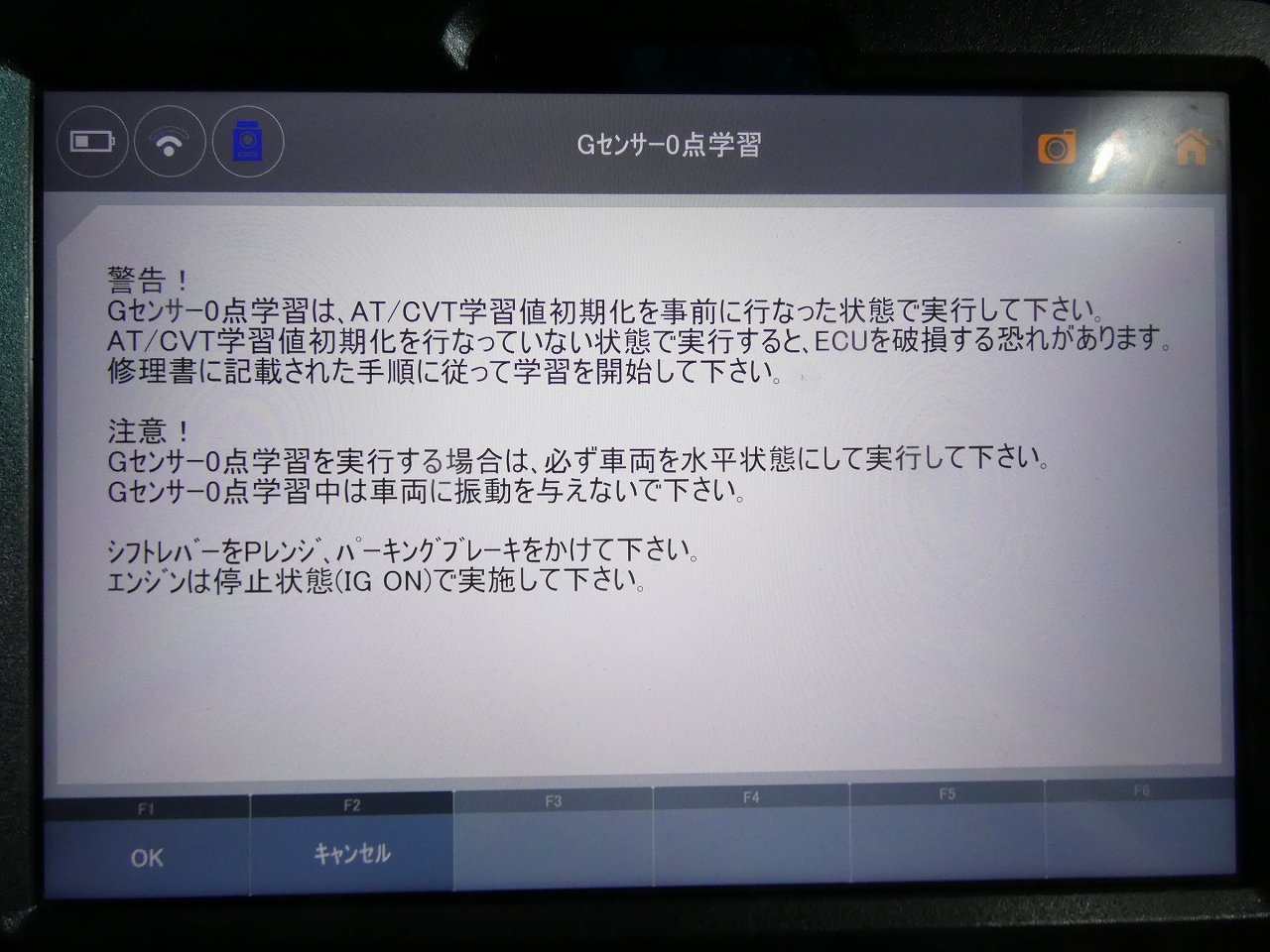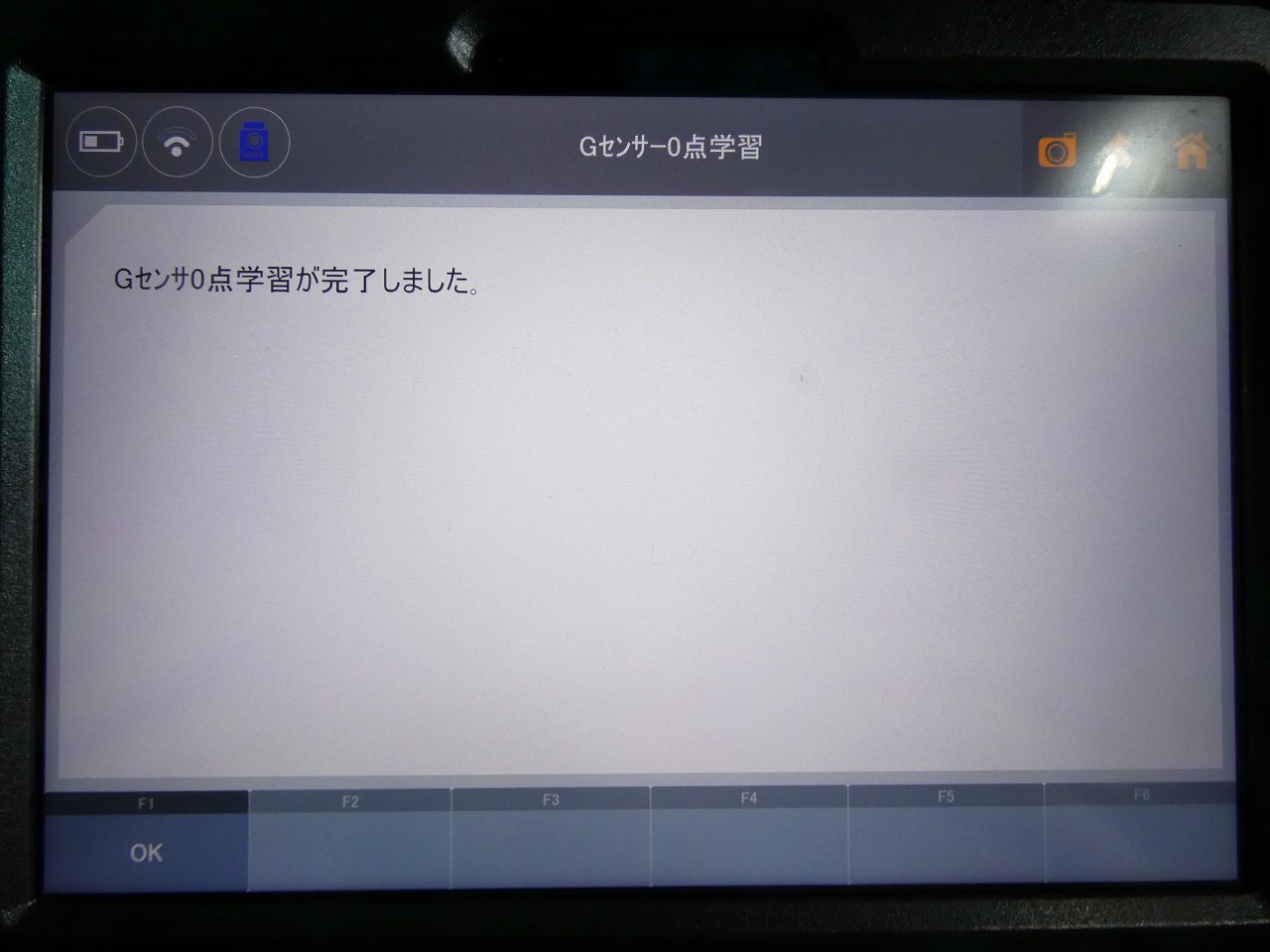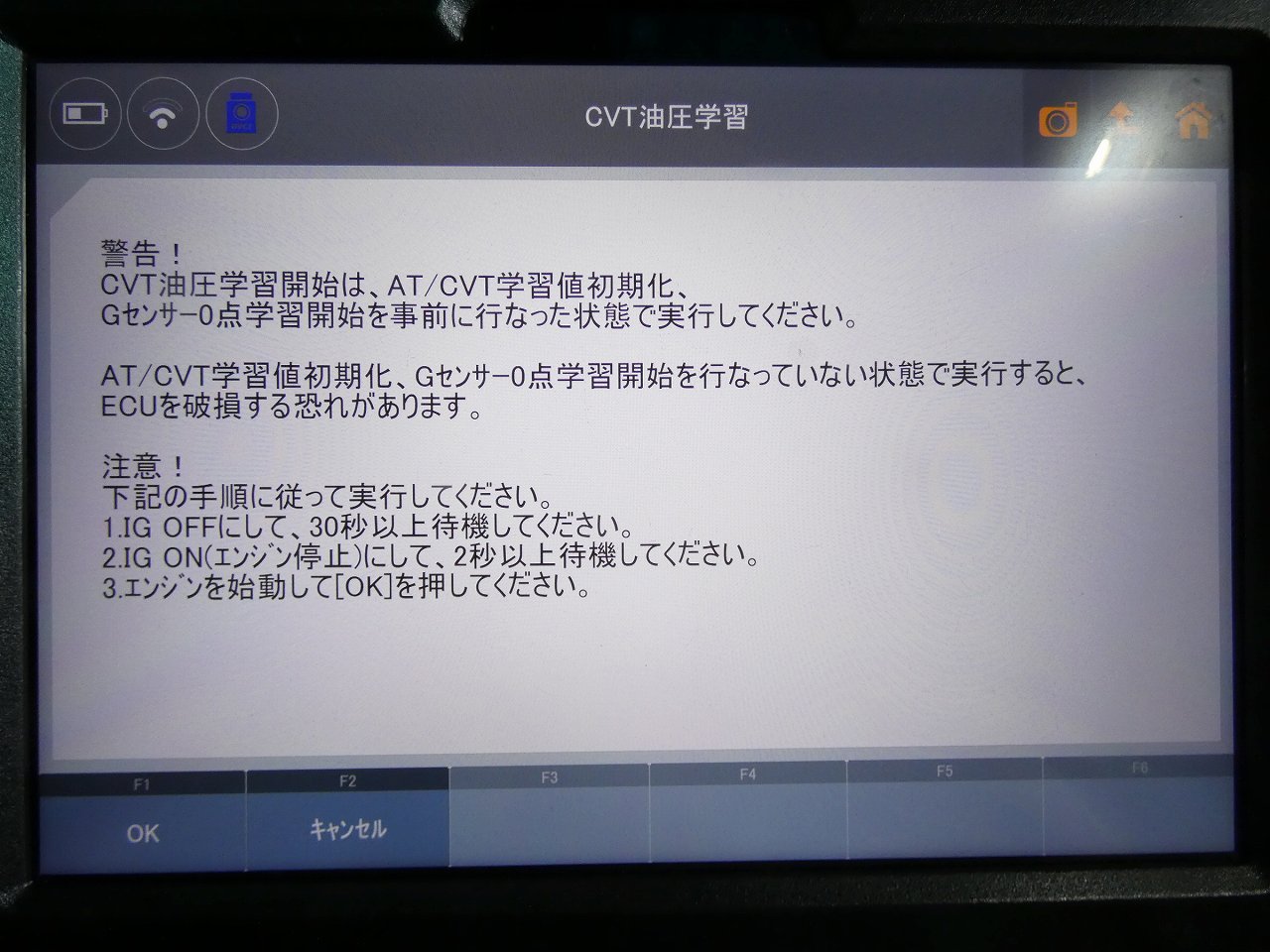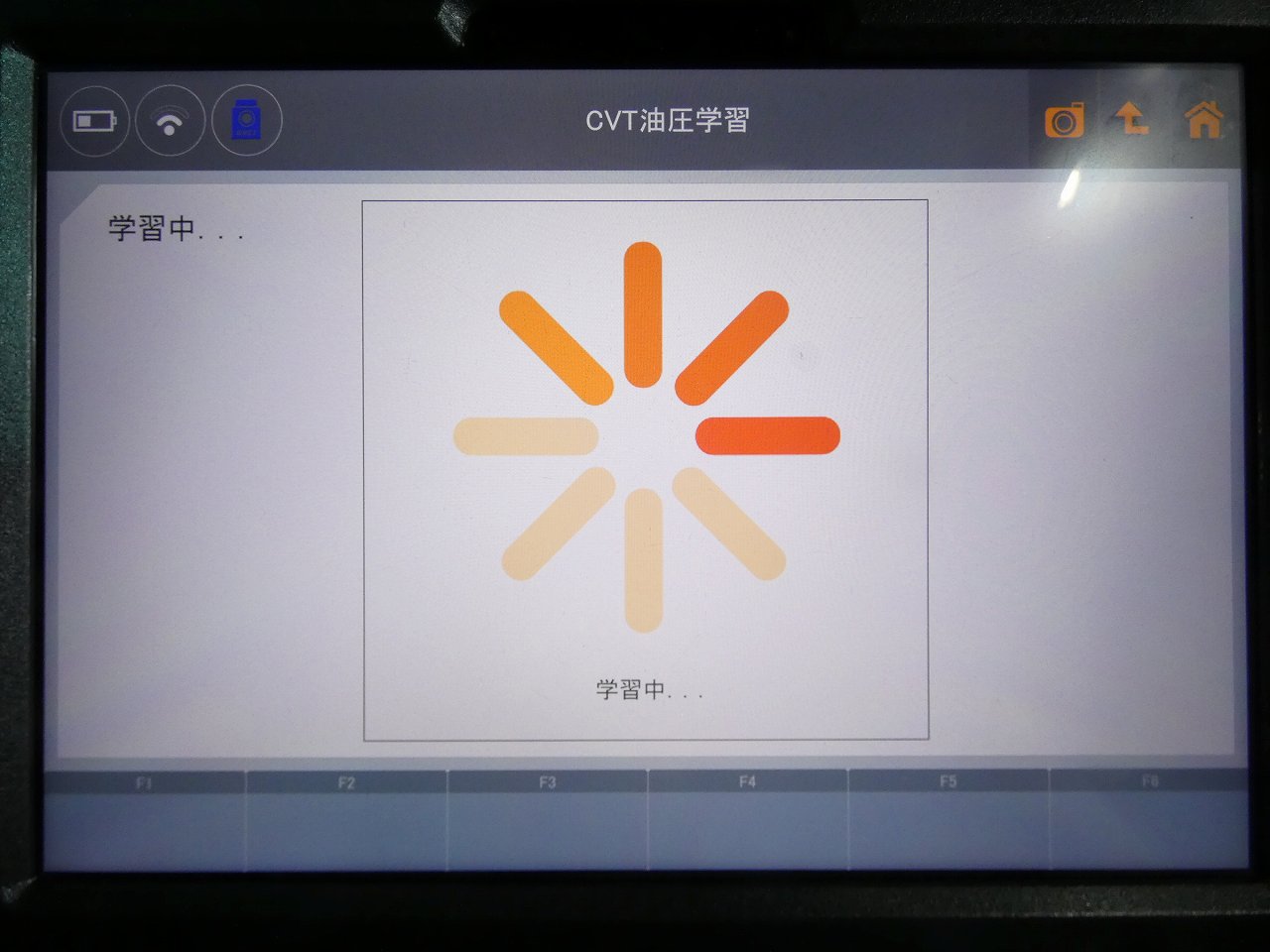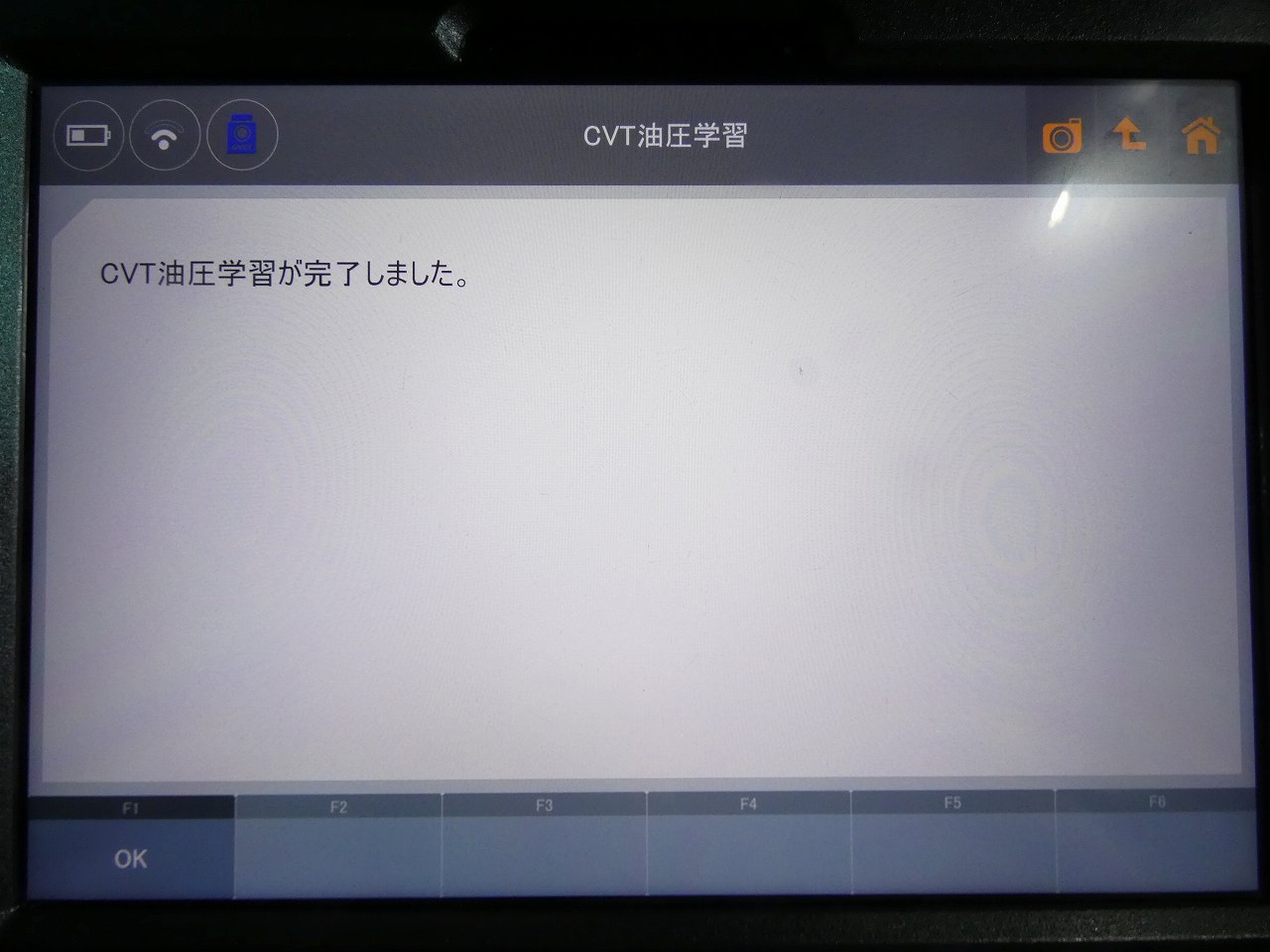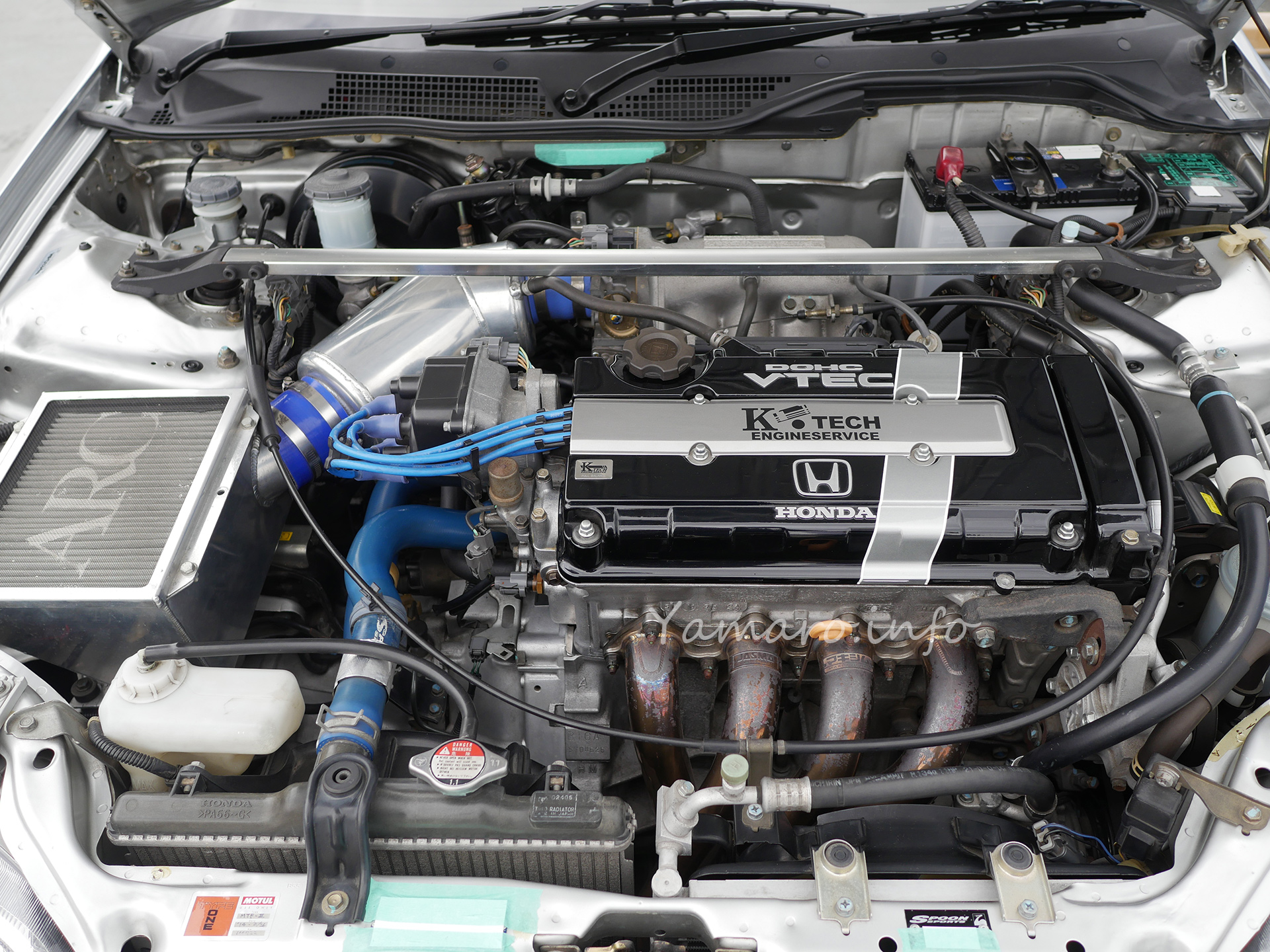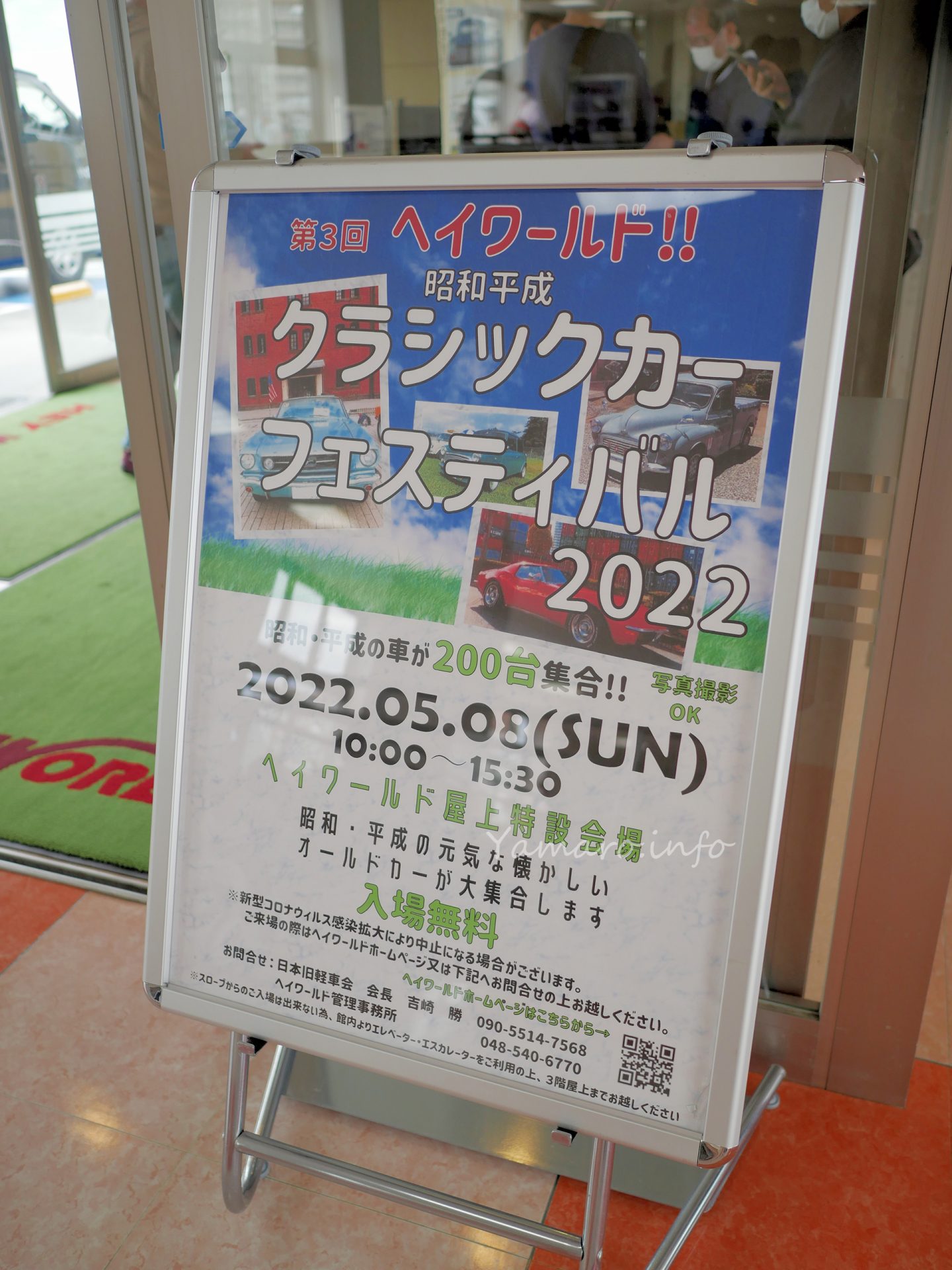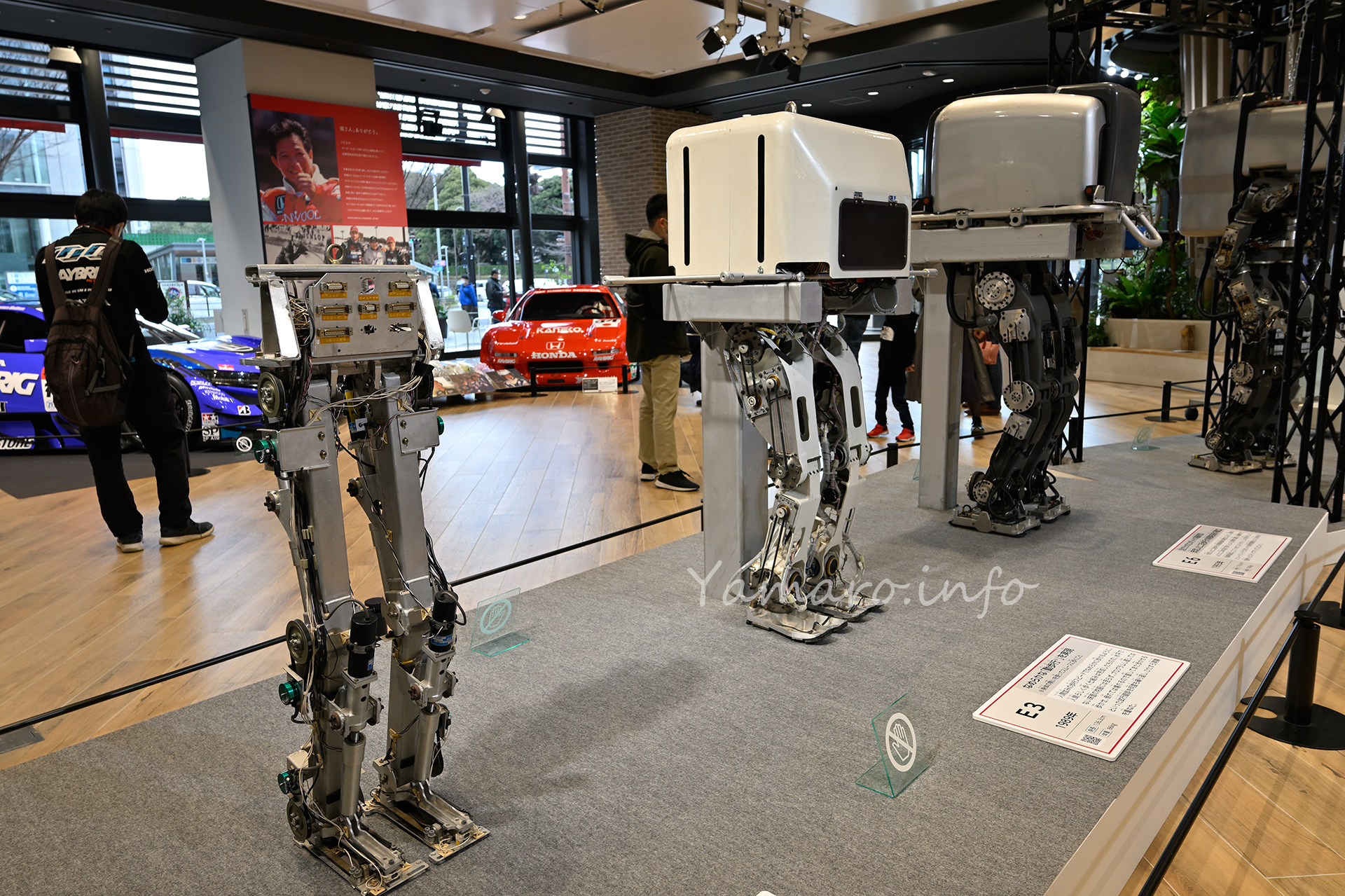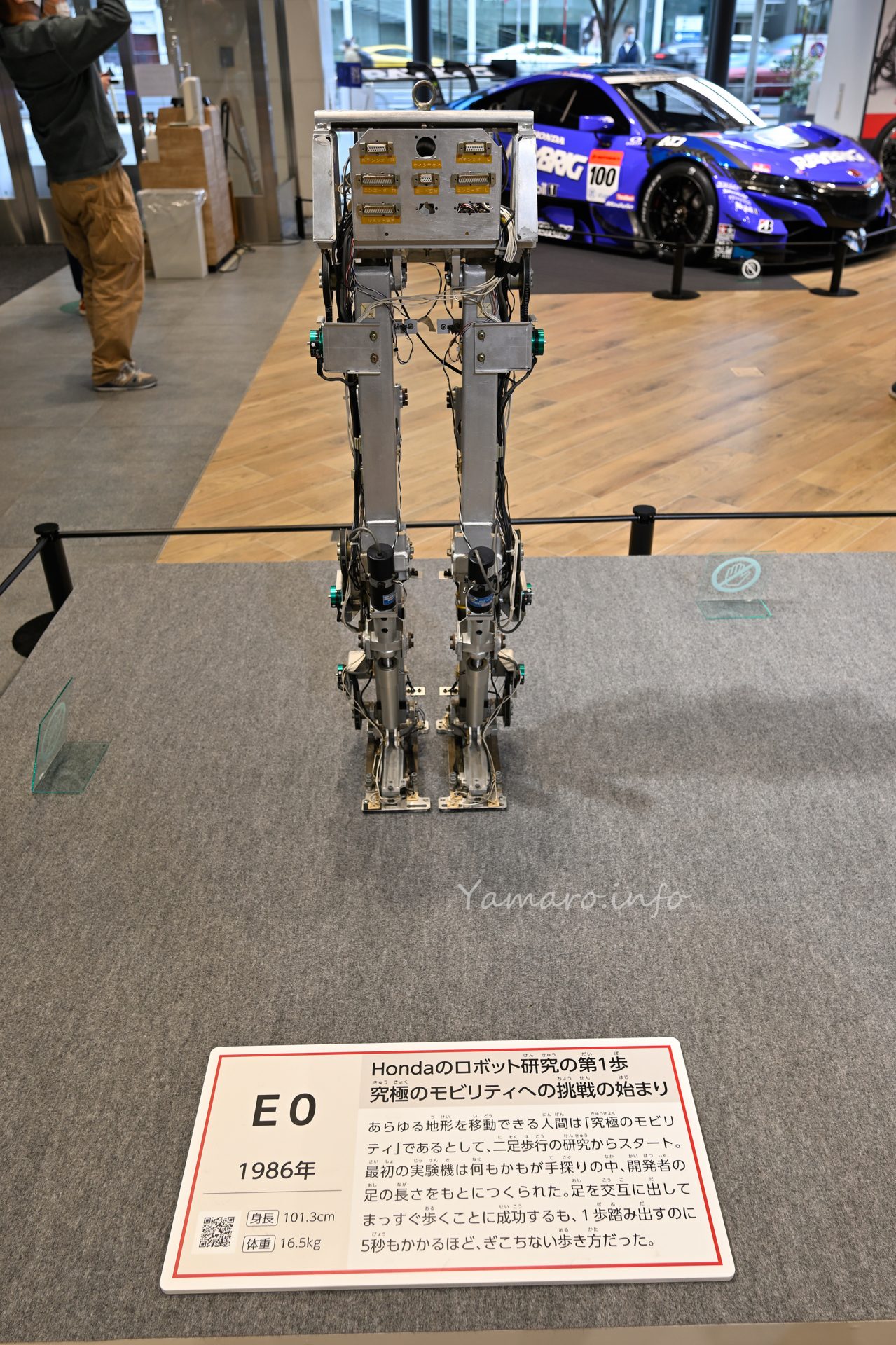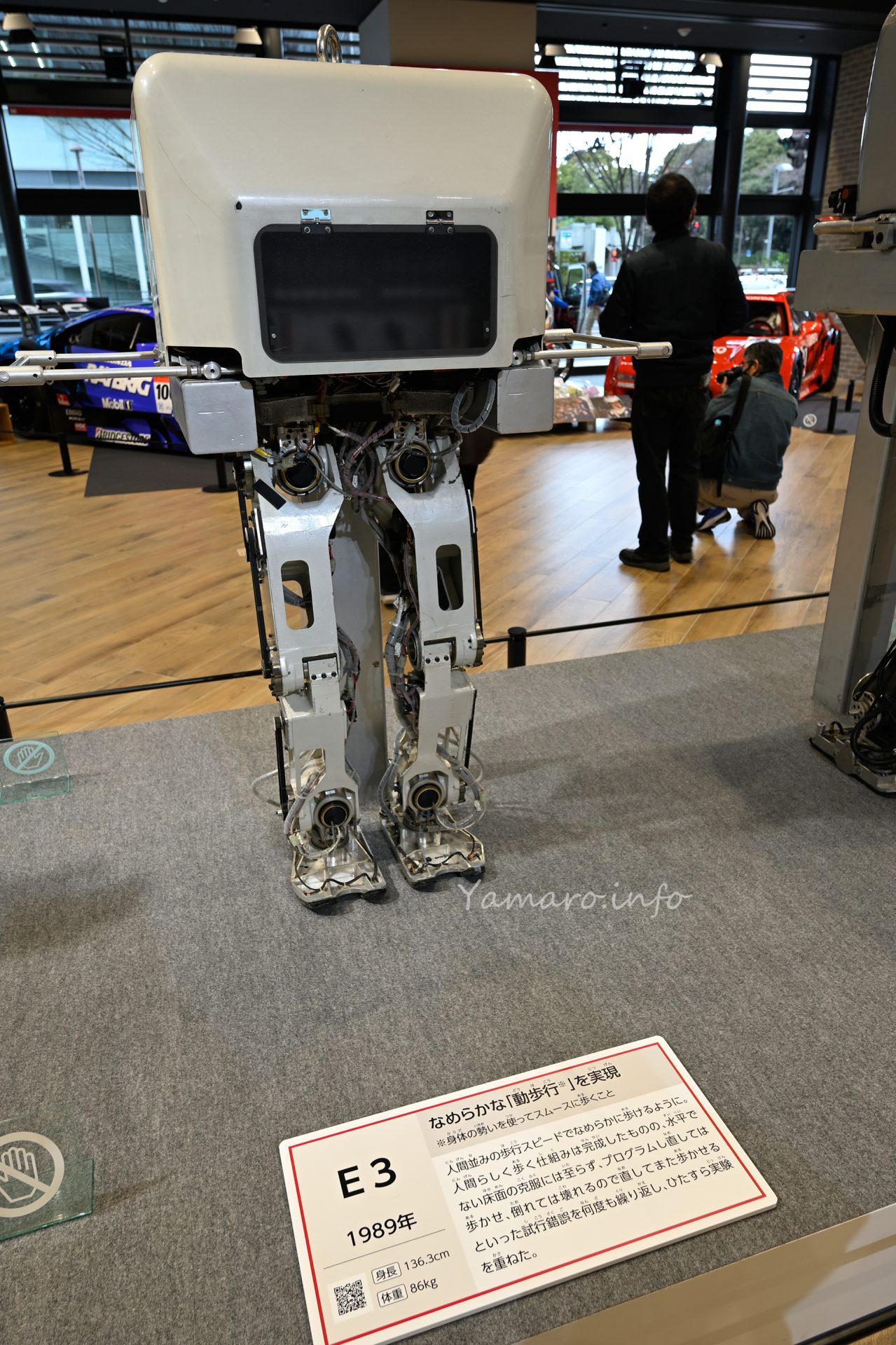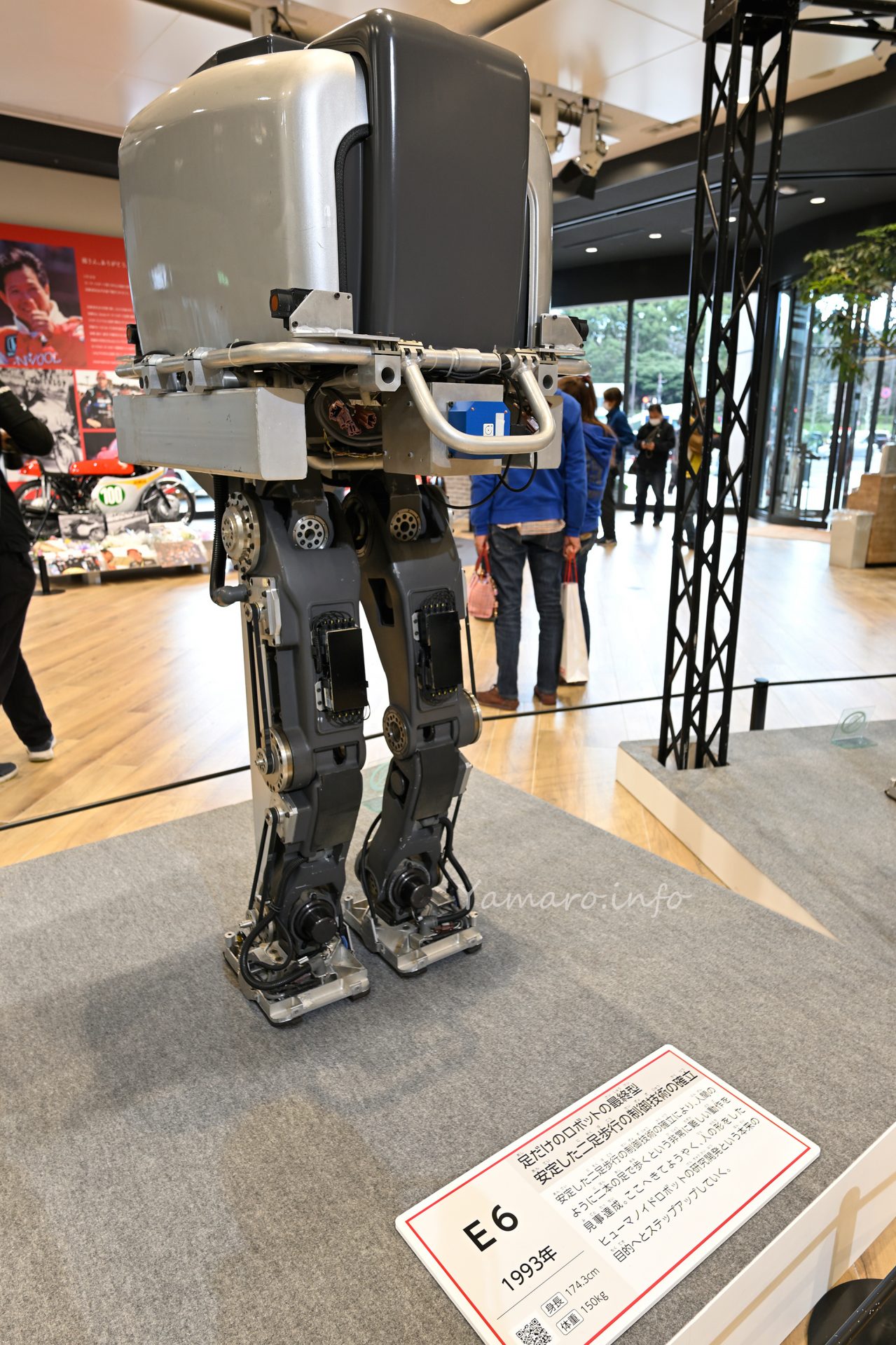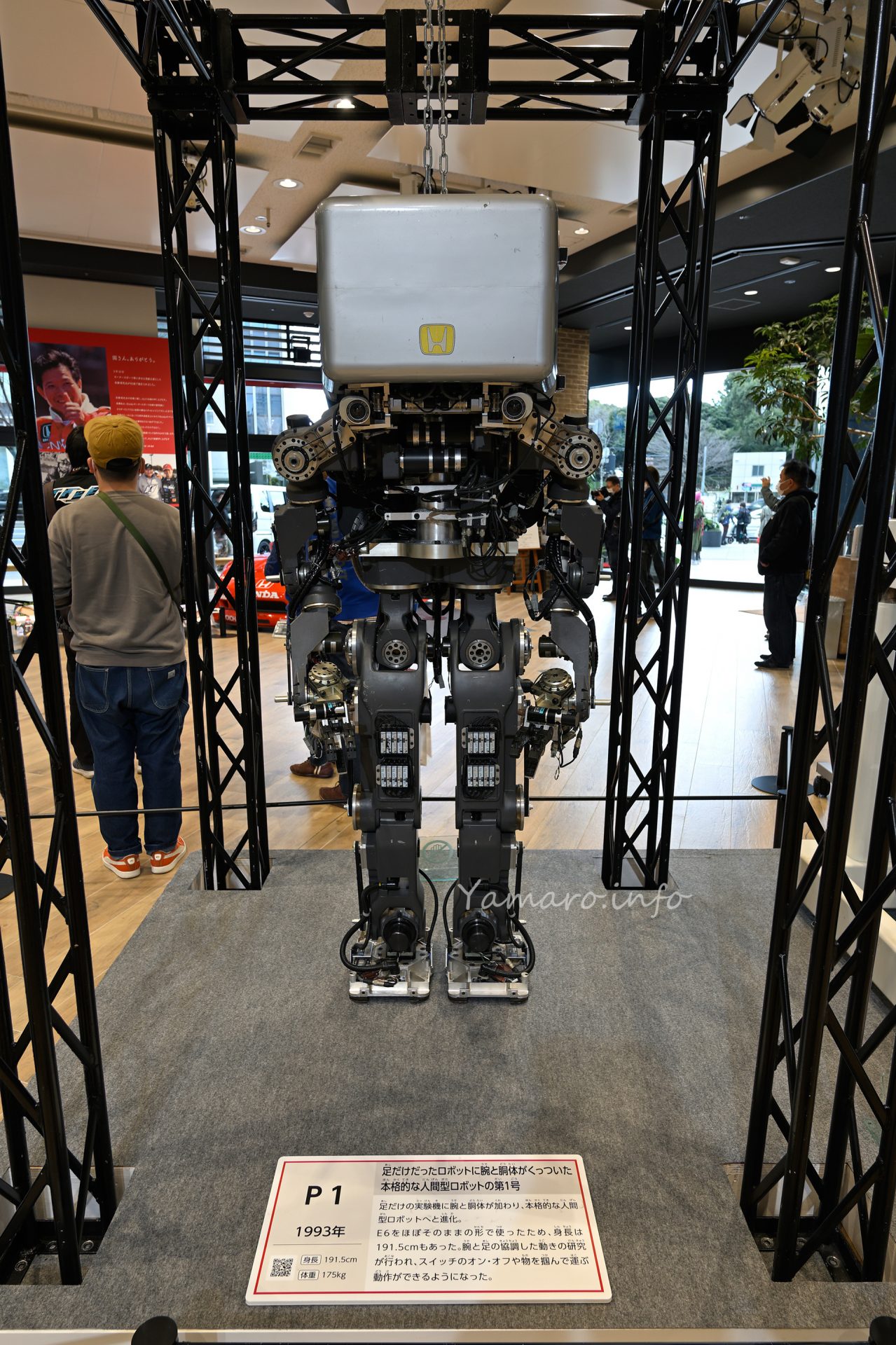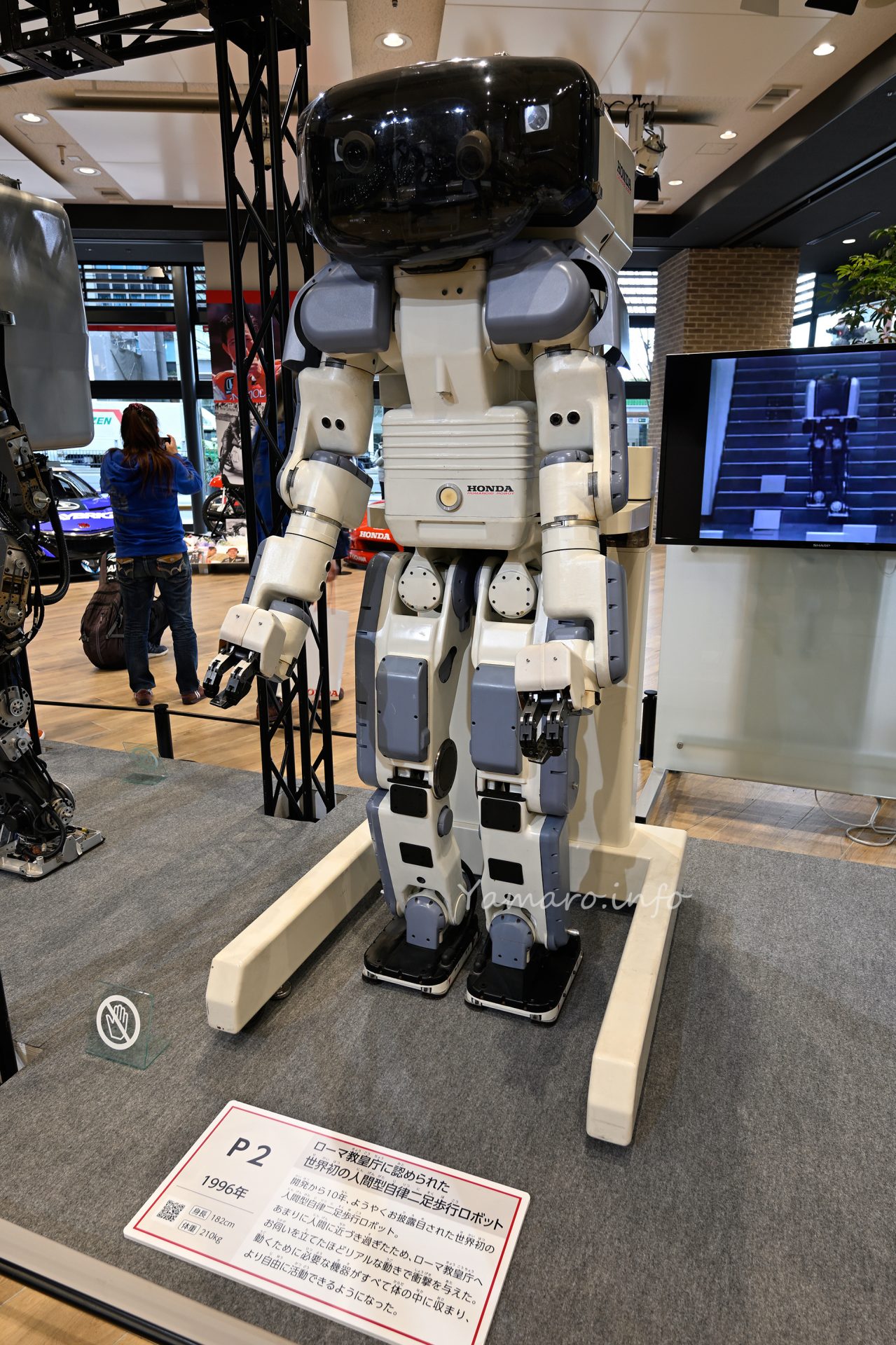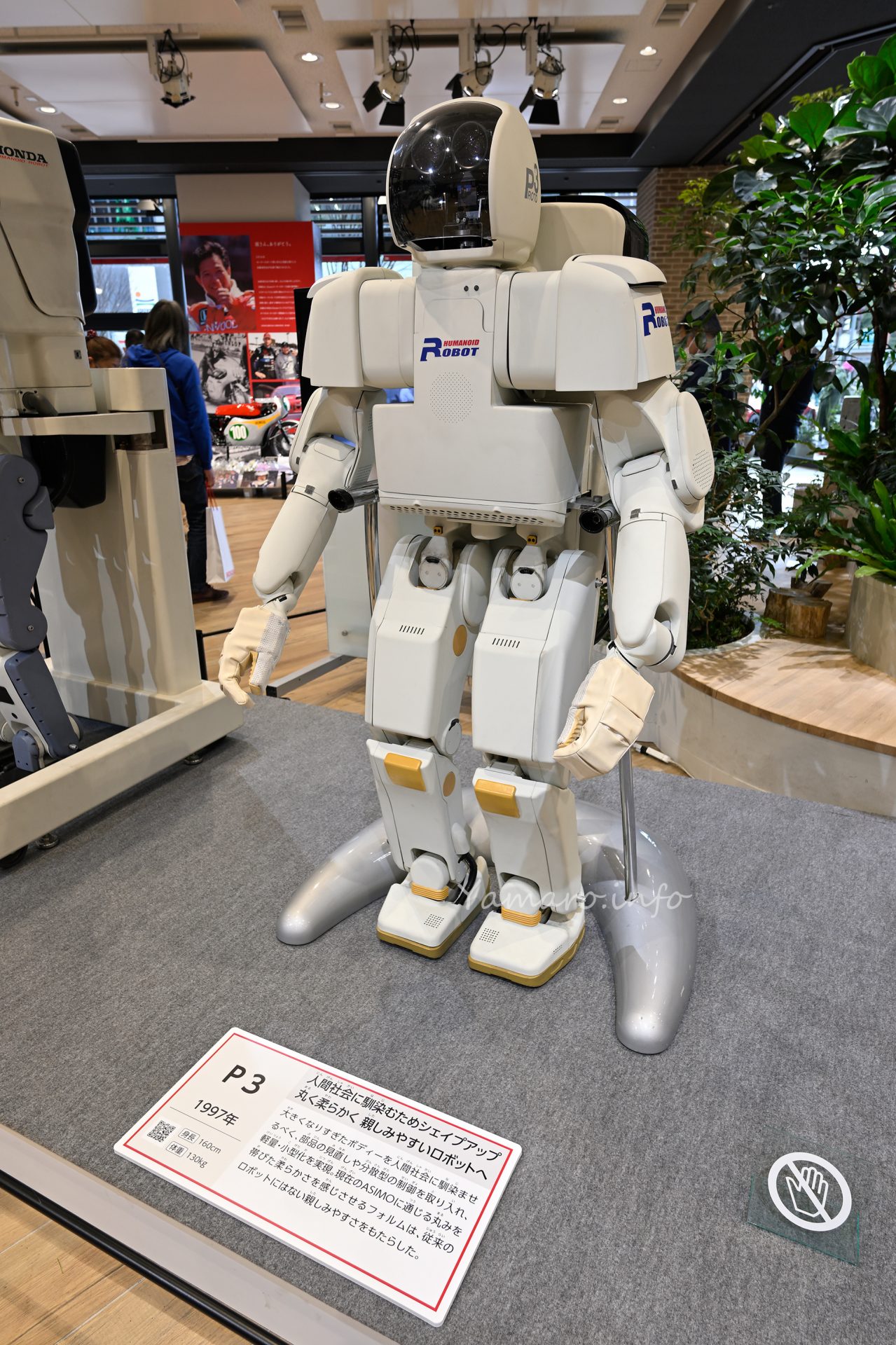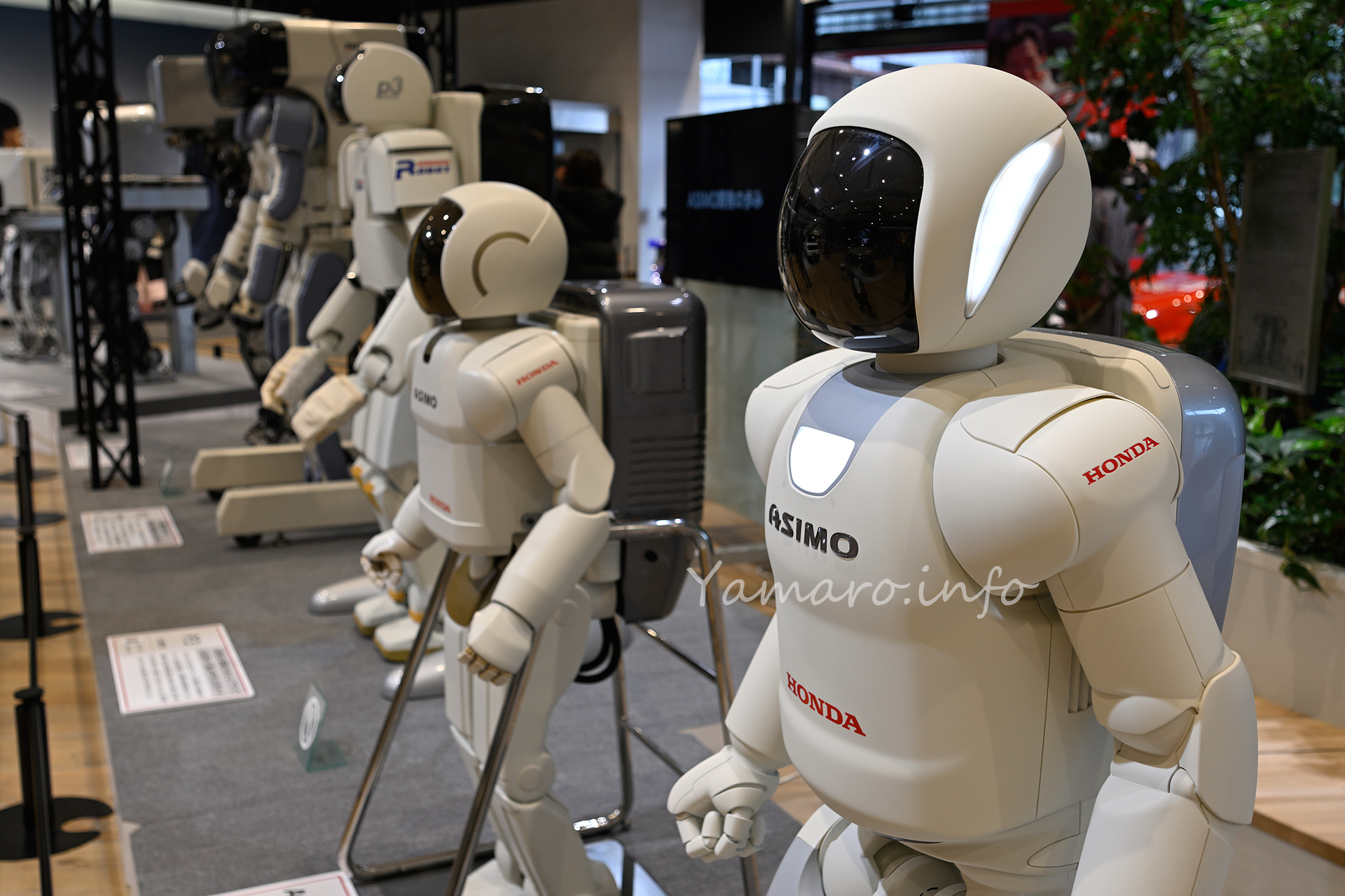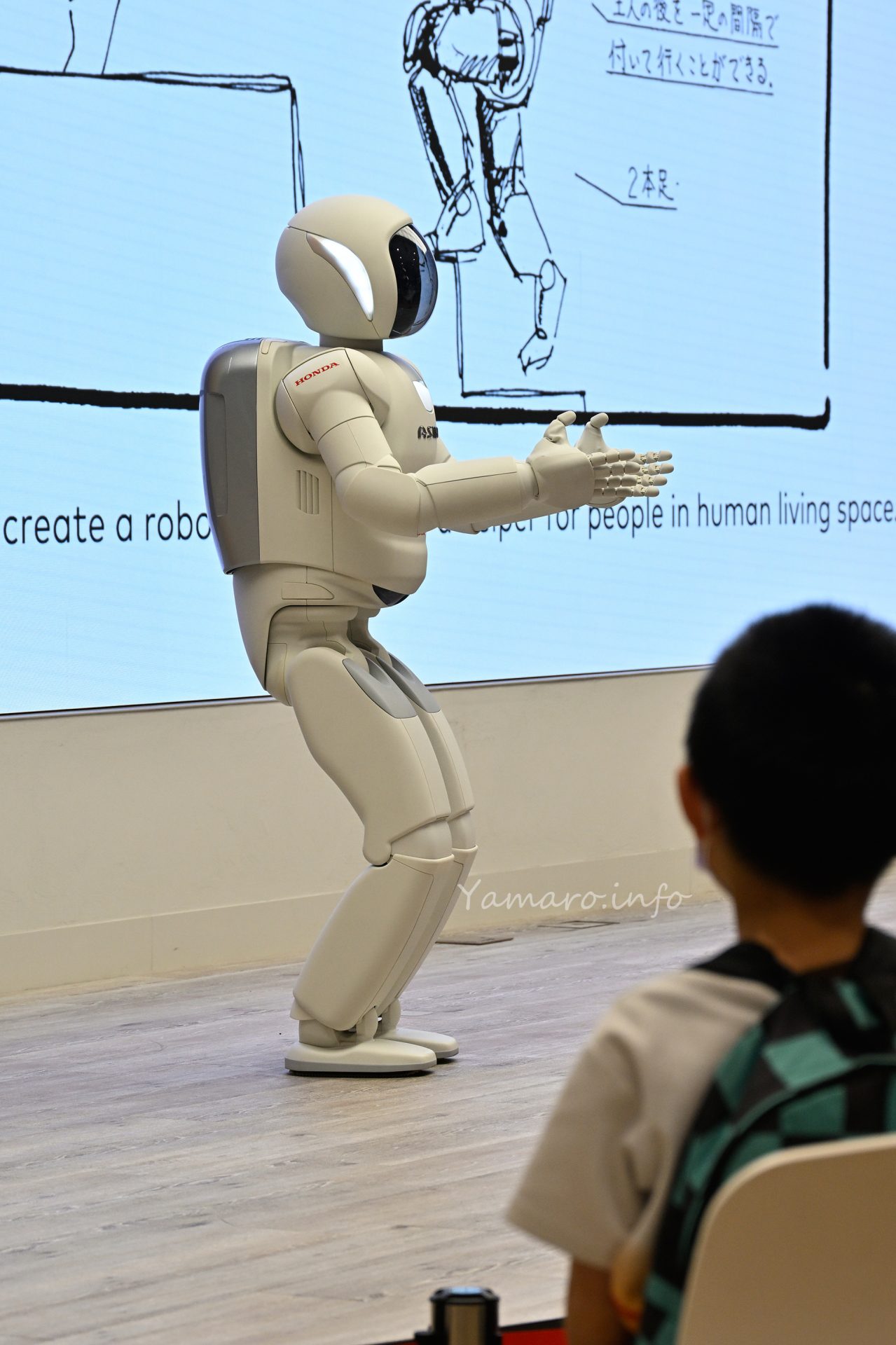VRX3アンバサダーのYamaroです。
2021年も終わりが見えてきた11月、ブリヂストンより、こんなキャンペーンが展開されました。
 BLIZZAK VRX3アンバサダー募集(現在は終了しています)
BLIZZAK VRX3アンバサダー募集(現在は終了しています)履いていたスタッドレスのBLIZZAK VRXが5年を迎え、溝はまだあるけど、そろそろ交換時期かなと思い、何気に応募してみました。
車は、嫁車(結婚する前に妻の買った車に今でも乗っています)のエスティマ、13年目ですが、お金もないので乗り続けています。
YamaroとBLIZZAK
ブリヂストンのスタッドレスタイヤといえばBLIZZAKです。雪国の北海道では、昔から装着率50%を誇ると言われている、信頼性の高いスタッドレスタイヤです。
自分が初めて買った車(ホンダ・ドマーニ)も、BLIZZZAK MZ-02でした。
しかし、就職して北海道を離れてからは、最初に住んでいた山梨は山の方は積雪すれど、地元の方は常時雪があるわけではなく、スタッドレスタイヤも他メーカーのものを使っていました。その後、転職して栃木へ、栃木は宇都宮市はほぼ雪が降りませんが、年に何回かは積雪があり、路面凍結が怖いので、スタッドレスは使っていました。
東京に転勤となった今も、帰省やレジャーで凍結が怖いので、基本冬季間はスタッドレスタイヤですが、通勤に使うわけでもないので、もったいない気がしていました。でもやっぱり安心を買うということで、スタッドレスタイヤは欠かさず冬は装着しています。
ずっと他メーカーのスタッドレスでしたが、久しぶりにBLIZZAKに戻ったのが2016年、VRXを導入しました。
BLIZZAK VRX、やっぱりスタッドレスはブリヂストンだな~というのを実感したのが、現在関東に住んでいて、冬季間の殆どを乾燥路面で過ごす、ちょっともったいない使い方でしたが、乾燥路面でもまるでサマータイヤかのように、グニャグニャした感触なく走れることと(それまで履いていた他メーカー製はグニャグニャ柔らかい感覚が少しあった)、雨のウェット路面での安心感が違いました。
本当によく出来ています。
2020年は、妻の実家に置かせてもらっていたサマータイヤに、COVID-19のまん延で帰省できなかったため、タイヤの履き替えが出来ず、1年半をスタッドレスのVRXで過ごしましたが、もちろんサマータイヤより剛性感は落ちるものの、割と普通に走ることが出来たのは、さすがだなと思いました。
なので、やっぱり次もBLIZZAKかなぁとは思っていましたが、BLIZZAK、物が良いだけに高価です。他のメーカーを試したいというのもあって迷っていました。
VRX3アンバサダー、当選!
12月も半ばになった時、こんなメールが届きました。
この度は、キャンペーンにご応募いただき、ありがとうございました。
BLIZZAK VRX3 アンバサダーキャンペーン事務局です。
厳正なる審査の結果、アンバサダーに当選されましたので、ご連絡いたしました。
おおお! 買えば、エスティマのサイズで215/55R17だと4本で13万円程度するVRX3をいただけるとは!
そして年末に、タイヤが届きました。
 VRX3届きました!
VRX3届きました!車のパーツって、家に持ち込むと大きい!、タイヤも! 定価だと1本5万円もするんですね。
年末は予定が立て込んでいたので、2022年年が明けてすぐに交換を行いました。
 アウトドアカードで車まで移動
アウトドアカードで車まで移動
 さすがミニバン、4本余裕で積めます
さすがミニバン、4本余裕で積めます
 ガソリンスタンドで交換してもらいました
新しいタイヤっていいですね!
ガソリンスタンドで交換してもらいました
新しいタイヤっていいですね!
外したVRXも、まだ冬用タイヤとして使える溝の残量はあり、ものすごく硬くなったという印象もなく、少々もったいない気もしましたが、廃タイヤ処分してもらいました。
いきなり高速道路を走行してみた
交換後すぐ、皮むきがてら、高速道路を走行してきました。趣味の撮影がてら、まずは乾燥路面での皮むきです。

 乾燥路面走行は、まるでサマータイヤのように剛性感のある走り
乾燥路面走行は、まるでサマータイヤのように剛性感のある走り
いやはや、高速道路で100km/h出しても、特に違和感ありませんね。よく出来ています。
これは以前のVRXでも感じていましたが、BLIZZAKの剛性感はとても良く、とにかくグニャグニャした感触は一切ありません。そういう意味では、VRXから出来が良かったので、2世代新しいVRX3で悪いはずもなく、走りはさらにシャープさが増しました。ハッキリ言って、サマータイヤと変わりません。乗り比べたら違うけど、もしこれだけで走行しても、ほとんど違和感ないですね。
高速道路でのレーンチェンジも、フラつきはほぼありません。
北海道では、1年の半分はスタッドレスタイヤを履く状況なので、年がら年中スタッドレスで過ごす人も少なくありません。一昔前までは、乾燥路ではグニャグニャし、雨の日はグリップが弱く、明らかに制動距離が伸びるというのが当たり前だったスタッドレスが、今や1年中履いていても違和感ないレベルに達しています。
近年は、積雪時も使える「オールシーズンタイヤ」が登場し、販売するメーカーも増えてきましたが、今の所ブリヂストンは販売していません。個人的にも気になっていたサマータイヤですが、年間走行距離が多い、関東圏のユーザーなら良いかと思います。
が、オールシーズンタイヤの泣き所、凍結路面でのグリップ力は、やはりスタッドレスのほうに軍配が上がりますから、個人的にはスタッドレスのほうが安心ですね。これだけ乾燥路面もちゃんと走れますからね。
いざ雪道へ!
さて、関東に住んでいると、1シーズンで2,3回程度しか雪が降らないし、降っても基本週末にしか乗らないとなると、雪道走行は皆無ですね。
というわけで、せっかくVRX3アンバサダーになったのですから、雪道レポートせねば! ということで、政府より子供に1人あたり5万円の給付金が出るのもあり、そして子どもたちが雪遊びをしたい!というのもあり、せっかくなので雪遊びできるところに泊まりで行こうとなりました。
その模様は下記ブログに書いています。
ここではBLIZZAK VRX3の雪道レビューをメインに。

 群馬県利根郡川場村の1月はしっかりと雪がありました
群馬県利根郡川場村の1月はしっかりと雪がありました
群馬県でも北の利根郡川場村、ご覧のように道路も雪があり、北国そのもの。もう少し北上すれば、新潟の湯沢とか魚沼があるわけですから、ここも雪国でした。
圧雪と、やや溶けかかったシャーベット状、日当たりが悪い路面は凍結と、明らかに関東とは違う、雪国の路面状況です。
圧雪路面は、スタッドレスタイヤの得意とするところです。VRXでも、安定していましたが、VRX3ではさらにしっかりとグリップしています。とにかく、ゆっくり走っている分には全く怖さがないです。
元北海道民とは言え、関東に十数年も住んでいると、雪道走行の機会はかなり減ってしまい、最初はドキドキでしたが、すぐに安心して走れるとわかりました。安定感はかなりよく、アイスバーンのコーナーでやっと少し滑る感触はあれど、滑り出しがゆっくりなので、対処が容易です。昔なら、少しでもアクセルペダルに足を載せるようなら、いきなりグルンと回ってしまうような轍でも、問題なしです。
うちのエスティマは、まだESP(トヨタで言うVSC、横滑り防止装置)が標準装備となる前の古い世代の車ですが、発進時にギュイーンと空転することもなく、グリップは抜群に良いです。ここはVRXと比べても格段に進化しています。
いちばん重要なブレーキングでも、ABSが動作するのは、意地悪にブレーキペダルを踏むときくらいで、ゆっくりじんわり踏むと、ABSが動作することなく停車できます。
 BLIZZAK VRX3なら圧雪路面は安心だな~
BLIZZAK VRX3なら圧雪路面は安心だな~他メーカーの同世代と比べることは出来ないけど、やっぱりBLIZZAKなら安心だな、というのが実感できますね。
冬の山道、たんばらスキーパークへ向かう
こんなに雪があるとは思わなかった! たんばらスキーパークへの道は、完全なる冬山道路でした。関東から近場のスキー場だと、駐車場も雪がなく、人工降雪機でなんとか運営しています、というスキー場も多い中、ここはスキー場までの道路が手前7,8kmから完全に山坂道。逃げ道もないし、スタッドレスタイヤは必須です。多分、オールシーズンタイヤでは、坂道を上がれないでしょう。
この日は晴れていて降雪はなかったので良かったですが、降雪時は除雪が間に合わない可能性もあります。FF車でも問題ないですが、タイヤだけはスタッドレスにしましょう。チェーンもあると、更に安心ですね。
 たんばらスキーパーク、積雪は1mをゆうに超えています
たんばらスキーパーク、積雪は1mをゆうに超えています
 お泊りしたペンション、毎日除雪機で除雪しているみたいです
お泊りしたペンション、毎日除雪機で除雪しているみたいです
積雪は1mどころか、道中も除雪した雪の壁が2mくらいはあるので、雪道初心者はあまりおすすめできないかも…。雪だけでなく坂道というのがネックです。坂で停車してしまうと、路面状況によっては二輪駆動の車は厳しいかもしれません。
幸い、VRX3を履いたエスティマ、やや渋滞気味のスキー場までの道中、何度か停車しましたが、発進は問題ありませんでした。が、油断は禁物です。


 ここまで雪があると、北海道に住んでいた頃を思い出します
ここまで雪があると、北海道に住んでいた頃を思い出します
こんなに雪があると、何だか北海道に住んでいた頃を思い出しますね。関東育ちの子どもたちに雪は新鮮だったようで、雪遊びのつもりが結局スキーをやることになりましたが、こんなに積雪があるので、たんばらスキーパークの雪質は素晴らしく、二十数年ぶりのスキーだったけど、楽しく滑ることが出来ました。終わったら筋肉痛でしたけどね(笑
雪道の下りも安心だったVRX3
雪道で一番怖いのは、下りのコーナー。
実は、免許を取って初めて車を買って、実家に帰省中の雪道、下りでコーナー、ややスピードが出すぎてしまって、テイルから滑って立て直しが出来ず、路肩に落ちてしまったことが。幸い、このときは雪がクッションになって車は無傷、通りかかったトラックに牽引してもらって脱出できました。
以来、下りはかなり慎重です。
今回、たんばらスキーパークからの帰り道は、下りでコーナーもたくさんありましたが、速度は抑え気味で、エンジンブレーキ併用でクリア。滑っていく感触もなく、麓まで降りれました。

 サラダパークぬまたで雪遊び
サラダパークぬまたで雪遊び
そして、サラダパークぬまたで雪遊びしてきましたが、日当たりの良い路面は雪が溶けて滑りやすい状況でした。ここで初めて、意図せずブレーキングでABS作動でもそれは一瞬で、車が意図せぬ向きに滑ることはなかったですね。
やはり雪道で怖いのは、アイスバーンと溶けかかった路面ですね。
というわけで、ガチな雪道から、乾燥路面まで、オールラウンドに走れてしまうVRX3、相当な実力の持ち主ですね。関東住みには宝の道ぐされ感は否めないものの、乾燥路面も安心して走れるのは魅力ですし、雪道やアイスバーンではトップクラスの実力です。
持ちも、VRXで5年間走ってまだ使えそうな感じでしたから、日本人の平均走行距離的な使い方なら、5.6年は問題なさそうです。
5年経ってもトレッドの柔らかさを保てるのは、さすがBLIZZAKですね。
VRX3も、VRX以上に耐久性は向上しているはずですから、長く使うならVRX3は、高価でも良い選択だと思います。
さて、13年目のエスティマ、これがこの車最後のスタッドレスになるかな…