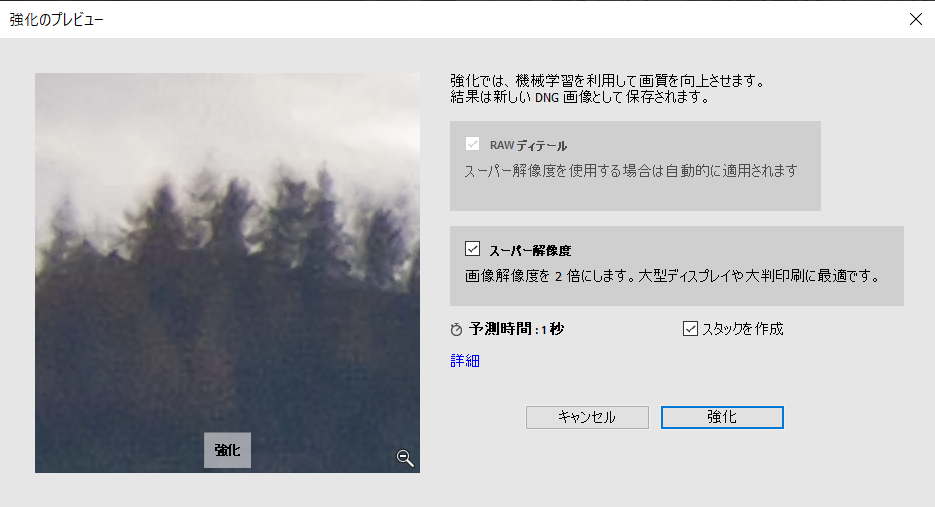10時すぎから楽しんだJMS2023も、そろそろ終了の19時が近づいてきました。
SUZUKI
変にオシャレな感じも気取った感じも意識高い系でもなく、実にSUZUKIらしい展示でした。
シニアカーに謎モビリティ、そして次期スイフトのコンセプト(ほぼこのまま出るのでしょう)、そして今後20年は売るであろうジムニー(写真は普通車のシエラ)、特段目を引くものはないけど、これがいつものSUZUKIです。
BMW
今回数少ない欧州勢の1つ、BMW。昔は好きだったメーカーで、いつかはM3に乗りたいと思っていましたが…もうデザイン的についていけないです。
まあ悪くないモデルもあるけど、中国で売ることを念頭にしているデザインは…
冒頭のコンセプトカーも何だかパッとしませんねぇ。
特段見るべきものがない…やっぱりスポーツモデルがないのが寂しいな。
MITSUBISHI MOTORS
一時期リコール隠しなどで低迷して、会社存続すら危うい感じだったMITSUBISHI MOTORSですが、もう方向性はSUV一色、これに尽きます。SUVブームに乗って、得意分野を猛アピールです。
Dynamic Sound Conceptが、DIATONEではなくYAMAHAと組んでいるのは、三菱グループ(特に三菱電機)から総スカンされた結果ですかね。逆にDIATONEもかつてカーオーディオのCMに登場させた車は外国車でした。
全てがSUVでした。ランエボみたいな車はもう出ないんだろうな。コンセプトカーのD:Xは次期デリカのイメージでしょうね。個人的に結構好きです。
NISSAN
話題の”チバラギ仕様”チャンプロードに出てきそうなGT-Rっぽい車両とか、次期型を開発しているのかエルグランドっぽいミニバンコンセプト、ん~って感じです。






なんだろうな、このモヤモヤ感。CGではかっこよく見えたのに、実車にしてみたらン?となってしまった感じです。
近年は、CADによるデザイン設計がふえて、クレイモデルはなるべく作らない方向になってきているようですが、やはり実際の感覚って大事です。
ということで、19時めいっぱいまで楽しみました。
Japan Mobility Show2023は、今週末まで開催です。3連休中も、まだの方はぜひ楽しんできてください。