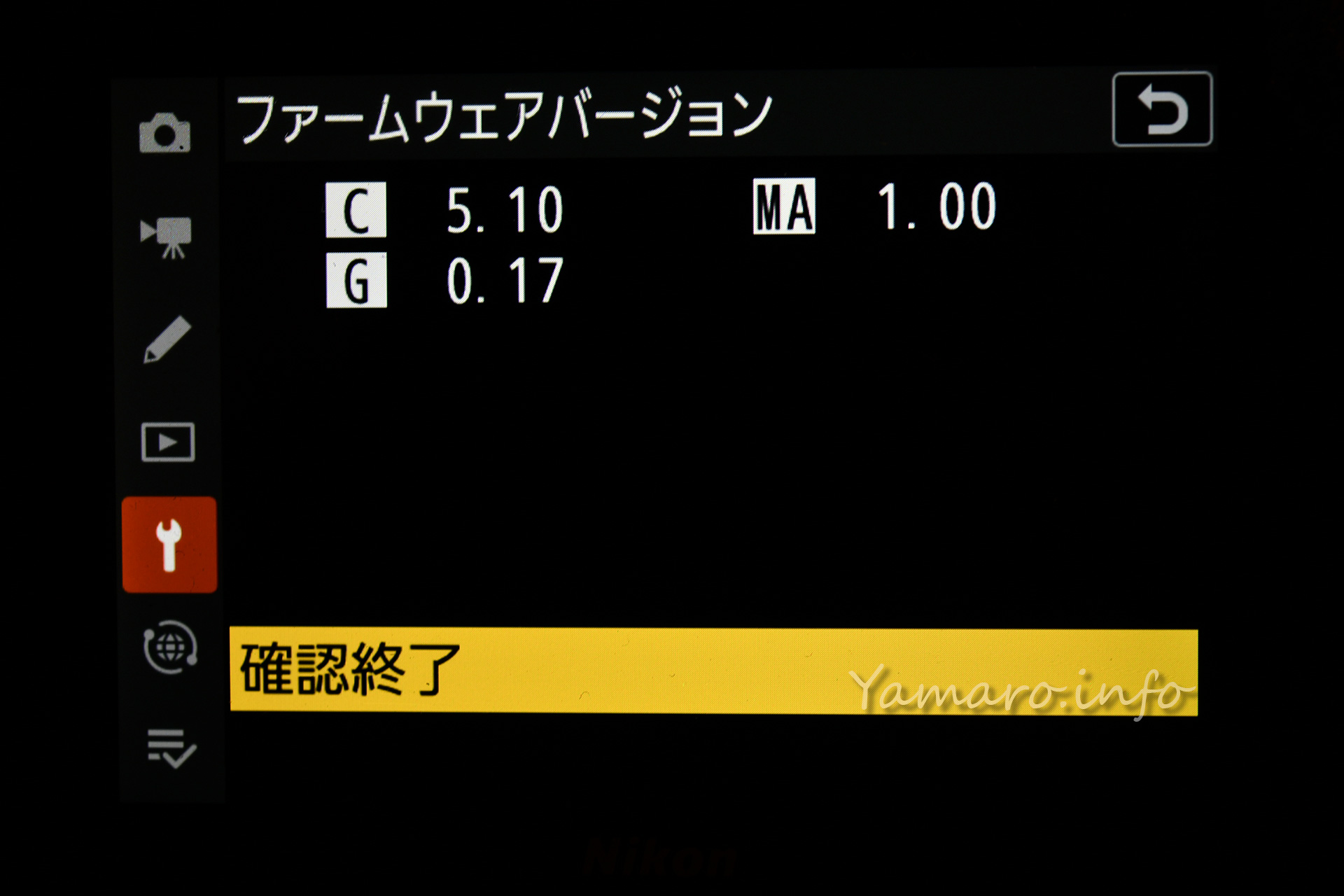昨年末、ちょっと時間があったときに書いていたお話です。
書きっ放しも何なので、放出。
文章が年末のままですが、あえてそのままにしておきます。
2024年も間もなく終わりですが、今年買ったカメラ関連のものは、アクセサリ類を除けば、ZマウントレンズのNIKKOR Z 35mm f/1.8Sの1本のみでした。
子供も大きくなって、だんだん子供と遊びに行く機会が減りつつあり、どちらかというと息子のサッカーの試合に飛行機撮影と、望遠レンズ主体が多かったですね。
娘の塾代も高額だし、将来に向けて貯蓄もしないととなると、カメラ関連はしばらく現状維持かなといったところです。あ、Nikon最後の純正スピードライトになるかもしれないSB-5000は抑えておきたいです。
一方、マイクロフォーサーズ(以下M4/3)のカメラはOLYMPUS E-P5が気に入り、その後PanasonicのLUMIX GX7 MarkIIに乗り換えてこれまた気に入り、次の世代のGX7 MarkIII(以下GX7MK3)はモデル末期になって後継機が出ないと知り慌てて購入しました。これが2021年4月の話です。
あれから3年半以上経過し、今でも愛用していますし、後継機がないので、これからも壊れるまで使うのかなとは思っています。
バッテリの蓋が外装の微妙な変形で開きづらくなっていますが、こういうところが華奢なのがLUMIXの欠点かなと個人的に思っていますが、このコンパクトなボディに操作性の良さが気に入っていて、動画画質もよいので、特段大きな不満はなかったりします。
GX7 MarkⅣが出たとして、果たして商品力はあるだろうか?

これが結局のところ、GX7 MarkIVが出ない最大の理由であると思います。GX7シリーズは、M4/3でも一眼レフのようなEVFのでっぱりがないコンパクトな機種としては高機能で、2コマンドダイヤルによる操作性の良さがありました。
しかし、値段を上げられない、値段を上げると売れない、これが販売上不利になる要因でした。
商品力とは単純に商品の魅力や性能だけではなく、切っても切れない販売価格も含まれます。そうなったときに、GX7シリーズのような高機能でコンパクト、だけど価格を上げるとAPS-C機と比較されてしまう、かといってGHシリーズほどの高機能は入れられない、このジレンマこそがGX7シリーズの最大の障壁でしょう。
現在、GX7シリーズに近い立ち位置にあるカメラはOMDS(旧OLYMPUS)のPEN E-P7で、これはかつて持っていたE-P5の実質的な後継機ですが、EVFはなく(オプションの外付けEVFもなし)、機能的にGX7MK3より優れている部分もないため、GX7MK3が壊れてどうしようもない場合の代替機かな、といったところです。
執筆時点でボディで8万円台、恐らくこの価格だと現在の資材高騰の時代に於いてあまり利益は出ないのかなと思います。かといって値上げしたらますます売れないでしょう。
今、そこそこコンパクトなAPS-Cミラーレス一眼がボディ単体で13万円前後で買えるので、値上げはE-P7にとっては不利でしかないわけです。
こんな状況から見ても、GX7MK4が12、3万円で出たところで、かなり厳しい戦いになるのが予想されます。値段を上げるにはそれなりの価値を正当化させる必要がありますが、動画機としてはセミプロ機としても使えるGH7が強いものの、GX7シリーズにそれを求めるにはいかず、かといって望遠レンズで撮るようなカメラでもない、となるとAPS-Cだけでなくスマホ相手でも不利な状況です。
加えて、今PanasonicのLUMIXのラインナップにはフルサイズミラーレスのSシリーズがあり、これもDC-S5初代では十数万円です。GH7はセミプロ機とも言える動画性能とスチル連写撮影の強みであの価格を正当化できていますが、それでも厳しい戦いです。
M4/3は商売的にもかなり難しい局面に来ています。小型さだけで売りになる時代ではなく、付加価値が求められます。そういった中で、GX7シリーズは機能はミドルクラスながら小型さはもはや売りとはならず、販売価格は上げられず、高級コンパクトに振るにもLEICA程の高級品ブランド力はない、だから売れない、売らない、となってしまっているのでしょうね。
仮にGX7MK4を出すとしても、実はそれほどやれることはない?
望みの限りなく薄いGX7MK4ですが、仮に出るとしたら、どういったスペックになるでしょう?
これはあくまで”僕が考えた最強のGX7 MarkIV”であり、こんなカメラが出るのは期待薄なので、戯言としてお読みください。
・2,520万画素像面位相差センサ搭載
2024年に発売されたG99M2は、イメージセンサは従来の2,030万画素センサで、このタイプのセンサは古く、像面位相差AFは搭載されていません。
しかしGX7シリーズの立ち位置からすると、さすがにGH7等に搭載される新世代の2,520万画素センサは欲しいです。これを搭載することで、4K120p動画も撮影可能となります。RAW動画はなくてもよいでしょう。H.265、あるいは新しいCodecであるAV1で撮影できればそれでよいと思います。
像面位相差AFを搭載することで、動態撮影、とくに動画AFはかなり改善されるはずです。イメージセンサを変えないと、MK3と代り映えしなくなってしまいますしね。
・EVFは据え置きでよいと思う
ここはコストのかかる部分です。GX7シリーズのアイデンティティとして、EVFを省くのは感心しませんが、下手に光学系の改善でコストアップも考え物です。
GX7シリーズのEVFはあくまで逆光など緊急時用、金をかけてしまうと上位機と値段が変わらなくなり、サイズも大きくなるので、ここ据え置きが妥当でしょう。
確かに光学系に金がかかっていないため、見づらいとか像が歪む、収差があるとかはあります。改善してほしい声も結構見かけましたが、改善して20万円になったらだれも買わないでしょう?
・USB Type-CとUHS-II対応は必須
Type-C化は時代の流れで避けられません。それでも、MarkIIIまでのMicroUSBで充電は出来ました。Type-Cになりさらに給電もできるとうれしいですね。
UHS-IIは、動画で4K60pを安定して撮るなら必要でしょう。連写によるバッファ開放もかなり速くなると思います。
・できれば外部マイク入力を
専用マイク端子でなくても、Type-Cにアダプタを経由する形であるとうれしいです。
TASCAMあたりに専用マイクやレコーダーを作ってもらうというてもあるでしょう。
これがあるとコンパクトながら、かなり動画機としても有利になります。
・Bluetoothで画像転送
Nikonと同様、WiFiにつながずBluetoothで転送できるようになれば、わずらわしいWiFi接続の工程を省けます。
GX7MK3はBluetoothがどうもつながりにくいため、そういった点も改善をして欲しいところです。
こうして挙げてみると、案外MarkIIIから大きく変わる部分は像面位相差AFが入る点くらいなんですよね。
だんだんとカメラの性能は頭打ちになりつつあるのがわかりますね。
M4/3の将来
M4/3アライアンスに加盟しているメーカーは、純粋な民生用カメラはOMDSとPanasonicの2社。日本国内での販売はないですが、スマホと組み合わせて使うカメラが海外に1社のみです。
あとはBlackmagic Designなどのシネカメラ、ライブカメラ、ハイスピードカメラ、小型カメラヘッドといった業務用になります。

そしてレンズは、かつてはサードメーカーからもいくつか販売されていたものの、そのほとんどが生産完了となってしまいました。今後サードメーカーからの販売は期待できなさそうです。
M4/3マウントのカメラが売れなければ、レンズも売れないわけで、サードメーカーは早々に手を引いてしまった感があります。
OMDSとPanasonicも、近年あまりレンズは多く出していません。
OMDSはOLYMPUSからの名称変更によるレンズの表示切替が主体で、2024年はM.ZUIKO DIGITAL ED 150-600mm F5.0-6.3 ISを出したのみ。しかもこのレンズはSIGMAのフルサイズ用のレンズの光学系を流用しているために大きく重く、M4/3に最適化された設計とは言えない上に、オリジナルのSIGMAよりも2.5倍も高額なためか、あまり売れていないようです。
OMDSはOLYMPUSから独立したものの、現状レンズの会社名表記変更に手いっぱいで、新規レンズの開発リソースがあまりないのでしょうね。
それでもボディはOM-1 MarkIIを頑張って出しました。
PanasonicもフルサイズのSシリーズの拡張を進めているところで、2024年にボディはGH7の1機種を出しましたが、レンズは出していないですね。2025年2月20日にG99M2の販売が予定されています。
今のところM4/3はすぐにはなくならないし、恐らくこれからも低空飛行で存続はすると思いますが、今後もレンズ交換式カメラの主流になることはないと思われます。
デジタルに最適化されたミラーレスマウントとして登場したM4/3でしたが、今はAPS-Cやフルサイズもミラーレスが主流となり、デジタルに最適化されたマウントという優位性も失われています。
業務用も採用されているため、そうした道で生きるというのも1つでしょうけど、趣味のカメラと考えた場合に、小さなセンサは難しいものがありますね。
OMDSは今年はOM-3の噂もありますし、盛り上げてほしいですけどね。