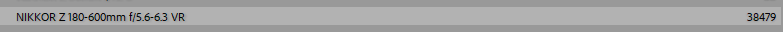この時期は日が短いですから、15時も過ぎると夕陽になってきました。早いなぁ、と思いつつ、3SQが再び動き出します。
ローカルの訓練なのか、航空祭向けなのか? 航空祭はこの時間はもう終わっているので、時間的にはもうやらんのかなと思いつつ、ちょっと期待しちゃいます。









先にT-4が上がりましたが、F-2戦闘機は待機。どうやらSKYMARKが先に上がるようです。



F-2戦闘機の1機が珍しくR/W03のL/Rの間で待機。そこにSKYMARKが来たけど、小回りがきくB737なので、眼の前でクルンとターンして上がっていきました。
F-2戦闘機はスペマ機を含む6機が待機。












夕陽に映えるF-2戦闘機が上がっていきます。
そして、やっぱりローカルの訓練ではなかった! 航空祭に向けての訓練ですね。フォーメーションにAGGとこなしていきます。
ああここまでやるなら、撮影場所ここじゃないほうが良かったか? まあ、それは本番にとっておきましょう。ここでしか撮れないものもあるということで。













パッカーンは真横で撮りたいな~。この時間のフライト、普段ローカルでこんな機動やらないので、もう心のなかではプチ航空祭、しかもこの夕陽に映える時間帯です。
終わりと思わせつつ、タッチアンドゴーで再び上がります。
いやぁこの時間、ホント絵になりますね。フォーメーションは4機、残りの2機は別行動でした。
せっかく夕方のこの時間、実はこの明るさでの戦闘機撮影は久しぶりの撮影、かつちょっと暗い望遠ズームのZ 180-600mmでは初めてなので、流し撮りで遊んでみました。
と言っても自分ができるのは1/125秒。腕の立つ方は1/30秒とかで流すんだからすごいですね。それでも何枚かはうまくいきました。
そして、本当に真っ暗にならない限り、開放f6.3のレンズでも、割とちゃんとAFが使えて迷うこともありませんでしたね。
Nikon Z 9もZ 8も、正直カタログスペックほど暗所AFが強いとは思えず、そこはまだD6とかD850クラスの一眼レフのほうが有利と思っていますが、食いついていればZ 8とかでも外すことはなかったですね。
ミラーレスの像面位相差AFは、フォーカス大外しからの復帰は苦手なようですが、そうでなければむしろコントラストAFも併用して食いつきは良いようです。
ってことでこの日の撮影は終了。満足の行く撮影ができた1日でした。
これは本番も楽しみですね~